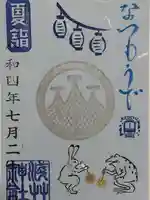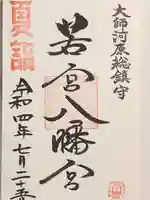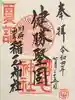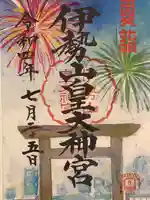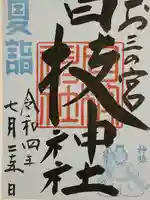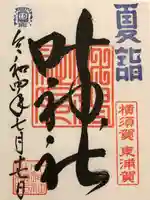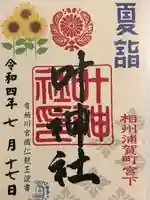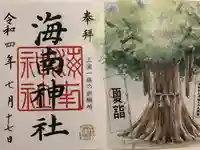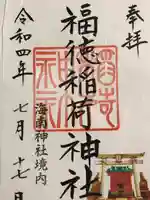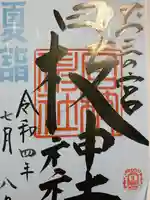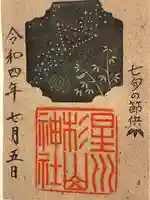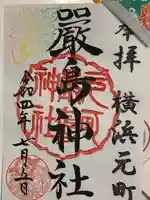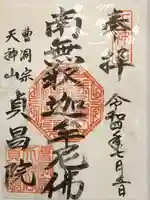御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方【サポーター特典】幸せと健康を毎月ご祈願
100年後に神社お寺を残せる未来へ![]()

100年後に神社お寺を残せる未来へ
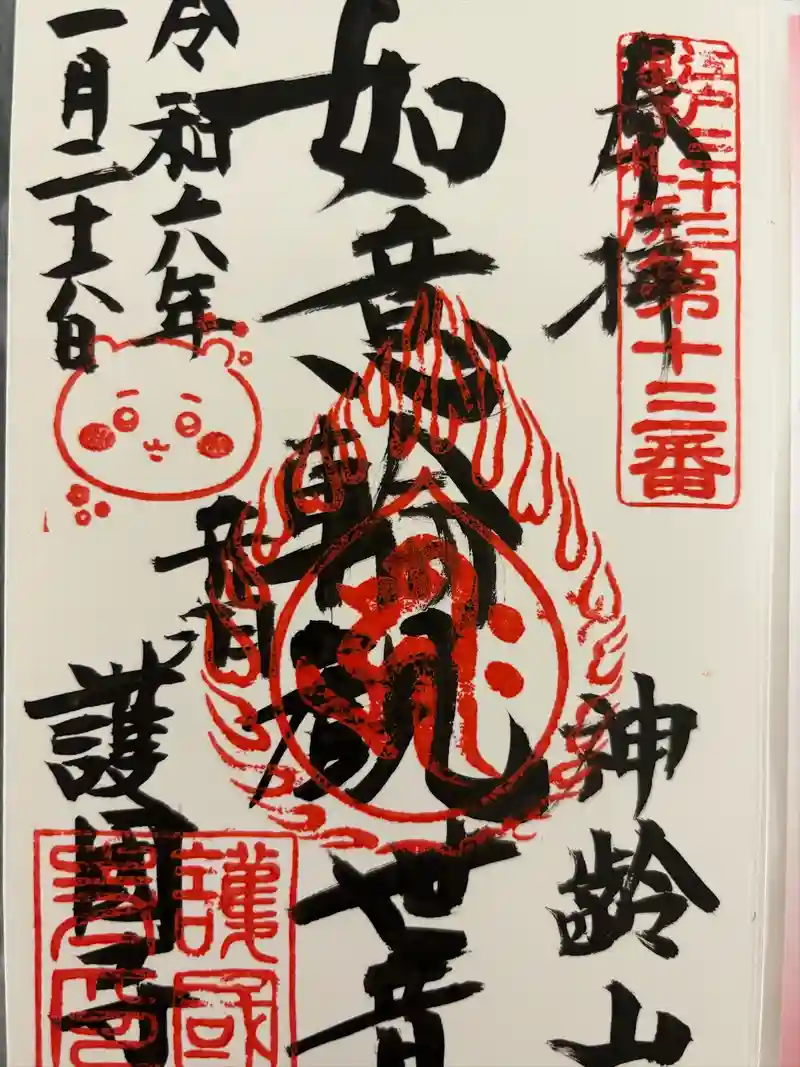

あずにゃんさん(3ページ目)
41件目から60件目を表示中(全96件)
2022年7月
57794
57794
57794
57794
57794
57794
57794
57794
57794
57794
57794
57794
57794
57794
57794
57794
57794
57794
57794
57794
※数値は1時間更新のため、最新のデータではありません
お参りした都道府県
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
投稿あり
10件以上
20件以上
100件以上
500件以上