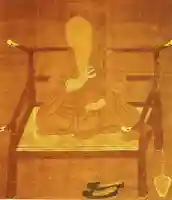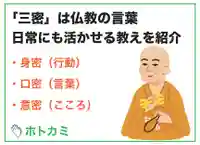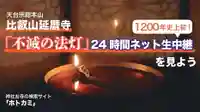初心者でも安心!写経とは?筆ペンと写経用紙セットを準備し、今すぐ写経を始めよう!
あなたは最近、ゆとりのある時間をすごしていますか?
忙しい日々のなかで心の余裕を持てず、
「写経をして心を落ち着けたい」と思ったことはありませんか。
しかし「写経を始めるために、なにを準備したらいいんだろう?写経の道具なんて持ってないし・・・」と、なかなか写経を始められない方や、
「どうせならお寺で写経してみたい!!」と、本格的に写経に取り組みたい方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
.jpg@webp)
しかし、せっかく写経に興味を持っても、 準備するものや書き方がわからないと、なかなか写経を始めることができないですよね・・・
というわけで、こんにちは。
高校生から仏教に関わってきた、ホトカミ編集部の仏教担当、横井です。
今回取り上げるテーマは
「写経」。
私の知人のNさんは、仕事におわれて職場と家を往復するだけの毎日。
もし休日があったら何をしようかと満員電車でInstagramを眺めていたところ、たまたま
「写経してスッキリした!」という投稿を見かけ、写経をやってみたくなったそうです。
ですが彼は小学校のとき、習字の先生に「集中力が足りない!」「基本は、とめ、はね、はらいだろ!」などと怒られつづけた思い出があるため
「うーん、写経かー、小学校のとき怒られまくって以来、習字苦手なんだよなぁー。いや、そもそも写経ってどうやったら始められるんだろう・・・」となかなか写経を始めることができないそうです。
彼の悩みは、
(できるだけ手軽に)写経を始めたい!
そこで今回は、Nさんのように写経を始められないあなたのために、
そもそも写経とは?という写経の基本から、写経の準備に必要なもの、写経の書き方、書き終わった紙の行方まで、
今すぐ写経を始めるために必要な情報をすべて紹介します。
この記事を読めば、お寺だけではなく、ご家庭でも簡単に写経を始めることができますよ。
写経したことない!という初心者の方に加えて、本格的に写経したいというベテランの方向けの情報もまとめました。
ぜひ、最後まで読んでみてください。
それでは、さっそく写経について紹介していきます!
すぐに「写経の準備に必要なもの」「写経の書き方」が知りたい方は、以下からどうぞ。
写経に必要なものはコチラ≫
写経の方法はコチラ≫
【47都道府県別】写経を体験できるお寺まとめ

ホトカミ編集部仏教担当
横井 郷
愛知県出身の仏教系大学生。一般家庭出身だがさまざまなご縁により仏教に興味を持ち、
あらゆる視点から仏教の可能性を追求している。
好きな仏さまは蔵王権現(ざおうごんげん)。
写経とは?写経の意味や効果を徹底紹介!
写経とは、文字通り「仏教のお経を書写する」こと
それではまず「写経ってそもそも何なのか?」紹介します。
写経とは、文字通り「仏教のお経を書き写す修行」のことです。
簡単にいうと、お経を筆で書き写すということですね。
そして、写経では、
般若心経(はんにゃしんぎょう)というお経を書くのが一般的です。
たくさんあるお経のなかで、なぜ般若心経が一般的かというと、
お経の文字数が300字程度で、およそ1時間ほどで書ける長さだからです。

写経は修行!?
写経とは「仏教のお経を書き写す修行」と紹介しました。
では「なぜ、写経をすることが修行になるのでしょうか?」
写経が修行になる理由を知るために、まずはお経について知りましょう。
(これには諸説ありますので、あくまで一説とお考えください。)
お釈迦さまの教えである「お経」が生まれるまで
およそ2500年前、インドで仏教を開いたお釈迦(しゃか)さまが生きていた時代のお話です。
お釈迦さまは悟りを開いてから亡くなるまでの間、
多くの人々に教えを伝え、
仏教はお釈迦さまを中心に成り立っていました。

しかし、お釈迦さまが亡くなってしまうと、その教えがバラバラになってしまいます。
そこで、お釈迦さまが亡くなったのち、弟子たちによってお釈迦さまの教えがまとめられました。
このお釈迦さまの教えをまとめたものを、お経といいます。
しかし、この時点ではまだお経は文字に書き起こされていませんでした。
なぜなら当時の人々は、お経を文字に書くことは良くないと考えていたからです。
そのため、お経はすべて頭の中で暗記し、口伝えで人々に広まりました。
昔の人はお経を丸暗記していたなんて、すごいですね!
写経の始まりと発展
お釈迦さまが亡くなって400年ほど経った紀元前1世紀ごろ(だいたい2000年前)に、
ようやくお経が文字で書かれるようになりました。
さらに、仏教を広めるために、お経がどんどん書き写されていくようになりました。
お経を書き写していくようになったのが、
写経のはじまりです。
しかし、お経は種類もたくさんあり、すべての教えをまとめようとすると、
とても一人では書き写すことができないほどです。

一人で書き写すのは難しい・・・ということは、みんなで力を合わせて書き写すしかありませんよね。
そのため大きなお寺や権力者が、みんなで写経するための写経所(しゃきょうしょ)をつくりました。
そのおかげで、多くの人が写経できるようになり、結果として書き写されたお経も増えました。
それらのお経は、インドを超えて、外国にも広がっていきます。
「猿とカッパと豚を連れて、ありがたいお経を取りに行くお話に、聞き覚えはありませんか?」

西遊記の物語に登場する三蔵法師のモデルとなった
玄奘(げんじょう)というお坊さんは、お経をインドの言葉から、中国の言葉である漢字に翻訳しました。
みなさんが写経をする般若心経も三蔵法師の玄奘さんによって、翻訳されたんですよ。
写経は、西遊記のお話とも繋がっているんですね。
さらに、仏教で重要なお経のひとつである「法華経(ほけきょう)」のなかには、
「写経すると、良いことがあるよ」と書かれています。

このように、写経、つまりお経を書き写すことは、昔から大切にされていたんですね。
ここまでの話をまとめると、
「写経は、お釈迦さまの教えを残し、その教えを広めるために書き写そう!」ということから始まりました。
そして、仏教が発展するなかで、
「写経そのものに意味があり、写経も大切な修行だ」と考えるようになりました。
写経というのは、2000年以上続く、仏教の大切な修行なんですね!
ここまで、写経はどんなものか紹介してきました。
それでは、写経にはどんな効果があるのでしょうか?
写経では、字がキレイになるだけでなく、医学的にも
「心の安定」「脳の活性化」などにも効果があると解明されています。
それでは、写経の効果について、くわしく見ていきましょう!
2000年続いてきた秘密が隠されているかもしれませんね。
写経は心を落ち着け、脳を鍛える効果アリ!
写経を続けていると、さまざまな効果が期待できます!
その効果について一緒に見てみましょう。
- 字がキレイになる
- 心の安定に効果あり
- 脳の活性化に効果あり
1、字がキレイになる
多くの字を書き写す写経を続けることで、字がキレイになります。
写経では、一文字一文字を丁寧に書くことを心がけます。
丁寧に書くことを意識すれば、自然と字がキレイになっていきます。
さらに、お経には、日常では書かないような難しい漢字も多くあります。
それらの難しい漢字をバランスなどを考えながら書くことよって、日常で書くような簡単な漢字はキレイに書けるようになるかもしれません。
2、心の安定に効果あり
写経をしているあいだは、書くことに集中しています。
写経をしているとき、他のことを考えてしまうなど集中が途切れると、
その心の乱れは文字になってあらわれます。
自分で書いた文字を見ることで、自分の心を見つめることができるのです。
そのため写経を通じて自分の心の状態に気づくことにより、
心を安定させることができます。
3、脳の活性化に効果あり
ある研究によると「写経をしているときは、普段よりも脳が活性化している」ということがわかっています。
これは、写経をしているとき、脳に流れる血液の量が増えるからです。
また、写経は意識を集中させ、手を動かすトレーニングとしても適しているため、
認知症の予防や脳を鍛えることにも効果があります。
写経をすることによって、字がキレイになるだけでなく、心も安定し、脳も活性化するんですね。
それでは、写経の意味や効果がわかったところで、
「写経を始めるために必要な準備」について紹介します!
【47都道府県別】写経を体験できるお寺まとめ
写経の準備~これだけあれば写経はできます!~
実は、写経を始めるために必要なものは、そんなに多くありません。
なんと「筆ペンとお手本がセットの写経用紙」さえあれば、今すぐに写経を始めることができます。
今回は初心者向けの写経セットに加えて、
本格的に写経をしたい人向けにも、写経に必要な道具を紹介します。
【初心者】筆ペン・写経用紙・お手本があれば、今すぐ始めることができます!
とにかく今すぐにでも写経を始めたい方は、
「筆ペンとお手本がセットの写経用紙」をそろえましょう!
「筆ペンとお手本がセットの写経用紙」は、近くの文房具店や100円ショップなどでも手に入れることができます!

まずは、筆ペンとお手本がセットの写経用紙について、詳しく説明します。
筆ペン
写経のときに書く文字は小さいので、細めの毛筆タイプの筆ペンがオススメです!
筆ペンが一本あると、封筒などの宛名書きなどにも使えますよ。
コンビニで買うことができます。
お手本がセットの写経用紙
写経をするときは、写経に適したサイズの写経用紙がオススメです。
また、写経用紙には、写経のお手本がセットのものもあります。
このお手本を写経用紙の下に敷いて、なぞることで、初心者でもキレイな字で写経ができます。

また、写経用紙の種類には、
・お手本が薄く印刷されているもの
・縦に線が入っているもの
・白紙のもの、など様々なタイプがあります。
初心者は、なぞり書きや、お手本が薄く印刷されたものから始めることをオススメします。
写経に慣れてきたら、線入りや白紙の写経用紙をつかい、なぞらずに、お手本を見ながら写経してみても良いかもしれません。
必要なものは、「筆ペンとお手本がセットの写経用紙」です。
たったこれだけで写経を始めることができます!
まずは「筆ペンとお手本がセットの写経用紙」を準備して写経を始めてみましょう!
ちなみに、「ペンで書いてみる写経」といった書き込み式の本も出版されています。書き込み式の本でも簡単に写経を始めることができますよ。
次に、慣れてきた方向けに、本格的な書道セットについても紹介します。
写経の書き方はコチラ≫
【本格派】書道セットを用意しよう!
筆ペンでの写経に慣れてきたら、本格的に筆を使って写経したくなりますよね。
筆を使って本格的に写経を始めるためには、小学生の書道のときに使っていたような書道セットが必要です。
書道セットは、Amazonや楽天のようなネット通販でも購入することができます。
改めて、書道セットの中身を見てみましょう。
筆(ふで)
写経は細かい文字をたくさん書くので、オススメはかための筆で、毛の部分が短い細い筆です。(※太い方の筆ではないことに注意)

墨汁(ぼくじゅう)
墨汁とは、すぐに使える液体の墨です。
墨汁は墨をする必要がないので、手軽に毛筆で写経に取り組むことができます。

硯(すずり)
墨汁を使う場合は、書道セットのプラスチックの硯で十分です。
硯を新しく買う場合、写経では多くの墨汁を必要としないため、小さな硯でも構いません。

下敷き
下敷きは、墨がにじんだときに吸い取り、文字を書きやすくするために必要です。
下敷きの種類には、かためで洗うことができる織布のラシャ製と、やわらかく弾力があり高級感もあるが、洗えない不織布のフェルト製があります。

文鎮(ぶんちん)
文鎮は、しっかり写経用紙を固定するために必要です。
形状は、一般的なもので構いません。

さらに道具にこだわりたいアナタは、より本格的な道具を揃えてみてはいかがですか?
ここでは、自分で墨をすりたい方向けに、固形の墨と天然石の硯を紹介します。
固形の墨
写経に慣れてきたら、自分で墨をすってみるのもいいですね!
墨をすると、心を落ち着ける効果もあります。
ほかにも、自分で墨の濃さを調整できるなど、自分のこだわりを出すことができます。

天然石の硯(すずり)
墨をするときは、天然石で作られた硯(すずり)が、固形の墨との相性が良いです。
プラスチック製やセラミック製に比べ、天然石の硯は墨をするのに適しています。
主に国産か中国産のものがあり、1000円程度のものから、数十万以上の高価なものまであるので、自分の財布事情に合わせて選びましょう。
ここまで見てきた書道セットは、ネット通販でも購入できますが、書道用品店に行き、店員さんと相談しながら選んでみても良いかもしれません。
ここで忘れてはいけないこと。
写経において大切なのは、高価な道具を揃えることよりも、心を込めて写経に取り組むことです。
お手持ちの道具があれば、それでかまいませんので、まず始めてみましょう。
さらにこだわりたい方は少しずつ道具を揃えていくのがいいですね。
写経に必要なものが準備できたところで、
いよいよ、写経のやり方について解説します!
【47都道府県別】写経を体験できるお寺まとめ
いざ、写経に取り組もう!
写経のやり方
写経に取り組む準備ができたら、いよいよ実際に書いてみましょう。
今回は、まずは初心者向けのやり方と、仏教の作法に合わせた本格的なやり方を紹介します。
しっかり説明を読んで、写経を始めましょう!
【初心者】まずは写経を始めてみたい方向けのカンタンお作法
1、気持ちの準備
まず、イスや座布団(ざぶとん)に楽な姿勢で座ります。
次に、深呼吸をし、リラックスした状態をつくります。
心が落ち着いたら手を合わせて合掌し、一礼します。
写経と向き合い、集中できる状態にします。
2、お経を書き写す
写経に落ち着いて取り組む準備ができたら、写経を始めます。
表題(お経のタイトル)から順番に、お経を書き写していきましょう。
ゆっくりでもかまいません。心を込めて丁寧に書くことを大切にしてください。

3、さいごに願文(がんもん/お願い事)を書く

お経を最後まで書けたら、次の行に一字下げて「為」と書きます。
お願い事がある場合、ここにお願い事を書きましょう。(家内安全、商売繁盛、身体健全など)
お手本によっては「右為」などとなっている場合もありますが、意味は同じです。
お願い事がない場合、書かなくても構いません。
4、日付と名前を書く
願文(がんもん/お願い事)の次の行に日付を書き、また次の行に名前を書きます。
名前の下には謹写(きんしゃ / 謹んで書写させていただきましたという意味)と書きます。
お手本によっては、日付と名前の場所が違ったりするものもあります。
その場合はお手本通りに日付と名前を書いてください。
5、写経を終える
手を合わせ合掌し、一礼をして写経を終わります。
【本格派】仏教の作法に合わせた写経のやり方
カンタンなお作法での写経に慣れてきた方は、仏教のお作法にあわせた方法で写経をしてみましょう!
お経を唱えたりすることにより、よりしっかりとした気持ちで写経に取り組むことができますよ。
最初は難しく感じるかもしれませんが、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
1、気持ちの準備
まず、イスや座布団(ざぶとん)に楽な姿勢で座ります。
次に、深呼吸をし、リラックスした状態をつくります。
心が落ち着いたら手を合わせて合掌し、一礼します。
写経と向き合い、集中できる状態にします。

2、墨をする
(墨汁を使う場合や筆ペンを使う方は次の3に進んでください。)
水を硯(すずり)にとり、静かに墨をすります。
10円玉ほどの水を落とし、力を入れずに静かにすります。
ちょうどよい濃さになれば、また水を足し、必要な墨の量になるまで繰り返します。
3、お経を読む
手を合わせ、写経するお経を読みます。
声に出しても、心の中で唱えても構いませんので、手を合わせてお経を一回読みます。
4、お経を書き写す
表題(お経のタイトル)から書き写します。
一字一字、お経を最初の行から書き進めていきます。
ゆっくりでもかまいません。心を込めて丁寧に書くことを大切にしてください。

5、さいごに願文(がんもん/お願い事)を書く

最後まで書けたら、次の行に一字下げて「為」と書き、願文(がんもん/お願い事)を書きます。
写経をすることが目的で、とくにお願い事がなければ書かなくても結構です。
(家内安全、商売繁盛、身体健全など)
6、名前と日付を書く
次の行に名前を書き、また次の行に日付を書きます。
名前の下には謹写(きんしゃ / 謹んで書写させていただきましたという意味)と書きます。
7、回向文(えこうもん)を唱える
回向文とは、最後に唱えるお経です。
自分の良い行いが、あらゆる人にも届きますようにという意味です。
合掌しながら、声に出すか、心の中で唱えてください。
「願以此功徳 普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道」
「がんにしくどく ふぎゅうおいっさい がとうよしゅじょう かいぐじょうぶつどう」
(意味:自分の良い行いが、この世のありとあらゆるすべてのものに届き、みんなと一緒に仏さまの道を歩めますように。)
お念仏を唱える浄土宗、浄土真宗ではすこし内容が変わり、
「願以此功德 平等施一切 同發菩提心 往生安樂國」
「がんにしくどく びょうどうせいっさい どうほつぼだいしん おうじょうあんらっこく」
(意味:自分の良い行いが、分け隔てなく施され、一緒に仏さまの心をおこして、極楽の世界にいけますように。)
8、写経を終える
手を合わせ合掌し、一礼をして写経を終わります。
以上が写経の流れになります!
宗派やお寺、書籍などによっては、作法や準備などが違う場合があります。その場合は、詳しい方に聞きましょう。
それでは、写経の流れがわかったところで、実際に写経にチャレンジしてみましょう!
写経は、自宅で取り組むこともできますし、お寺の写経会に参加する方法もあります。
ご自宅で取り組む場合と、お寺の写経会に参加する方法についてご紹介します。
自宅で写経に取り組む場合
自宅で写経を取り組むときは、部屋をきれいにし、写経に集中できる環境を整えることが大切です。
仏壇がある部屋であれば、お線香をあげることも良いでしょう。
自宅で写経した場合、書き上げた写経をどうしたらいいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか?
書き上げた写経は、大切に扱いましょう。
床に置いたり、くしゃくしゃにするなど粗末に扱ってはいけません、
写経用紙は、仏壇にお供えするのも良いですし、お寺に持って行き、奉納するのも良いでしょう。
また、うまく書けたら額に入れて飾ることも良いですね!
お寺によっては、書き終えた写経の奉納を受け付けています。数百円ほどの奉納金で、仏さまの前で供養していただくことができます。
お寺に奉納したい方は、住職さんに相談してみてください。
お寺に奉納できない場合は、一度手を合わせてから、丁寧に畳んで捨てましょう。
(本当は、捨てるという表現は適切でないですし、捨てて欲しくはないのです。しかし、お寺に縁のない人は仕方がないので、捨てると表現しました。できれば、ホトカミを通じてお寺とのご縁を結んでいただきたいです。)
お寺で写経に取り組む場合
日本各地のお寺では、たくさん写経会が開かれています。
また、いつでも写経ができるお寺もあります。
お寺での写経会に参加することで、お坊さんに写経について、直接教えてもらうことができます。
さらに、お寺で写経をする場合、写経のための道具が用意してあったり、正座が苦手な方や足が悪い方のために、イスで写経体験できるお寺もあります。
写経会に参加するのに必要な奉納金はお寺によってさまざまですが、
おおよそ1000円から2000円のお寺が多いようです。
写経ができるお寺はコチラ≫
写経を自宅で行う場合も、お寺で行う場合も、実際にやってみるとわからない点がいろいろ出てくるかもしれません。
次に、写経でよくある質問とその答えを紹介します。
【47都道府県別】写経を体験できるお寺まとめ
写経でよくある質問


しかし、仏教ではお経を大事にするので、たとえ途中であってもゴミ箱などに捨ててしまうのはよくありません。
誤字脱字のときは、字を訂正する作法がありますのでご紹介します。

- 誤字の右に点を打ち、同じ行の上下どちらかの余白に正しい字を書く。
- 脱字の場合、文字と文字の間に点を打ち同じ行の上下どちらかの余白に正しい字を書き、点を打つ
万が一、どうしても写経用紙を捨てる場合は、一度手を合わせてから、捨てるのが良いです。


そのため、初心者には般若心経を写経することをオススメします。
しかし、もちろん般若心経以外のお経でも構いません。
仏教には、八万四千の法門(はちまんしせんのほうもん)とよばれるほど、たくさんのお経があります。
法華経(ほけきょう)やお題目(おだいもく)、阿弥陀経(あみだきょう)や重誓偈(じゅうせいげ)、正信偈(しょうしんげ)といったお経や偈文(げもん)など、般若心経以外のお経を写経することもよいでしょう。
般若心経以外のお経を写経したい方は、本屋さんや各宗派のホームページなどでお手本を手に入れることができます。


お墓へ写経を納める方法は、願い事の欄に、為○○信士(戒名、法名)供養と書き、写経した紙を骨壺(こつつぼ / お骨を入れるつぼ)の下に敷きます。
納骨のときの方法など、詳しくは菩提寺(ご先祖様のお位牌があるお寺)や、ご近所のお寺のお坊さんにお尋ねください。


自分の書きやすい紙を選んで写経しましょう。


しかし、漢字は右利きで書かれることを想定してつくられているため、左で書くと、はねやはらいが書きにくく感じるかもしれません。
しかし、左手で書いても大丈夫です。
写経の体験できるお寺7選
ここからは境内で写経ができるお寺を7ヶ寺紹介します。
新型コロナウイルスの影響で、写経を中止しているところもありますので、最新の情報をご確認のうえお参りください。
また、写経を郵送で納めることで、納経の証として御朱印を頒布しているお寺もあります。
以下の記事で紹介しているので、ぜひお読みください。
御朱印の郵送対応可能な神社お寺5選!写経して限定御朱印をいただこう
大龍寺(東京都 早稲田駅)

以前ホトカミで取材させていただいた曹洞宗のお寺です。
大龍寺のインタビュー記事はコチラ
座禅会と同じ日に写経会もおこなっています。
住職のやさしい指導の下、落ち着いた雰囲気で写経をすることができます。
【宗派】曹洞宗
【奉納金】お気持ち
【開催日時】6週間毎
【予約】要予約
【アクセス】東京メトロ東西線早稲田駅(2番出口)、都営大江戸線若松河田駅(若松口)徒歩7分
【ホームページ】大龍寺Facebook
大龍寺ブログ
【ホトカミ】大龍寺
大雄院(茨城県 日立駅)

境内で写経をすると季節の限定御朱印をいただけます。
本来のあり方である「納経の証としての御朱印」を大切にされおり、納経必須で御朱印を頒布しているお寺です。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での納経も受け付けていました。
※2020年7,8月は法要の準備でお忙しいため、御朱印の受付を停止しています
【宗派】曹洞宗
【奉納金】1,000円以上(御朱印希望の場合別途かかります)
【開催日時】毎日9時~15時半まで随時
【予約】予約不要
【アクセス】日立中央ICより車で5分
日立駅より車で10分
【ホームページ】大雄院
【ホトカミ】大雄院
深川不動堂(東京都 門前仲町駅)

千葉にある、成田山新勝寺の東京別院として、多くの参拝者が訪れるお寺です。
写経だけではなく、仏さまの絵を写す写仏を体験できたり、ご祈祷もしていただけるなど、さまざまな体験ができるお寺です。
【宗派】真言宗
【奉納金】2000円以上
【開催日時】毎日9時~14時まで随時
【予約】予約不要
【アクセス】東京メトロ東西線「門前仲町」駅1番出口より徒歩2分
都営地下鉄大江戸線「門前仲町」駅6番出口より徒歩5分
【ホームページ】深川不動堂
【ホトカミ】成田山深川不動堂(新勝寺東京別院)
永平寺(福井県 永平寺口駅)

座禅を大切にするグループである禅宗の一派、曹洞宗の大本山です。
禅宗について詳しく知りたい方はコチラ
神奈川県の總持寺と、この永平寺が曹洞宗の重要なお寺、大本山です。
今でも多くのお坊さんが修行しているお寺なので、引き締まった気持ちで写経をすることができます。
【宗派】曹洞宗
【奉納金】1000円 ※拝観料別途
【開催日時】随時、参拝時間に従う
5月~10月 8時~17時30分
11月~4月 8時30分~17時
【予約】予約不要
【アクセス】えちぜん鉄道・勝山永平寺線「永平寺口駅」から、京福バス「永平寺門前行」または「永平寺行」に乗り換えて終点下車、徒歩5分。
福井駅より直行バスにて30分
【ホームページ】大本山永平寺
【ホトカミ】永平寺
薬師寺(奈良県 西ノ京駅)

西遊記にも登場し、般若心経を翻訳した中国のお坊さん、玄奘(げんじょう)が開いた宗派である法相宗(ほっそうしゅう)のお寺です。
写経道場では毎日写経を体験することができます。
特に、毎月8日の薬師如来の縁日の写経会では、管主(住職)さんのお話を聞くことができます。
また、薬師寺の写経道場は椅子席も用意されていますので、膝が悪く、正座ができない方などにもやさしい道場となっています。
【宗派】法相宗
【奉納金】2000円以上 ※拝観料別途
【開催日時】随時、参拝時間に従う 8時30分~17時(拝観受付 16時半まで)
【予約】予約不要
【アクセス】近鉄西ノ京駅下車すぐ。
【ホームページ】薬師寺
【ホトカミ】薬師寺
觀音寺(徳島県 立道駅)

徳島県にある高野山真言宗のお寺で、建物内の天井絵は必見です。
写経だけではなく、真言宗の瞑想法である阿字観の体験や護摩祈祷なども行っています。
ぜひお参りください。
【宗派】高野山真言宗
【奉納金】500円
【開催日時】月に一度 日程は ホームページ のお知らせを確認
【予約】予約不要
【アクセス】徳島鳴門インターチェンジより車で10分
徳島県内ならカーナビで觀音寺088-699-2280にて誘導に従って来寺
【ホームページ】法話と天井絵の寺 觀音寺
【ホトカミ】法話と天井絵の寺 觀音寺
仁和寺(京都府 御室仁和寺駅)

真言宗御室派の総本山である仁和寺は、長い間皇室出身者が代々住職(門跡)を務めていたこともあり、日本国内でも格式が高いお寺として有名です。
境内には遅咲きの桜、御室桜が植えられており、桜の名所としても有名です。
【宗派】真言宗御室派
【奉納金】1000円
【開催日時】毎月第3木曜日開催 午前10時30分〜正午(受付:午前10時〜10時25分)
【予約】電話(TEL:075-463-1095) またはメール(hana@ninnaji.jp)で要予約
※ 開催日の2日前(火曜日)までに申し込みが必要
【アクセス】嵐電 御室仁和寺駅より徒歩3分
【ホームページ】仁和寺
【ホトカミ】仁和寺
おわりに
いかがでしたか?
写経は字がキレイになるだけでなく、自分自身と向き合い、心を落ち着かせるなどの効果があります。
そして、「筆ペンとお手本つきの写経用紙」を準備するだけで、今すぐ写経を始めることができるんです!
この記事を読んだ方が、写経を始めることができたら嬉しいです。
お読みいただき、ありがとうございました!
【47都道府県別】写経を体験できるお寺まとめ
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。