御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方菩薩とは?弥勒菩薩や観音菩薩など7種類の有名な仏様を徹底解説
※記事中に使用したイラストの無断転載を禁止します。
「菩薩ってどんな仏様?」
「観音菩薩は他の菩薩と何が違うの?」
「それぞれの違いを知って、お寺めぐりをもっと楽しみたい」
全国8万ヶ寺以上のお寺を紹介する日本最大の神社お寺・御朱印の検索サイト「ホトカミ」編集部の高原です。

お寺を訪れると、「〇〇菩薩」と書かれた仏像を目にすることがよくありますよね。
その姿はそれぞれ個性的ですが、「どんな意味が込められているのだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、ひとくちに仏像と言っても様々な種類があり、菩薩だけでも13種類以上あります。
数は多いですが、
「足を組んでいるのは弥勒菩薩で、深く考えている様子を表す」
というように、いくつかの特徴を知るだけで、菩薩の見分け方や込められた意味が理解できるようになります。
仏像ごとの違いやその背景も知ることで、お寺への参拝がより楽しく、深い体験になるはず。
ぜひ最後までお読みいただき、実際にお寺を訪れてみたください!
- 悟りを求める「菩薩」の基本を解説
- 個性豊かな菩薩たちを紹介!
- 一般的な7つの菩薩
- 弥勒菩薩(みろくぼさつ):仏教版「考える人」・足を組み、右手は頬
- 普賢菩薩(ふげんぼさつ):白い象の上で合掌
- 文殊菩薩(もんじゅぼさつ):獅子に乗り、右手には剣
- 虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ):座禅を組み、左手に玉
- 地蔵菩薩(じぞうぼさつ):坊主頭・杖・玉の3点セット
- 日光・月光菩薩(にっこう・がっこうぼさつ):薬師如来の両隣
- 7つの観音菩薩
- 【決して誰も見捨てない!】菩薩の起源
- 【如来のサポート役】菩薩の役割
- おわりに
目次
御朱印・神社お寺の検索サイト「ホトカミ」について
ホトカミは 日本全国14万件の神社お寺、1万9000件の御朱印の情報のなかから次にお参りしたい神社お寺を検索できるサイトです。
「100年後に神社お寺を残す」ために、日本全国の皆さんに神社お寺の魅力を伝えています。
全国のユーザーさんが想いを込めてホトカミに投稿して下さった情報をもとに、すてきな神社お寺を紹介中。
さらに、ホトカミは日本全国1400人以上の神主さんお坊さんからの公式情報も集まっています。
ホトカミを通じて、全国の神社お寺と読者の皆様のすてきなご縁が結ばれますように。
神社お寺を都道府県から探す≫
この記事はホトカミサポーターさんのおかげで公開できました!

〈ホトカミサポーターとは〉
「100年後に神社お寺を残そう」というホトカミの理念に共感し、ホトカミの今後を応援してくださる方に、毎月500円からサポートしていただく仕組みです。
【サポーター限定の特典】
プレミアム検索機能では、切り絵・刺繍御朱印・一粒万倍日など、こだわりの御朱印がある神社お寺を、20種類以上の項目から見つけられます。さらに、神さま・仏さま・宗派からも検索可能。(無料お試しあり)
このほか「毎月あなたの幸せと健康をご祈願」「お気持ちで特典(全国の寺社からサポーター限定の特典)」「バナー広告の非表示」があります。
悟りを求める「菩薩」の基本を解説!
仏像は上から「如来」「菩薩」「明王」「天部」の4つの階層に分かれています。

今回の記事で紹介する菩薩たちは、上から2番目の位に属しています。
菩薩は基本的に出家をする前のお釈迦様の姿をしています。
出家前のお釈迦様は釈迦族の王子であったため、華やかな見た目をしています。
菩薩は悟りを求めて修行中
菩薩は「悟りを求める」仏様です。
自らの悟りを求めるために修行をしつつ、他の人をも悟りへと導くという意味があります。
サンスクリット語では「ボーディサットバ:bodhisattva」と言われ、
・bodhi=悟り
・sattva=人
の2つの言葉を合わせて「悟りを求める人」と言われるようになりました。
菩薩は【アクセサリー】:ファッショナブルな姿

菩薩(ぼさつ)とは、悟りを求めつつ人々を救済する、出家する前のお釈迦様(ゴータマ・シッタールタ)の姿をしている仏像です。
「菩薩=悟りを開く前」と覚えましょう。
菩薩を見分ける5つのポイント
菩薩は個性豊かな姿をしていますが、それぞれ共通しているポイントもあります。
ここでは、菩薩に共通する5つのポイントをご紹介していきます。

-
菩薩を見分ける5つのポイント
①高く結い上げた髪:宝髻(ほうけい)
②宝石で飾り付けられた冠:宝冠(ほうかん)
③宝石で飾り付けられたネックレス:瓔珞(ようらく)
④肩からかけているスカーフのような布:天衣(てんね)
⑤腰に巻いているスカートのような衣:裳(も)
出家前のお釈迦様はインド釈迦族の王子であったため、
如来と比べて綺麗な服装やアクセサリーを付けています。
ここからは、菩薩ごとの見分け方や特徴について解説していきます。
個性豊かな菩薩たちを紹介!
菩薩には、一般的な菩薩と観音菩薩の2つのカテゴリー分類することができます。
まずは、一般的な菩薩から紹介していきます。
一般的な7つの仏像

一般的な仏像には
・弥勒菩薩(みろくぼさつ)
・普賢菩薩(ふげんぼさつ)
・文殊菩薩(もんじゅぼさつ)
・虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)
・地蔵菩薩(じぞうぼさつ)
・日光菩薩(にっこうぼさつ)
・月光菩薩(がっこうぼさつ)
があります。
ここからはそれぞれの見分け方と特徴を紹介していきます。
弥勒菩薩(みろくぼさつ):仏教版「考える人」・足を組み、右手は頬

弥勒菩薩は未来の世界を救う仏様です。
弥勒菩薩は【仏教版 考える人】です。
飛鳥・奈良時代の弥勒菩薩の多くは
・足を組んでいる
・右手は頬
のように半跏思惟像(はんかしいぞう)と呼ばれる深く考え込む様子を表す姿をしています。
ちなみに、「半跏」とは片足を組んで座ることを意味します。
平安時代以降に作られた弥勒菩薩は、他の菩薩と同じように立像になっていたり、華やかな姿をしていたり見分けが難しくなります。
弥勒菩薩は半跏思惟像であることが多いため、
【弥勒菩薩は半跏思惟像(仏教版考える人)】
と覚えましょう。
弥勒菩薩は56億7000年後の未来に降り立って人々を救うとされる菩薩です。
現在は天界の中の一つである兜率天(とそつてん)という場所で私たちを見守り、修行していると言われています。
弥勒菩薩が有名なお寺
・広隆寺(京都府)弥勒菩薩半跏思惟像
飛鳥時代から存在する京都最古の寺である広隆寺を創建当時から見守ってきた、国宝に指定されている仏像です。
ホトカミページを見>>
普賢菩薩(ふげんぼさつ):白い象の上で合掌

普賢菩薩はさまざまな世界に現れ、深く思いやる心で人々を救うとされています。
普賢菩薩は【白い象の上で合掌】です。
・合掌
・6本の牙を持つ白い象
と覚えましょう。
普賢菩薩は釈迦如来の右側で祀られている場合と、単独で祀られる場合があります。
多くの場合、清浄を表す白い象に乗った姿をしています。
普賢菩薩が有名なお寺
・岩船寺(京都府)普賢菩薩騎象像
平安時代中・後期に制作されたとされています。
空海の甥である智泉大徳が一度絵に描いたものを、当時の仏師が形にしたものとされています。
ホトカミページを見る≫
文殊菩薩(もんじゅぼさつ):獅子に乗り、右手には剣

文殊菩薩は知恵によって人々を救うとされています。
文殊菩薩は獅子に乗り、右手は剣です。
・獅子
・右手に剣
・左手に経巻(きょうかん):経典を書いた巻物
と覚えましょう。
文殊菩薩は釈迦如来の左側に祀られている場合と、単独で祀られる場合があります。
威風堂々とした獅子には文殊菩薩の知恵の力の強さが表れています。
文殊菩薩が有名なお寺
・安倍文殊院(奈良県)騎獅文殊菩薩像
1203年に仏師の快慶の手によって作られた国宝に指定される仏像です。
7mの高さを誇り、獅子に乗った姿の仏像の中では日本最大です。
ホトカミページを見る≫
虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ):座禅を組み、左手に玉

虚空蔵菩薩は知恵と徳で人々を救う仏様です。
虚空蔵菩薩は坐禅を組み、左手に玉です。
・足は座禅を組む(結跏趺坐:けっかふざ)
・左手に玉(宝珠:ほうじゅ)
と覚えましょう。
イラストでは右手に剣を持っていますが、剣に変わって、心や行いが清らかなことを表す蓮華(れんげ)を持つなど様々なパターンがあります。
「虚空」とは「大空」を表し、大空のように広く無限な知恵と徳で人々を救うとされています。
さらに、記憶力を高める仏様としても信仰されており、虚空蔵菩薩のご真言を100万回唱えると記憶力が上がるとされています。
虚空蔵菩薩が有名なお寺
・神護寺(京都府)五大虚空蔵菩薩像
約1200年前に作られた、国宝にも指定される仏像です。
5体の虚空蔵菩薩が並んでおり、手の形や持ち物がそれぞれ異なります。
普段は一般公開されていませんが、毎年10月の第一土曜日から3日間、特別公開されています。
ホトカミページを見る≫
地蔵菩薩(じぞうぼさつ):坊主頭・杖・玉の3点セット

地蔵菩薩は、輪廻転生する全ての生き物を救う仏様です。
地蔵菩薩は、アクセサリーなどをつけず質素な服装をしています。
・坊主頭
・右手に杖(錫杖:しゃくじょう)
・左手に玉(宝珠:ほうじゅ)
の3点セットで地蔵菩薩です。
道端や庭に祀られる地蔵菩薩は何も持たずに合掌している場合もあります。
華やかな姿をしている他の菩薩と比べると、違いがわかりやすいですね。
地蔵菩薩はお釈迦様が亡くなってから、弥勒菩薩が地上に降り立つまでの仏様がいない間、人々を導き、罪や苦しみをなくすことを自らの使命としています。
また、地獄に落ちた人を含め、輪廻転生する全ての生き物を救うとされるため、日本の至る所に作られ「お地蔵さん」と親しまれるようになりました。
地蔵菩薩が有名なお寺
・六波羅蜜寺(京都府)地蔵菩薩立像・坐像
六波羅蜜寺には、立像は定朝、坐像は運慶と日本を代表する仏師によって制作された2体の地蔵菩薩があります。
ホトカミページを見る≫
・建長寺(神奈川県)地蔵菩薩坐像
建長寺の地蔵菩薩は、この地が処刑場だった時代に、処刑された罪人たちに祈りを捧げるために制作されました。
寺の創建後も、この地蔵菩薩は大切に受け継がれています。
ホトカミページを見る≫
日光・月光菩薩(にっこう・がっこうぼさつ):薬師如来の両隣

日光菩薩は昼を、月光菩薩は夜を見守る仏様です。
日光・月光菩薩は薬師如来の両隣に配されます。
・向かって右側、太陽を表す「日輪」を持っている日光菩薩
・向かって左側、月を表す「月輪」を持っている月光菩薩
と覚えましょう。
日光・月光菩薩はその名の通り、太陽と月の光で昼も夜も世界を照らし、人々を救う仏様です。
単独で祀られることはほとんどなく、基本的には薬師如来の補佐をする脇侍(きょうじ・わきじ)の位置に配されています。
脇侍の解説はこちらから>>
薬師如来の見分け方はこちらから>>
日光・月光菩薩が有名なお寺
・薬師寺(奈良県)日光・月光菩薩立像
薬師寺の日光・月光菩薩は、本尊の薬師如来とともに国宝に指定されています。
ホトカミページを見る≫
ここまで一般的な7つの菩薩の見分け方や特徴について解説してきました。
次に、千手観音菩薩のように「観音」とつく菩薩について、一般的な菩薩との違いや見分け方を紹介していきます。
7つの観音菩薩
観音菩薩は、世の人々の声を聞き、その悩みや苦しみから救う仏様です。
一般的な菩薩との違いは、人々の声に応じて様々な姿に変化することです。
この変化した姿の観音菩薩を「変化観音」と呼びます。

ここからは、個性豊かな姿をした観音菩薩のなかでも特に有名な「六観音(ろくかんのん)」を紹介していきます。
六観音:6つの世界を救う観音菩薩のチーム
仏教では、私たちは6つの世界を生まれ変わりながら徳を積んでいき、最終的には全てから解放された世界を目指します。
六観音は、その六つの世界それぞれに対応した観音菩薩のことです。

聖観音(しょうかんのん):人間に近い姿+頭上に小さな仏像

聖観音はすべての観音の基本となる仏様です。
聖観音は姿形も観音菩薩の基本形で、人間に近い姿をしています。
基本的な菩薩の特徴に加えて、宝冠に小さな仏(化仏:けぶつ)がついています。
聖観音は、これから紹介する観音菩薩の基本的な姿です。
それぞれの教えに応じて姿が変わる「変化観音」と区別され、「聖観音」と呼ばれています。
また、慈悲の心で人々の悩みや苦しみを救う仏様として親しまれています。
単独で祀られる場合と、阿弥陀如来の隣に配される場合があります。
聖観音が有名なお寺
・薬師寺(奈良県)聖観世音菩薩像
約800年前の白鳳時代と呼ばれる時代に制作された国宝に指定される仏像です。
衣のシワなど細部まで表現されており、仏師のこだわりを感じます。
ホトカミページを見る≫
十一面観音(じゅういちめんかんのん):頭に11の顔

十一面観音は11の顔で人々の願いを叶える仏様です。
十一面観音はその名の通り頭に11の顔を持っています。
頭部の顔はそれぞれ異なる表情をしています。

・正面の3つは穏やかな顔(菩薩面)
・向かって右側の3つは怒り顔(瞋怒面)
・向かって左側の3つは牙を出した顔(狗牙上出面)
・後ろの1つは大笑いした顔(大笑面)
・頭頂部の1つは如来の顔(仏面)
この11の顔には、全方位を見渡して人々の悩みや病気、悪い心から救い、あらゆる願いを叶えるという意味が込められています。
十一面観音が有名なお寺
・聖林寺(奈良県)十一面観音立像
奈良時代に制作された国宝に指定される仏像です。
アメリカの東洋美術史家のアーネスト・フェノロサも見惚れたと言われています。
ホトカミページを見る≫
千手観音(せんじゅかんのん):たくさんの手+頭に11の顔

千手観音はすべての悩みや苦悩も救う仏様です。
千手観音はたくさんの手+頭に11の顔です。
千手観音の多くは実際に1000本の腕があるのではなく、
合掌する2本の腕とそれ以外の40本の腕の合計42本の腕を持っています。
千手観音の腕は一般で25の世界を救うとされ、
40(腕の数)×25(各腕が救う世界の数)=1000
になることから、計1000の世界を救うと考えられています。
数は少ないですが、1000本の腕を持つ千手観音も存在します。
また、それぞれの手のひらには目がついています。
手のひらの目は苦しんでいる人を見つけるためについています。
さらに、頭上には十一面観音と同じ11の顔を持っています。
十一面観音をパワーアップしたような仏様ですね。
「千」は無限を表し、人々を救う術を無限に持っている存在として信仰されています。
つまり、どんな問題も解決してくれる、万能な仏様ということです。
千手観音が有名なお寺
・三十三間堂(京都府)千体千手観音立像・千手観音坐像
三十三間堂には千手観音が1000体が祀られています。
お堂の中に整然と並ぶ姿は圧巻です。
お堂中央には、千手観音坐像が配されています。
1000体の千手観音立像とお堂中央の千手観音坐像はすべて国宝に指定されています。
>>ホトカミページを見る
馬頭観音(ばとうかんのん):頭の上に馬の頭

馬頭観音は人々の一切の煩悩を断つ仏様です。
馬頭観音はその名の通り、頭上に馬の頭を乗せ、怒った顔(憤怒相)をしています。
・頭上の馬
・3つの怒った顔
・8本の腕
の特徴があれば馬頭観音です。
馬頭観音は、馬が雑草を食べ尽くすように、人々のすべての煩悩を断ち切る力を持つとされています。
また、近代では家畜をはじめとする動物の守り神としても広く信仰されるようになりました。
馬頭観音が有名なお寺
・観世音寺(福岡県)木造馬頭観音立像
この仏像は平安時代に作られました。
平安時代以前に制作された馬頭観音は非常に少なく、その中でも高さが5mを超える唯一の仏像です。
ホトカミページを見る≫
如意輪観音(にょいりんかんのん):膝を立て、右手を頬

如意輪観音はすべての人々の願いを満たす仏様です。
如意輪観音は右膝を立て、右手を頬に添える姿をしています。
・右膝を立てて両足の裏を合わせた輪王座(りんのうざ)
・右側の手を頬に添える思惟(しい・しゆい)の姿
・6本の腕
といった特徴があります。
如意輪観音は左側の手に法輪(ほうりん)、右側の手に如意宝珠(にょいほうじゅ)を持っています。
・如意宝珠(にょいほうじゅ):如意(=あらゆる願いを自在に叶えること)を象徴
・法輪(ほうりん):煩悩を打ち砕き、仏の教えが広まることを象徴
右手を頬にそえ、右膝を立てる姿が弥勒菩薩に似ていることから、中宮寺の仏像のように寺の伝承では如意輪観音とされていながら、一般的には弥勒菩薩とされている仏像もあります。
如意輪観音が有名なお寺
・観心寺(大阪府)如意輪観音坐像
平安時代に制作された、国宝に指定される仏像です。
普段は一般公開されていませんが、毎年4月17日、18日にご開帳されます。
ホトカミページを見る≫
不空羂索観音(ふくうけんさくかんのん):縄を手に持ち、眉間に第三の目

不空羂索観音はすべての人々を漏らさず救う仏様です。
不空羂索観音は手に持つ縄(羂索:けんさく)と眉間の第三の目が特徴の仏様です。
通常は1つの顔と8本の腕を持っていますが、異なる姿をしている場合もあります。
不空羂索観音を見分ける際には、特に手の縄と眉間の第三の目に注目すると良いでしょう。
不空羂索観音の「不空」とは、「空いているところがない=余すことなく」という意味です。
また、「羂索」には「人々を煩悩の海から救いとる縄」という意味があります。
「不空」と「羂索」の意味から、人々を羂索で余すところなく救う仏様として知られています。
さらに、病気や水害、火災から守ってくれる仏様としても信仰されています。
不空羂索観音が有名なお寺
・東大寺(奈良県)不空羂索観音像
東大寺の法華堂に置かれる不空羂索観音は国宝に指定されています。
頭上の宝冠が美しいことで有名です。
ホトカミページを見る≫
准胝観音(じゅんでいかんのん):18本の腕と印を結んだ手

准胝観音は、たくさんの仏様を産んだ母のような仏様です。
准胝観音は18本の腕が特徴です。
千手観音と似た姿をしていますが、
・千手観音:胸の前で手を合わせている(合掌)
・准胝観音:胸の前で施無畏印(せむいいん)や説法印(せっぽういん)などの印を結ぶ
といった違いがあります。
准胝観音は、無数の仏を生み出した母のような存在です。
そのため、准胝仏母(じゅんでいぶつも)とも呼ばれています。
菩薩は基本的に性別を超越した存在ですが、この特徴から、女性の姿で表現されることもあります。
准胝観音が有名なお寺
・大報恩寺(京都府)木造准胝観音立像
大報恩寺には国宝に指定された六観音(不空羂索観音を除く)の仏像があります。
准胝観音の仏像は数少ないため、貴重な作例です。
ホトカミページを見る≫
ここまで、菩薩それぞれの見分け方や特徴について紹介してきました。
いまでは個性豊かな姿をした菩薩ですが、仏教が始まった頃は、お釈迦様のことのみを指した言葉でした。
ここからは、菩薩の起源や、菩薩ならではの役割を解説していきます。
【決して誰も見捨てない!】菩薩の起源
元々「菩薩」とは、お釈迦様が出家する前の姿を表す言葉でした。
時代が下るにつれ「菩薩」は異なる意味を持つようになっていきます。
現代の日本でよく見かける「菩薩」の仏像は、全ての人々を救う仏教の教えに起源があります。
お釈迦様の前世としての菩薩
ジャータカという仏教の物語集には、お釈迦様が悟りを開く前の生涯についての話が記されています。
物語の中では、お釈迦様の前世は「菩薩」と呼ばれ、慈悲行と呼ばれる他の人々を助ける善行を積み重ねた結果、悟りに至ったとされています。
このことから、初期の仏教では修行者時代のお釈迦様のことを「菩薩」と呼んでいました。
生き方としての菩薩
2つの仏教
仏教は、お釈迦様が亡くなってしばらくすると、人々の考え方の違いから
・上座部仏教(じょうざぶぶっきょう)
・大乗仏教(だいじょうぶっきょう)
の2つのグループに分かれました。
これらはそれぞれ異なる修行の目的を持ち、仏教の広がりとともに地域ごとに発展していきました。
上座部仏教(じょうざぶぶっきょう):
・スリランカやタイなど
・自身の解脱のために修行を行う
大乗仏教(だいじょうぶっきょう):
・中国や日本など
・全ての人々の救済を目指す
菩薩という存在は、「大乗仏教」の中で発展しました。
2つの仏教の違い
上座部仏教では、個人の救済を目的とし、救済を得るには自ら出家し、厳しい修行を経て「阿羅漢(あらかん)」と呼ばれる最高位の僧侶にならなければなりません。
つまり、基本的には修行によって救われるのは自分一人だけということになります。
そのため、救われる人の数は限られてしまいます。
一方、大乗仏教は、上座部仏教の個人の救済を重視することに対し、お釈迦様が行った慈悲行が欠けているとし、自分自身の救済を求めて修行しつつ、他人も救済へと導くこと、すなわち全ての人々の救済を目指すことを重視しました。
大乗仏教では「菩薩=生き方」
大乗仏教では、ジャータカの物語や全ての人々を救済するという目標を背景に、お釈迦様が過去世で慈悲行を行った結果、悟りを開くことができたことを手本とし、自らもブッダになることができると考えられました。
こうして、大乗仏教では、修行段階にいる者も、お釈迦様と同じように「菩薩」と呼ばれるようになったのです。
現代の日本では「菩薩=信仰対象」
大乗仏教では、ブッダになるための修行段階にいる者を菩薩と呼ぶようになりました。
そのため、初期の仏教のように菩薩はお釈迦様が出家する前の姿のみを表す言葉ではなくなり、複数の菩薩が存在するようになりました。
このことから、人々の苦悩を取り除き、悟りに導く理想的な存在として、多種多様な菩薩の仏像が作られるようになりました。
【如来のサポート役】菩薩の役割

日光・月光菩薩の見分け方のポイントでも少し触れましたが、菩薩は単独で祀られることもあれば、如来などの隣に配置されることもあります。
如来などの隣に配置される菩薩のことを「脇侍(きょうじ・わきじ)」と呼びます。
また、脇侍に挟まれた中央の仏像を「中尊」、「脇侍」と「中尊」を合わせて「三尊」と呼びます。
脇侍は、中尊をサポートすると同時に中尊が持つ特性を表す役割を担っています。
ここからは、脇侍を務める菩薩たちを紹介していきます。
薬師如来の脇侍は日光菩薩と月光菩薩

薬師如来の脇侍は向かって左側に月光菩薩、右側に日光菩薩が配されています。
月光菩薩は知恵の光で、日光菩薩は慈悲の光でこの世を照らし、常に薬師如来をサポートしています。
阿弥陀如来の脇侍は観音菩薩と勢至菩薩

阿弥陀如来の脇侍には向かって左側に勢至菩薩(せいしぼさつ)、右側に観音菩薩が配されています。
勢至菩薩は阿弥陀如来の知恵を、観音菩薩は慈悲を表すとされています。
釈迦如来の脇侍は文殊菩薩と普賢菩薩

釈迦如来の脇侍は向かって左側に文殊菩薩、右側に普賢菩薩が配されます。
文殊菩薩は釈迦如来の知恵を、普賢菩薩は実践する力を表しています。
終わりに
ここまで菩薩の見分け方や役割などについて解説してきました。
同じ菩薩の中でも、姿形が大きく異なることには、それぞれの教えや背景が関係しています。
仏像に込められた教えや物語を知ることで何気なく手を合わせていた仏像から、新たな学びや感動を得られるはずです。
ぜひ、この機会に仏像を見にお寺に参拝してみてはいかがでしょうか。
お寺に参拝した際には、ホトカミにも投稿してくださいね!
仏像イラストレーターが作った 仏像ハンドブック


初心者からマニアまで、これを読めば仏像がもっと楽しくなる!

神社お寺の検索サイト「ホトカミ」運営代表
吉田 亮
月間120万人の神社お寺ファンが使う神社お寺の検索サイト「ホトカミ」を運営する株式会社DO THE SAMURAI代表取締役。
東京大学理科II類入学後、文学部言語文化学科日本語日本文学(国語学)専修課程卒業。
2013年より日本文化や歴史を後世に繋ぐ事業を開始、2016年法人化。
これまで2000人以上の参拝者との対話や、累計1000万アクセスを超えるお参りに関する記事の執筆編集、100年後に神社を残すために社会と神社の接点を創出する。

ホトカミ編集部 御朱印記事ライター
高原 健太郎
日本文化や神社お寺が好きです。
独特の雰囲気に魅了されてから、寺社めぐりが趣味になりました。

イラストレーター
田中ひろみ
絵文人・仏像研究家(株)TERABIT代表、奈良市観光大使女子の仏教サークル「丸の内はんにゃ会」代表。
カルチャー センター講師。元ナース。テレビ出演、講演も多数。ART ・俳句・盆踊らー
著書 『イラストレーターが作った仏像ハンドブック』(ウェッジ) など約70冊
仏像紹介記事一覧
弥勒菩薩の起源と信仰を紹介
弥勒菩薩とは?半跏思惟像で有名な56億7000万年後に現れる仏様の役割を解説
有名な7つの観音菩薩を徹底解説
観音菩薩とは?あなたの悩みに寄り添う観音様の役割をやさしく解説
千手観音の起源と信仰を紹介
千手観音とは?1000本の手が表す意味や人々を救う方法を徹底解説
この記事はホトカミサポーターさんのおかげで公開できました!

〈ホトカミサポーターとは〉
「100年後に神社お寺を残そう」というホトカミの理念に共感し、ホトカミの今後を応援してくださる方に、毎月500円からサポートしていただく仕組みです。
【サポーター限定の特典】
プレミアム検索機能では、切り絵・刺繍御朱印・一粒万倍日など、こだわりの御朱印がある神社お寺を、20種類以上の項目から見つけられます。さらに、神さま・仏さま・宗派からも検索可能。(無料お試しあり)
このほか「毎月あなたの幸せと健康をご祈願」「お気持ちで特典(全国の寺社からサポーター限定の特典)」「バナー広告の非表示」があります。
都道府県から神社お寺を探す
北海道・東北
関東
中部
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。




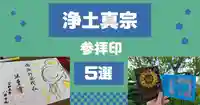

初心者向けの仏像の基本的な知識から、仏像の世界がさらに広がるマニア級の深い豆知識まで、イラストで分かりやすく解説されています。
ホトカミユーザーの皆さんにオススメの1冊です!