なんぜんじ|臨済宗南禅寺派
南禅寺のお参りの記録一覧

哲学の道から知恩院へ向かうため、必然的に南禅寺へ😄
午後4時30分頃でも参拝者でいっぱい✨
桜に加えて山門やら水路閣やら、写真映えスポットだらけですもんね📷
蹴上インクラインの桜も満開前でしたが、記念撮影インバウンドで大混雑💦(4月2日)






時代劇でお馴染み

ここにも来ちゃうなぁ

インクラインは人が写りすぎて、撮った写真ほとんど使えず

京都市左京区にあるお寺です。
山号は瑞龍山
宗旨宗派は臨済宗南禅寺派
寺格は大本山、京都五山および鎌倉五山の別格上位
ご本尊は釈迦如来
です。
方丈は国宝に指定されており 境内は国の史跡に 方丈庭園は国の名勝に指定されています。
前にお参りした時は 突然の雨に襲われ 三門の上で時間つぶしをしました。
それはそれで風情があったのですが やはり晴天の南禅寺を参拝したくて お参りしました。
しかし暑すぎでした。
塔頭も多く 歴史もあり 立派な建物は圧巻です。


三門




柱の台座が面白いと思いました



本殿 天井の龍



方丈庭園

方丈庭園

方丈庭園

欄間 変わっています

欄間 変わっています


小方丈庭園


これ 硯ですよね



境内の外にあります 大寂門

やって来ました南禅寺2回目!!✨✨
春に来た時の、なんてきれいなトコなんだろ、が忘れられなくてもう一回来たかったトコです!😭
しかし京都はキレイなところが詰まりすぎです!
ちょっと走ればすぐスゴイとこに着きますね!🚗³₃
南禅寺はもうやっぱりステキ過ぎです✨✨✨
あーだこーだはいりません。写真で❤

南禅寺といえば、、、これっす😍✨

どーん!✨✨

抜けて振り返ると✨✨

御本堂〜✨✨✨

ここはここまで!

ん〜✨何回見てもキレイ✨✨✨

南禅寺といえばver.2

逆サイド!✨✨

南禅寺は臨済宗南禅寺派の大本山の寺院。山号は瑞龍山。本尊は釈迦如来。開山は無関普門(大明国師)、開基は亀山法皇。正式には太平興国南禅禅寺と号する。日本最初の勅願禅寺であり、京都五山および鎌倉五山の上に置かれる別格扱いの寺院で、日本の全ての禅寺の中で最も高い格式を持つ。
~ウィキペディアより抜粋~
昼から訪れたこともあり、観光客で賑わっていました😄

中門
慶長6年(1601)松井康之より、伏見城松井邸の門を勅使門として寄進されたもの。

勅使門(重要文化財)
寛永18年(1641)明正天皇より、御所にあった「日の御門」を拝領したもの。

南禅寺の由緒書き

三門の由緒書き

三門(重要文化財)①
三門とは仏道修行で悟りに至る為に透過しなければならない三つの関門橋を表す、空、無相、無作ね三解脱門を略した呼称。南禅寺の三門は別名「天下竜門」とも呼ばれる。

三門②
開創当時のものは永仁3年(1295)西園寺実兼の寄進によって創立。歌舞伎「楼門五三桐」の石川五右衛門の伝説で有名。

法堂
法式行事や公式の法要が行われる場所であり、南禅寺の中心となる場所。

疎水
琵琶湖から京都市内に向けて引かれた水路。疎水の工事は1885年に始まり、1890年に竣工した。

南禅院
亀山天皇は、正応2年(1289)離宮で出家して法皇となられ、離宮を寄進して禅寺とし大明国師を開山とされた。ここは離宮の遺跡であり、南禅寺発祥の地。

高徳庵①

高徳庵②

御朱印(書き置き)
三門の拝観受付で授与されています。

御朱印(書き置き)
方丈庭園拝観にある売店コーナーで授与されています。

さて南禅寺へきました!
、、、スゴイですねココ、、、✨😢
とにかくデカいしキレイだし迫力がスゴすぎるし、、、✨
めちゃくちゃ写真撮りました📸
あんなにスゴイ建物どうやって運んで組み立てたんすかねいやマジで🤩🤩🤩✨
ココも文よりも写真で!!

山門!

山門②!

の下!

の下②!

くぐって振り返ると!✨

少し離れて!

ややサイドから!

✨

✨✨

本堂〜!✨

建築以外も!✨

おー!

おーー!!✨

この日は雨でしたが、ここは行きたいと思っていたので、宿から駅、駅からさらにバスに乗り、降りてさらに歩いてこちらに。
公式サイトのバス停からの案内に沿ってむかいましたが、途中の道も美しく、ああ、京都に来てよかったと実感。
ついたのが勅使門の内側の道でしたし、あまりに広すぎて、どこが境内なのか、一瞬迷ってしまいました^^;
それでも三門がみえましたので、そちらだろうと思い進みました。
三門。拝観できるとあったので、どういうことだろう、と思っていましたが、大きさを見て納得。
階段を上がり、その中を拝見できるのですね。
さらに進んで法堂。
ただただ圧倒されます。
そして、方丈。本坊で申し込みをし、拝観。
土曜日でしたが、雨の朝だったせいか、ほかに人もいなく、貸し切り状態で拝見することができ、
美しい庭、お部屋(襖絵など)、建物に感動というか、逆に心がおちついていく、というか、時間を忘れました。
滝の間でお茶がいただけるということでしたので(準備中と書かれていましたが、聞いたら大丈夫とのことでした)、
滝をみながらお茶をいただきました。
こちらも時間を忘れます。
そして、こちらに来たら、やはり見たい、水路閣。
はじめ水路閣の下を通って左(上流)に向かっていき、そこで拝見。
ここは誰もいなかったので、こんなものなのかな?と思って降りていったら、そこには人がたくさん。
雨で足元がわるかったですが、上にあがり、鐘楼も拝見。
南禅院、三門も拝見したかったのですが、時間が読めなかったので(午後は予定あり)今回は断念。
次回来るときは、時間にゆとりを持ってこなくては!
御朱印はご本尊のものと、三門のもの(拝観しなくてもいただけました)をいただきました。

































































南禅寺
大晦日で人は少なめ
とても素晴らしい所でした。
今までお寺ってあまり行かなかったんですけど
芸術的ですよね。
今年の京都もとても素晴らしい旅行になりました。
芸術の都ってやつなんじゃないでしょうか?
やっぱり京都は良い。
京都はなんと言っても人が良いし、神社もお寺も、歴史探訪したくて何度でも来たいです。
まだまだ見たい所が沢山ありますが
うしろ髪ひかれる思いで大阪へ向かいます。
待ってろたこ焼き!

こんな不思議なトンネル通って

すーごい門通って

素敵な水道橋見て

線路歩いて
スタンド・バイ・ミー
この線路の先には2023年

そうだ京都行こう〜紅葉名所編③〜 金地院の次は南禅寺です。こちらも紅葉の名所で有名です。昼時なので大混雑が予想されますが、平気です。良い所は混むのが当たり前です。こちらは鎌倉時代の創建です。当時の亀山天皇が造営されました。京都五山の最高位である「五山之上」とされています。紅葉の他にも二階建ての重厚な三門やレンガ造りのモダンな水路閣、国宝の方丈の中にある方丈庭園、狩野派の障壁画など見所満載なので楽しみです。

入口の前の駐車場は観光バスがズラーッと並んでいます。

さあ。入りますよ😄

まずは三門からです。

かの石川五右衛門がこちらの三門上で「絶景かな、絶景かな」と言った場所です。拝観料がいるし、こちらも眺めまで撮影禁止になっているので登るのはやめておきました。

柱の間が紅葉の名画みたいになっています。

至るところこんな感じ🍁

真っ直ぐ行くと、

法堂(はっとう)が見えてきました。豊臣秀頼が寄進されましたが、明治28年焼失して同42年再建されました。

こちらでお参りしましょう。

天井の龍図が見応えあります。

次は水路閣です。

古代ローマの水道橋を模して明治時代に造られました。全長93m、幅約4mのレンガ造りの疏水橋です。実際に水が流れているそうです。

次は方丈庭園を見に行きましょう。

左側から見たところ

中央

右側から見たところ。心が落ち着きます😊

小方丈の庭です。こちらもいいです。

建物に沿って歩きます。


紅葉でお腹一杯になりました。方丈の中で豪華な狩野派の襖絵をたっぷり見せてもらいました。全部撮影禁止なので載せられませんでした。

最後に三門を抜けてサヨナラしました。

書置きの御朱印です。ありがとうございました。
京都府のおすすめ🌸
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ

































































































































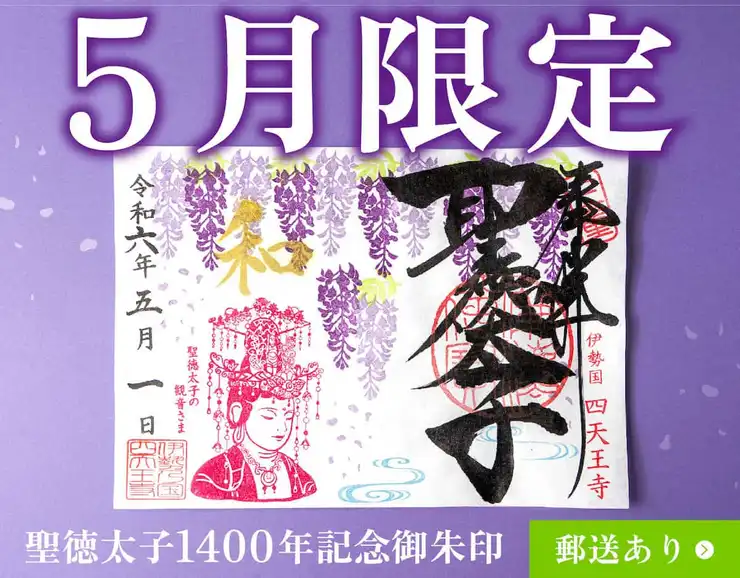





10
0