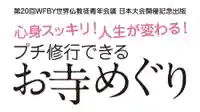七福神とは?見分け方やご利益、由来をご紹介
「七福神にはどんな神さまがいるんだろう?」
「七福神の見分け方を知りたい」
七福神という言葉は聞いたことあるけれど、それぞれの神さまのお名前までは分からない方も多いのではないでしょうか。
こんにちは。
日本最大の神社お寺のお参りの記録投稿サイト「ホトカミ」編集部の吉田です。
今回取り上げるテーマは「七福神」。

神社や年賀状など、七福神を目にする機会は意外と多いと思います。
最近ではアニメのキャラクターなどが七福神の格好をしていることもあります。
しかし、七福神って縁起が良さそうだけど、
七福神の神さまの名前と特徴まではわからないですよね・・・。
私も好きなアイドルグループが七福神をモチーフとした衣装を着ていたときに、誰がどの神さまなのか分からず調べたことがあります。
そこでこの記事では、
すぐに七福神を見分けられる早見表をはじめ、七福神の神さまがどんな方々なのか、
由来やご利益などもあわせて紹介します。
また、後半では七福神がまつられている神社をまわる「七福神めぐり」についてもお伝えします。
「七福神の見分け方を知りたい」
「七福神ってどんな神さまなのか知りたい」
と思ってる方はぜひ最後まで読んでみてくださいね。

吉田 亮
「100年後に神社お寺を残す」ために月間120万人の神社お寺ファンが使う神社お寺の検索サイト「ホトカミ」を運営する株式会社DO THE SAMURAI代表取締役。
東京大学理科II類入学後、文学部言語文化学科日本語日本文学(国語学)専修課程卒業。
2013年より日本文化や歴史を後世に繋ぐ事業を開始、2016年法人化。
この記事は、ホトカミサポーターさんのおかげで公開できました!

〈ホトカミサポーターとは〉
ホトカミの理念に賛同いただける方、ホトカミの今後の展望を応援してくださる方に、
毎月500円からサポートしていただく仕組みです。
いただいたお金は、開発費・人件費・サーバー代など、
ホトカミを安定して運営し、より良いサービスにするために活用させていただきます。
どうか、あたたかいサポートをよろしくお願いします。
それではさっそく、七福神の見分け方を紹介します。
七福神ってどんな神さま?
七福神の見分け方
そもそも七福神とは、福を授ける神さまとして知られる7体の神さまのことで、
弁財天(べんざいてん)・毘沙門天(びしゃもんてん)・大黒天(だいこくてん)・恵比寿(えびす)・布袋(ほてい)・寿老人(じゅろうじん)・福禄寿(ふくろくじゅ)のことを指します。
七福神は見た目が似ている神さまもいて、名前や特徴がわかりづらいかもしれません。
そこで、ホトカミ編集部では、それぞれの神さまの特徴をまとめた早見表を作りました。
この早見表を見れば誰でも簡単に七福神の神さまを見分けることができます。
早見表はこちらです。

それではこの表をもとに七福神を見分けるポイントを紹介します。

弁財天は唯一の女性で、羽衣をまとい琵琶(楽器)を持っています。
毘沙門天は甲冑に身をつつみ、先が三つに分かれた武器や、宝塔(ほうとう)という小さな塔を持っています。
2,鯛と釣り竿を持つ恵比寿

恵比寿は鯛と釣り竿を持っていることが多いです。
どちらかしか持っていない場合もありますが、鯛か釣り竿のどちらかを持っている神さまは恵比寿です。
3,打ち出の小槌の大黒天、袋だけを持つ布袋

大黒天と布袋には「大きな袋をかついでいる」という共通点があります。
2柱の神さまの違いは持ち物。
打ち出の小槌を持っているのが大黒天です。
また布袋は着物をきちんと着ておらず、胸やお腹を出した様子で描かれることが多いです。
4,鹿と一緒の寿老人、最後に残るは福禄寿

最後に、見分けるのが難しいのが寿老人と福禄寿になります。
いずれも老人の姿をした神さまで、手に巻物を持っていることが多いです。
老人の姿をした神さまのうち、桃を持っていたり鹿を従えているのが寿老人になります。
そして最後に残った神さまが福禄寿と考えるとよいでしょう。
福禄寿は鶴とともに描かれることもあります。
-
七福神の見分け方
- 琵琶を持つ弁財天、武器を持つ毘沙門天
- 鯛と釣り竿を持つ恵比寿
- 打ち出の小槌の大黒天、袋だけを持つ布袋
- 鹿と一緒の寿老人、最後に残るは福禄寿

これでもう七福神の見分け方はバッチリですね。
次に、それぞれの神さまのプロフィールを紹介します。
七福神のご利益・お姿・由来
弁財天(べんざいてん)

弁財天は、財運・音楽・芸能の神さまです。
知恵や弁舌、縁結びをつかさどるともいわれています。
七福神のなかでは唯一の女性の神さまで、羽衣をまとい冠をつけ、琵琶(びわ)を弾く天女の姿であらわされることが多いです。
インドの神話にでてくる水神サラスヴァティがモデルだと考えられ、仏教に取り入れられたあと日本に伝来しました。
弁天さまと呼ばれ人々から親しまれています。
毘沙門天(びしゃもんてん)

毘沙門天は福徳・厄除けの神さまです。
甲冑を身にまとい、右手には先が三つに分かれた矛(ほこ)を、左手には宝塔(仏教の一重の塔)を持った姿であらわされることが多いです。
にこやかな七福神のなかで、ただ一人怒ったような表情をしていることがあります。
もとはインドの神さまで、ヒマラヤの山に住みインドの北を守る神さまとされていました。
仏教に取り入れられてからは仏法(仏の説いた教え)を守る四天王の一人として、北の守護神とされるようになり、日本に伝来しました。別名を多聞天といいます。
戦いの神さまとしても知られ、上杉謙信などが信仰した軍神です。
恵比寿(えびす)

恵比寿は商売繁盛・五穀豊穣・大漁祈願の神さまです。
平安時代の貴族の装束である狩衣(かりぎぬ)を着て烏帽子(えぼし)をかぶり、手には釣り竿、脇に鯛を抱えた姿であらわされることが多いです。
七福神の中で唯一の日本の神さまで、一説によるとイザナミとイザナギの第一子・蛭子(ひるこ)のことであるとされています。
「釣りして網せず」のお姿から、暴利をむさぼらない清い心を持った神さまであると考えられ、商売繁盛の神さまとして広く知られるようになりました。
恵比寿(えびす)は、恵比須・戎・夷とも表記されます。
大黒天(だいこくてん)

大黒天は財宝・開運・子孫繁栄の神さまです。
打ち出の小槌と大きな袋を持ち、米俵の上に乗った姿であらわされることが多いです。
もとはインドの想像と破壊の神・シヴァ神の化身であるマハーカーラという神さまでした。
シヴァ神が世界を破壊するときにこの姿になるといわれ、恐ろしい表情をしていました。
「マハー」はサンスクリット語で「大」、「カーラ」は「黒」という意味です。
仏教に取り入れられた後日本に伝来しましたが、日本古来の神さまである大国主神(おおくにぬしのかみ)(※)の「大国」と「大黒」が似ていることから同一視されるようになり、現在の優しい表情をした大黒天になりました。
(※大国主神は、傷ついた兎を救った因幡の白兎伝説で有名です)
布袋(ほてい)

布袋は笑門来福・夫婦円満・人徳の神さまです。
太鼓腹で着物を着崩し、大きな袋をもった僧侶の姿であらわされることが多いです。
七福神のなかでは唯一実在した人物で、一説によると中国の唐代末期の禅僧・契此(かいし)がモデルであるとされています。
契此(かいし)は、大きな布の袋に施された食べ物やもらい物を入れて放浪生活を送っていた僧侶ですが、彼の占いは百発百中だったそうです。
中国では、釈迦の没後56億7千万年の頃に現れ人々を救う弥勒菩薩(みろくぼさつ)の化身と考えられています。
福禄寿(ふくろくじゅ)

福禄寿は長寿延命・立身出世・子孫繁栄の神さまです。
杖や巻物を持ち、白くて長いひげをたくわえた長頭の老人の姿であらわされることが多いです。鶴を従えていることもあります。
もとは中国の道教の神さまで、南極老人星(りゅうこつ座のカノープスという星)の化身と考えられていました。
南極の星であり中国ではめったに見ることができなかったため、世の中が平和なときにのみ出現するめでたい星や、皇帝の寿命を支配する星と信じられていたようです。
寿老人(じゅろうじん)

寿老人は長寿延命・諸病平癒の神さまです。
鹿を従え、手には巻物をつけた杖や桃などを持ち、白くて長いひげをたくわえた長頭の老人の姿であらわされることが多いです。
鹿や桃は長寿の象徴とされています。
実は、寿老人のモデルは福禄寿と同じ仙人です。
福禄寿と寿老人の姿が似ているのもうなずけますね。
日本では別の神さまとして受け入れられたのですが、寿老人を七福神と考えない地域もあり、その場合は吉祥天(インドの美の女神)や猩々(大酒のみの猿の姿をした霊獣)を七福神とします。
七福神が宝船に乗る理由
七福神を思い浮かべたとき、宝船に乗った神さまを想像する方も多いのではないでしょうか。
なぜ七福神は宝船に乗っているのでしょう?

答えは、宝船はおめでたいものを詰め込んだ船だからです。
そもそも宝船とは、縁起物を乗せた船のことです。
古くは稲穂や米俵を乗せたものが主流でしたが、次第に打出の小槌・千両箱・鶴亀など、様々なおめでたいものを乗せるようになりました。

やがて、福を招く7体の神さまである七福神を乗せた宝船が多く描かれるようになり、現在の宝船と七福神のイメージにつながっています。
また、宝船の絵の上に「永き世の 遠の眠りの みな目ざめ 波乗り船の 音のよきかな」という歌を書いた紙を正月2日に枕の下に置いて寝ると、縁起の良い夢を見ることができると信じられています。
実はこの歌は回文になっているんです。
「なかきよのとをのねふりのみなめさめなみのりふねのをとのよきかな」
お正月は宝船の絵を枕の下に置いて寝てみてください。
縁起の良い初夢がみられるかもしれませんね。
500年続く七福神の歴史
ここまで、七福神の神さまのプロフィールを紹介してきました。
では、七福神の神さまにはなぜあの7体の神さまが選ばれているのでしょう?
七福神はいつ頃から信仰されるようになったのでしょう?
諸説ありますが、歴史学者の喜田貞吉氏によると、
七福神は今からおよそ500年前、室町時代末期に京都で成立しました。
当時から、
鞍馬寺(京都)の毘沙門天
延暦寺(滋賀県)の大黒天
西宮神社(兵庫県)の恵比寿
宝厳寺(滋賀県)の弁財天
は人々から篤く信仰されていたようです。
また、恵比寿と大黒天はセットでおまつりされることが多く、絵に描かれることもありました。
布袋・寿老人・福禄寿もよく絵に描かれていました。
上方で流行していた恵比寿と大黒天を中心に、
当時の人々に広く信仰されていた神々が加えられ、七福神の原型ができあがったといわれています。
七福神めぐりをしよう!
ここまで七福神がどのような神さまなのか、ご利益や由来などを紹介してきました。
ところで、「七福神めぐり」という言葉を聞いたことはありませんか。
これは七福神の神さまがまつられている7つの寺社をめぐり、開運を祈るお参りです。
(宝船を含めて8つの寺社をめぐるところもあります)
東京だけでも数十種類の七福神めぐりコースがあるといわれ、日本各地で行われています。
七福神めぐりのオススメの時期はお正月です。
日本には昔から「七福神もうで」という風習があり、これは年の始めに七福神をまつる7つの寺社をめぐり、その年の開運招福を祈願するものでした。
江戸時代に盛んに行われるようになったといわれています。
現代にもこの風習が残り、
七福神めぐりのなかには、元日から7日(もしくは十数日)の間のみ、七福神めぐり限定の御朱印をいただけるところがあります。

御朱印のいただき方はコチラ≫
多くの七福神めぐりは4~6時間でお参りできるようです。
パンフレットや公式サイトに記載されている所要時間の多くは最短でめぐった場合ですので、境内を散策したり途中で休憩することを考えると、1.5~2倍は見積もった方がよいでしょう。
七福神めぐりは日をまたいでめぐっても大丈夫ですので、時間がない場合は二日に分けてお参りすることがオススメです。
また、七福神めぐりには2000~3000円程度のお金が必要です。
これは七福神めぐり専用の色紙と、それぞれの寺社で御朱印をいただくときに必要なお金になります。
御朱印をいただかない場合はお賽銭の分のお金だけ用意しておけば大丈夫です。
ぜひ2024年のお正月はお近くの七福神めぐりに行かれてはいかがでしょうか?
おわりに
ここまで七福神の神さまの見分け方にはじまり、
それぞれの神さまの由来やご利益、
そして七福神めぐりを紹介してきました。
七福神はインド・中国・日本の神さまが集まったおめでたい神さまです。
新年に七福神をまつる神社にお参りするときっとあなたのところにも福が舞い込んでくるはず!
ぜひ2024年のはじまりに七福神めぐりをしてみてくださいね。
この記事は、ホトカミサポーターさんのおかげで公開できました!

〈ホトカミサポーターとは〉
ホトカミの理念に賛同いただける方、ホトカミの今後の展望を応援してくださる方に、
毎月500円からサポートしていただく仕組みです。
いただいたお金は、開発費・人件費・サーバー代など、
ホトカミを安定して運営し、より良いサービスにするために活用させていただきます。
どうか、あたたかいサポートをよろしくお願いします。
都道府県から神社お寺を探す
北海道・東北
関東
中部
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。