ちょうこくじ|高野山真言宗|飯上山長谷寺如意輪院
長谷寺神奈川県 本厚木駅
参拝可能時間
8:30~16:30
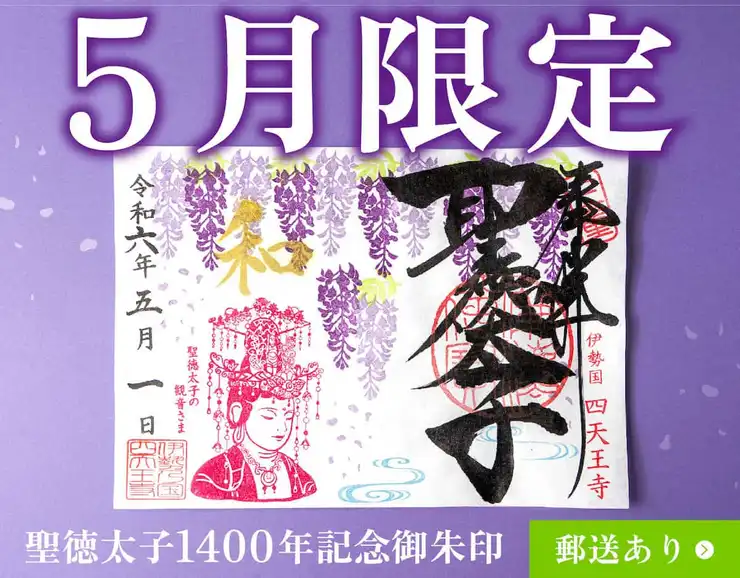
| 御朱印 | |||
|---|---|---|---|
| 限定 | - | ||
| 御朱印帳 | |||
| 駐車場 | 500円/日 |
飯山観音の正式名称は「飯上山長谷寺(ちょうこくじ)」。
高野山真言宗。
坂東観音巡礼第6番の札所として知られ「飯山観音」の名で親しまれている。
725年(神亀2年)に行基によって開かれたとも、810~824年の弘仁年間に弘法大師(空海)よって開かれたとも伝えられている。
また、源頼朝が秋田城介義景(安達盛長の子)に命じて堂宇を造営させたのが、この寺のはじまりとも伝えられている。
麓の金剛寺には盛長の墓と伝えられている五輪塔がある。
本尊の十一面観音には、行基がクスノキで造ったという尊像が胎内に納められているという。
1672年(寛文12年)、飯山村の大工西海氏によって造られた厚木市の重要文化財の「厨子」の中に安置されている。
長谷寺(ちょうこくじ)は、神奈川県厚木市にある高野山真言宗の寺院。寺号は飯上山(いいがみさん)。本尊は十一面観世音菩薩。通称「飯上観音」。坂東三十三所観音6番。
寺の創建には2説ある。一つは奈良時代初期に行基がこの付近に五色に輝く泉があったためクスノキで十一面観世音菩薩を刻み安置したというもの、もう一つは平安時代初期に当地に立ち寄った弘法大師が宿の礼に大和長谷寺と同じ木で作った観音像を授けたというもの。その後、鎌倉時代には源頼朝の命で観音堂が建立され、四宗兼学の寺として栄えた。
当寺は、小田急小田原線・本厚木駅の北西7kmの丘陵地にある。山門から本堂までは段々で少しずつ上がって行き、最上段からは厚木市内が見渡せる。見て廻るエリア自体は広くはないが、6月見頃のたくさんの紫陽花を含め、見応えはある。
今回は、坂東三十三観音札所であるため参拝することに。参拝時は週末の午後で、自分以外にも数人参拝者が来ていた。
境内入口の<山門>。宝永年間(1704年~1711年)造営の三間一戸八脚門。寄棟造、茅葺。(2020年6月当寺工事中)。
工事はやや残念だったが、山門手前の<あじさい>が歓迎ムードを出している。
山門を抜けたところ。イヌマキの巨木がすごいインパクト。かながわの名木100選に選ばれていて、高さ17m、目通り3m弱、推定樹齢400年。古刹であることを感じさせてくれる。
参道右手の<水屋>。
参道左手の<寺務所>。
参道右側、見晴しの良い場所に地蔵様と石碑。
参道右側、<六地蔵尊>。
<観音堂>のある境内への階段を登る。
階段を登ったところ。参道に沿って並ぶ石燈籠が印象的。
すぐ右手からは、厚木市内が見渡せる絶景。
右手方向にある<鐘楼>。銅鐘には、室町時代1442年の銘がある。
参道を進んで、常香炉の向こうに<観音堂>。江戸時代建立と推定される。桁行五間、梁間五間の正方形平面をもつ、銅板葺の宝形堂。端正なルックス。
<観音堂>正面。奥の厨子の中に、奈良時代の725年に行基が大和長谷寺の仏材に刻んだと伝わる本尊・十一面観音薩立像を安置。
観音堂の左手に<納経所>。御朱印はこちら。
観音堂から見た境内。
<観音堂>全景。
当寺では、境内のいたるところに<あじさい>が咲いていて非常にきれい。
| 住所 | 神奈川県厚木市飯山5605 |
|---|---|
| 行き方 | 【バス】
【お車】
|
| 名称 | 長谷寺 |
|---|---|
| 読み方 | ちょうこくじ |
| 参拝時間 | 参拝可能時間
|
| 参拝料 | なし |
| トイレ | 駐車場にあります。 |
| 御朱印 | あり |
| 限定御朱印 | なし |
| 御朱印帳 | あり |
| 電話番号 | 046-241-1635 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |
| ホームページ | https://www.iiyamakannon.com/ |
| 坂東三十三観音 | |
|---|---|
| 東国花の寺百ヶ寺 |
| 山号 | 飯上山長谷寺如意輪院 |
|---|---|
| 宗旨・宗派 | 高野山真言宗 |
| 開山・開基 | 行基 |
| 体験 | 御朱印 |
| 概要 | 長谷寺(ちょうこくじ)は、神奈川県厚木市飯山(相模国愛甲郡飯山村)にある高野山真言宗の寺院。山号は飯上山。本尊は十一面観世音菩薩で、坂東三十三観音霊場第6番札所、東国花の寺百ヶ寺神奈川6番札所である。飯山観音とも称される。 本尊真言:おん まか きゃろにきゃ そわか ご詠歌:飯山寺建ちそめしよりつきせぬは いりあいひびく松風の音 |
|---|---|
| 歴史 | 由緒[編集] 725年(神亀2年)に行基が開創したとも、弘仁年間(810年 – 824年)に空海が開創したとも伝えられる。 |
| アクセス | 交通[編集] 小田急小田原線本厚木駅から神奈川中央交通バスで飯山観音前下車 [厚18]上飯山行 [厚19][厚22]上煤ヶ谷行 [厚20][厚21]宮ヶ瀬行 |
| 引用元情報 | 「長谷寺 (厚木市)」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E9%95%B7%E8%B0%B7%E5%AF%BA%20%28%E5%8E%9A%E6%9C%A8%E5%B8%82%29&oldid=99781887 |
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。
ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ














































7
0