たかてるじんじゃ
あなたのサポートが必要です〈特典あり〉
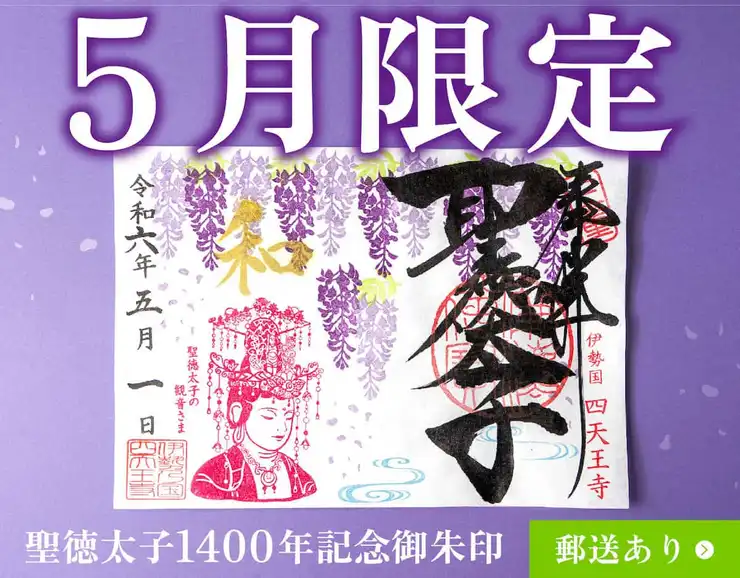
高照神社について
弘前藩中興の祖とよばれる4代目藩主津軽信政公が祀られておる神社で、御廟もあります。
ご神職様はいらっしゃらないですが、300年間氏子さんたちが守り抜いてきたお社です。
お社自体は重要文化財として登録されています。
氏子さんたちが管理しているので、決して手入れは充分ではないのですが、中には江戸時代の大絵馬が飾られていて、誰でも見れます。
おすすめの投稿

津軽公が眠っています。
駐車場、トイレ有ります。
御朱印は道路挟んで向かいの商店で頂けます。
神社以外にも博物館が併設してあったり、馬場跡があったりと、見どころがたくさんあります。


高照神社は青森県弘前市高岡神馬野に鎮座する神社です。高照神社の創建は不詳ですが古くから春日四神(武甕槌命・伊波比主神・天児屋根命・比売神)を祀る小祠があったと伝えられています。
津軽家は南部家の一族である久慈氏出身とされ、本来は源氏(南部家の祖)の氏神、八幡神を崇敬していましたが、南部家からの独立に際し、自らの祖を藤原氏とした為、藤原氏の氏神、春日神(春日大社の分霊)を祀る必要性があったと思われます。
特に弘前藩4代藩主津軽信政は吉川神道の創始者である吉川惟足に師事し、高岡の地に社殿を再建する計画を立てました(高岡の地は弘前城から西方にあたる為、東西軸に社殿を配置すれば弘前城を見下ろせる位置関係となっています)。
しかし、信政は宝永7年(1710)に計画半ばで弘前城で死去した為、5代藩主津軽信寿が引き継ぐ事になり、信政の遺言に従い神式の霊廟を小祠の背後と定め吉川惟足から授けられた神号「高照霊社」を社号としました(享保15年に高照神社と改称)。
藩主を祭る神社は明治時代以降、各地で盛んに創建されましたが、江戸時代中に創建される例は日光東照宮(栃木県日光市)は例外としても高照神社の他、会津藩初代藩主保科正之の土津神社(福島県猪苗代町)や長岡藩3代藩主牧野忠辰の蒼柴神社(新潟県長岡市)など例が少なく、同じ神道でも加賀藩主前田家や岡山藩主池田家、鳥取藩主池田家などは墓碑が神式の亀趺墓を採用し人里離れた霊地に墓域を構えていますが神社という形式は採用しなかったようです。
以来、高照神社は津軽家の崇敬社として庇護され5代藩主津軽信寿が正徳2年(1712)に本殿を造営したのを筆頭に7代津軽信寧は宝暦5年(1755)拝殿、9代津軽寧親は文化7年(1810)に随神門、文化12年(1815)に廟門を建立しています。
境内の伽藍配置は吉川神道の教えに基づき東西方向に建物が一直線に並ぶ独特な配置としています(会津藩初代藩主保科正之も神式の霊廟で土津神社の境内に葬られましたが、社殿は戊辰戦争の兵火で焼失した為、現存社殿としては全国唯一と言われています)。




















【陸奥國 古社巡り】
高照神社(たかてる~)は、青森県弘前市高岡字神馬野にある神社。旧社格は県社。祭神は津軽信正命(津軽藩4代藩主)。別称は「高照霊社」、「高岡霊社」、「高岡さま」。本殿、中門、西軒廊、東軒廊、拝殿及び幣殿、廟所拝殿などが国指定の重要文化財。
『陸奥國津軽高岡高照霊社御縁起』によると、江戸時代中期の1711年、弘前藩5代藩主・信寿が、先代の津軽信正の廟所を建立したことに始まる。信正は生前、吉川神道の創始者・吉川惟足に師事していたことから、吉川神道の思想に基づき社殿が造営され、祭祀が行われた。以後、津軽氏歴代藩主に崇敬された。明治時代に入り、近代社格制度のもと郷社に列し、春日4神と藩祖・津軽為信を合祀、のち県社に昇格した。
当社は、JR奥羽本線・弘前駅の西北西12kmの緩やかな丘が続く山あいにある。境内は広く森に囲まれていて、境内東端入口は県道30号線に面している。南側の敷地には「高岡の森 弘前藩歴史館」がある。深い木々の神聖な空気の漂う参道を進むと、歴史の風格を感じさせてくれる、国重文の大きな社殿に辿り着く。なお、社殿の背後(西側)少し離れたところに津軽信政公廟所があり、こちらも国重文だが、自分の雑な下調べにより見逃してしまった。かなりショック…(^_^;)
今回は、拝殿、幣殿、本殿などが国重文の古社であることから参拝することに。参拝時は休日の午前中で、自分以外にも参拝者を数人見掛けた。
※社務所は無人だが、御朱印は一之鳥居の県道を挟んで向かい側にある商店で拝受できる。

境内東端入口の<一之鳥居>と<社号標>。

<一之鳥居>は木製の両部鳥居。

しばらく真っ直ぐ進んで<二之鳥居>。石製の神明鳥居。
この辺りは「高岡の森 弘前藩歴史館」の駐車場になっていて、駐車場の真ん中にある。

参道左側の<忠魂碑>群。後ろに見えるのが「高岡の森 弘前藩歴史館」。人気があるみたい。

さらに進むと水路が流れていて<神橋>が架かっており、その先には<三之鳥居>がある。

参道左側の<手水盤>。

参道右側の<神馬>。

参道の正面には<随神門>。1810年造営、3間1戸、切妻造、鉄板葺の八脚門。
神域は朱色で塗られた塀で囲まれている。

随神門をくぐってさらに進み、参道左側にある<手水舎>。(さっき手水盤があったのに...(^_^;))

<拝殿>全景。1755年造替。桁行7間梁間3間の入母屋造、杮葺。正面屋根に千鳥破風、中央3間に軒唐破風の向拝が張り出している。外部は丹塗り、内部は弁柄塗り。国指定の重要文化財。
ちなみに拝殿の後方から突き出す形の<幣殿>は、桁行2間梁間3間の切妻造妻入。国指定の重要文化財。

<拝殿>正面。華やかな丹塗りの躯体に、軒下の極彩色が施された彫刻が映える。

<拝殿>内部。弁柄塗りの内装。左右上部の大絵馬(県重宝)は、津軽藩や幕府お抱えの狩野派の絵師が描き、藩主やその家族、家老たちが奉納したとのこと。

拝殿から振り返って境内全景。

拝殿後ろの<中門>と<本殿>。中門の手前が<東軒廊>、その奥が<西軒廊>。4件いずれもが国指定の重要文化財。

<東軒廊>と<西軒廊>の間にある<中門>。いずれも1712年の造営。
<中門>は1間1戸の平唐門、柿葺。<東軒廊>と<西軒廊>はいずれも桁行4間梁間1間の切妻造、柿葺。

一段高い場所に瑞垣で囲まれている<本殿>。1712年の造営。桁行3間梁間3間の入母屋造。正面屋根には千鳥破風、1間の向拝には唐破風が付く。外部は丹塗り、内部は一室で朱塗り、中央基壇上に方一間の宮殿が備わっているとのこと。

最後に、大きく威厳のある<社殿>全景。
あらゆる構造物に歴史的価値がある、国指定の重要文化財のかたまり、オンパレード。
弘前藩主・津軽家の栄華が偲ばれる。(^▽^)/
歴史
弘前藩の4代藩主津軽信政公の祀られている神社です。
信政公は吉川神道を学んでいて、死後はここに祀るようにと言い残し亡くなったあと高照神社に祀られました。
弘前藩の一大事にはお告げ御用と言って信政公に子細を報告する神事も行われていたそうです。
| 名称 | 高照神社 |
|---|---|
| 読み方 | たかてるじんじゃ |
| 御朱印 | あり |
| 限定御朱印 | なし |
| 絵馬 | あり |
詳細情報
| ご祭神 | 津軽信政公 |
|---|---|
| ご由緒 | 弘前藩の4代藩主津軽信政公の祀られている神社です。
弘前藩の一大事にはお告げ御用と言って信政公に子細を報告する神事も行われていたそうです。 |
| 体験 | 重要文化財武将・サムライ |
Wikipediaからの引用
| 概要 | 高照神社(たかてるじんじゃ)は、青森県弘前市に鎮座する神社。弘前藩4代藩主・津軽信政の廟所に始まり、信政を神として祀る。平成18年(2006年)に社殿の多くが国の重要文化財に指定された。 |
|---|---|
| 歴史 | 歴史[編集] 宝永7年(1710年)に卒去した弘前藩4代藩主の津軽信政の廟所に起源を持つ。信政は生前、吉川神道の創始者・吉川惟足に師事していた経緯があり、信政の遺命により5代藩主・信寿が、幕府の神道方で吉川神道2代・吉川従長(よしかわ よりなが・1655 - 1730)[注 1]を斎主[注 2]とし神葬祭を行い、高岡の地に埋葬した[1]。埋葬地には、本墓と拝墓の2つの墓碑が東西線軸上で前後に建てられ[2]、後方(西側)にある本墓の八角柱の墓碑には「宝永七庚寅年」の銘が刻まれている[3]。葬儀は津軽家の菩提寺の天台宗・報恩寺で、吉川神道に基づいた祭儀により営まれ、その後、遺骸は高岡に葬送し...Wikipediaで続きを読む |
| 引用元情報 | 「高照神社」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E9%AB%98%E7%85%A7%E7%A5%9E%E7%A4%BE&oldid=99318586 |
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ























1
0