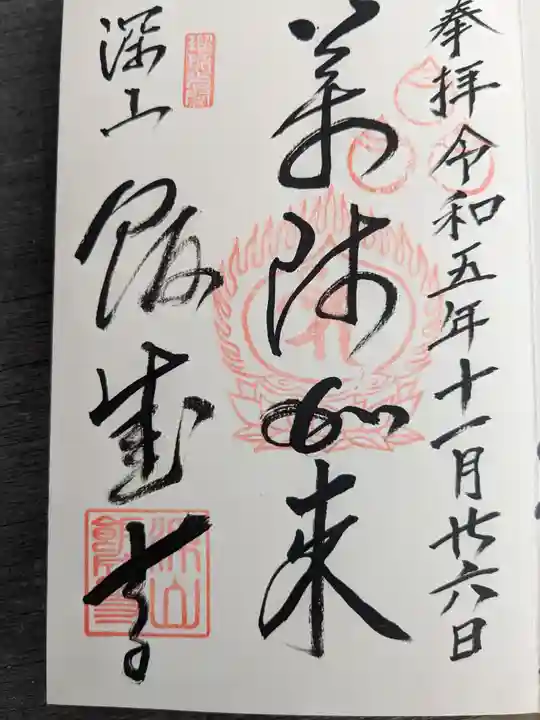はんじょうじ|高野山真言宗|深山
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方深山 飯盛寺のお参りの記録一覧
1〜4件4件中
絞り込み
複数語は空白区切り
参拝期間
----年--月
〜----年--月
御朱印関連
フォロー中
自分
サポーター
検索する
絞り込み限定
投稿日降順
キーワード
参拝----年--月〜----年--月
御朱印
フォロー
自分
サポーター
検索

タンホイザ
2024年07月23日(火)3892投稿

惣一郎
2022年11月06日(日)1269投稿
【若狭國 古刹巡り】
飯盛寺(はんじょうじ)は、福井県小浜市飯盛にある高野山真言宗の寺院。山号は深山(しんざん)。本尊は薬師如来。本堂は国指定の重要文化財。
寺伝によると、創建は南北朝時代の文和年中(1352年~1356年)、後光厳院の勅願所として建立され、最盛時は七堂伽藍十二坊を擁した。室町時代の1484年に火災に遭い、本堂、塔頭、什物すべてを焼失した。現在の本堂は1489年の再建で、桁行5間、梁間5間、単層、寄棟造、妻入、桟瓦葺(かつては茅葺)となっている。
当寺は、JR小浜線・加斗駅の南方2kmの山の中、飯盛川沿いに登る山道の突き当りにある。境内と言っても、仕切りや壁があるわけではないので、山の中に伽藍がある感じ。山道の突き当りの境内北端に駐車場、納経所、庫裏があり、南方少し離れた場所に山門、参道、一段高いところに本堂、大師堂があるという造り。豊かな自然の中に佇む、まさに山寺の雰囲気。
今回は、本堂が国重文であることから参拝することに。参拝時は休日の午前中で、到着時ちょうどお寺の方が所用で出掛けるところで、御朱印は拝受できたが、本堂には入ることはできなかった。自分以外にも数組参拝者が訪れていた。
もっと読む最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ