にうかんしょうぶじんじゃ
あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

| 御朱印 | 真ん中に丹生神社と書かれ、右上に弘法大師創建の印、真ん中に丹生官省符神社の印、左上に官省符の印、左下に高野山町石道登山口の印が押されています。 | ||
|---|---|---|---|
| 限定 | - | ||
| 御朱印帳 | |||
| 駐車場 | あり |
和歌山県のおすすめ🌸
おすすめの投稿

和歌山、紀の川と橋本の参拝、慈尊院から石段をあがって丹生官省符神社へ。
丹生官省符神社は、弘法大師が高野山開山の際に政所として慈尊院を創建、さらに丹生高野明神社を創建されたとあります。かつては壮麗を極めたそうですが神仏分離令により大きく縮小し、現在の建物となったようです。
境内からは本殿横に高野山を望み、高野山詣での玄関口として機能したようです。祀神は丹生明神、高野明神、天照大神、気比明神、八幡大神、春日大神、厳島明神。鮮やかな朱塗りの本殿は本来四棟あったものが一棟失われているそうです。
御朱印をいただく際に、そこの石版から見ると高野山が見えると教えていただき、無事拝めました。

御朱印

世界遺産20周年御朱印もいただきました。

慈尊院からの石段。わりと急です。

一の鳥居。

二の鳥居。

石段上から。

拝殿。

拝殿から本殿。

見づらいですが、本殿。

こちらも本殿。

わずかに覗く空部分に高野山が見えます。

丹生官省符神社(にうかんしょうぶじんじゃ)
~ 令和五年
㊗️弘法大師御誕生千二百五十年 ~
主祭神 丹生都比売大神
高野御子大神
大食都比売大神
市杵島比売大神
天照大御神
誉田別大神
天児屋根大神
創建 弘仁7年(816年)
本檜皮葺
札所等
神仏霊場巡拝の道第11番(和歌山第11番)
例祭日 10月第4日曜 官省符祭
弘法大師が慈尊院を開創された弘仁7年(816年)、その守神として地元にゆかりのある丹生都比売・高野御子の二神をお祀りした神社です。
社殿三棟は木造一間社春日造、桧皮葺、極彩色北面で重要文化財に指定されています。
丹生官省符神社の神様の使いである白黒2頭の犬は、安産、子授け祈願、縁結びの神さまとして古くから尊崇され、家内安全、試験合格、商売繁盛、交通安全、厄祓、厄除、病気平癒などのご利益があるとされます。
社名の「丹」は、銅の製錬技術にはなくてはならないもので、古代より魔除けの象徴とされてきました。
神社ができた当時の位置は、現在の渡し場の東にあたる宮の橋の付近であったと考えられています。
その後、河北から高野領地となり、官省符21ヶ所村が成立すると、その総氏神として栄えてきました。
慈尊院の弥勒堂が現在の位置に移された際、この神社も一段高い神楽尾山へ移されました。
その時、天野神社にならい気比、厳島二神を合わせ祀って四神とし、古くからこの地に御鎮座されていた天照、八幡、春日の三神を合わせ祀って七社明神としました。
御本殿は、平成16年(2004年)に「紀伊山地の霊場と参詣道」として、世界遺産に登録されました。
和歌山県伊都郡九度山町慈尊院835

丹生官省符神社
弘法大師御誕生千二百五十年記念御朱印
高野明神


































丹生官省符神社の基本情報
| 住所 | 和歌山県伊都郡九度山町慈尊院835 |
|---|---|
| 行き方 | JR和歌山線「高野口」駅より徒歩40分 車の場合、京奈和自動車道「高野口」ICより10分 |
和歌山県のおすすめ🌸
| 名称 | 丹生官省符神社 |
|---|---|
| 読み方 | にうかんしょうぶじんじゃ |
| 通称 | 九土山丹生神社 |
| 参拝にかかる時間 | 15分 |
| 御朱印 | あり 真ん中に丹生神社と書かれ、右上に弘法大師創建の印、真ん中に丹生官省符神社の印、左上に官省符の印、左下に高野山町石道登山口の印が押されています。 |
| 限定御朱印 | なし |
| 御朱印帳 | あり |
| 電話番号 | 0736-54-2754 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |
| ホームページ | http://niujinja.sakura.ne.jp |
| 絵馬 | あり |
巡礼の詳細情報
| 神仏霊場巡拝の道 |
|---|
詳細情報
| ご祭神 | 《合》宇迦魂大神,猿田彦大神,保食大神,金山彦大神,木花開耶姫大神,八王子大神,迦具土大神,飯炊大神,菅原道真,金刀比羅大神,蛭子大神,大黒天神,槙尾大神,子守大神,《主》丹生都比売大神,高野御子大神,《配》市杵島比売大神,大食都比売大神,天照大神,誉田別大神,天児屋根大神 |
|---|---|
| 創始者 | 空海 |
| 体験 | 世界遺産札所・七福神巡り |
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ





























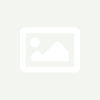







11
0