たいりゅうじ|東寺真言宗|再度山
大龍寺兵庫県 新神戸駅
9:00〜17:00
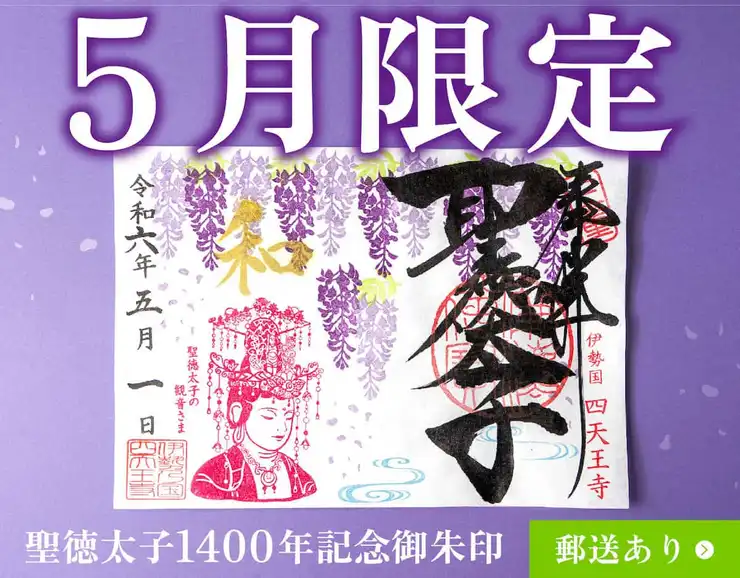
| 御朱印 | |||
|---|---|---|---|
| 限定 | - | ||
| 御朱印帳 | - | ありません | |
| 駐車場 | 山門前に駐車場スペースあり |
近畿36不動尊第9番霊場で、参拝。神戸三宮から20分位のとこですが、既に山の中にあり、訪問者は少なかったですが、ゆっくりと参拝することができました。
東寺真言宗別格本山 再度山 大龍寺
まず最初に驚いたのは、ここが神戸市中央区だったということでした。
三宮やハーバーランドと同じ中央区・・・神戸に住んでいながら知りませんでした😅
創建は神護景雲2年(768年)と云われており、称徳天皇勅願を受けた和気清麻呂によって創建されたそうです。
創建当時は、摩尼山如意輪寺と号していたとか。
延暦年間(782~806年)に入唐前の空海が参堂し、帰朝後にふたたび訪れたことから「再度山」の名が付けられ、阿波の大龍岳に似ていることから「大龍寺」と名付けられたそうです。
本堂のお参りを済ませ、御朱印をいただこうと霊明殿に向かったのですが、ご祈願のお勤め中だったためしばらく待たせていただいたのですが、「今日は縁がなかったのかな?」と思い、一旦山門に向かって帰りかけたときにふと奥の院にお参りしてないことに気付き、Uターンしました。
ここで思い出していなかったら帰宅後後悔するところでした。
そして奥の院のお参り後、「弘法大師自作亀石」があることを知り、そこからさらに登山することに。
無事に亀石を拝むこともできて、再度霊明殿に向かってみたのですが、今度は別の方のご祈願中でした。
やっぱりこの日はご縁がなかったようです。
しかしきれいな紅葉も見れたし、想定外の軽い登山でいい運動になったし、大満足でした。
山門
水子地蔵尊
みんないい顔してます
仁王門
仁王門くぐってすぐ右手にある手水舎
まっすぐ進むと本堂
なんですが、左側にある権倉稲荷大明神と書かれた鳥居方向に進みました
権倉稲荷大明神の鳥居
鳥居が続いてなかなかたどり着けないのでちょっと不安になります。
この左手の鳥居の先に鐘楼が見えてきます
ようやく権倉稲荷大明神にたどり着きました。
再度山厄除不動明王
本堂
御本尊 菩薩立像
本堂の手挟みの彫刻もなかなか素敵でした
奉納燈籠
左奥に見えているのは、ぼけ封じ三十三ケ所第8番札所の観音像
毘沙門堂
毘沙門天、大黒天、弁財天が祀られています
毘沙門堂の彫刻
護摩堂
不動明王が祀られています
霊明殿前で猫ちゃん達がご飯をもらっていました
諸天堂
諸天堂の彫刻
諸天堂の扁額
奥の院大師堂
護摩堂の右側から奥の院へと進む道がひっそりとあります。
先に進むのに必至で、途中の山道は写真撮ってません😅
山道には八十八か所巡りの祠が並んでいました。
そして「大師の霊水」というものがあるらしいのですが、どこにあるのか判らず・・・
帰宅後に調べたら、この奥の院大師堂の後ろにあるらしいです。
奥院大師堂の右手には「弘法大師自作亀石」の文字が。
右手に道が続いており、「右一丁上ル」と書かれています。
一丁=約100mちょっとか・・・折角だし行ってみよう!
途中には「貴姫大御神」
ここから先が少し軽い登山になります。
100mを甘く見てました。
なんとか登りきった先に大きな岩が現れます。
こちらは天狗岩
あれ?亀石は?
この大きな岩の右上にありました。
上に登って写真を撮りたいところでしたが、下山する体力も残しておかねばと思いとどまりました。
天狗岩からさらにちょっとだけ登ると再度山頂上に到着。
ハイキングをされてる方が数名いらっしゃいました。
「毎日登山」の碑
東寺真言宗別格本山 再度山 大龍寺
近畿三十六不動尊霊場第九番札所
西国愛染霊場第五番札所
摂津西国三十三ヶ所第六番札所
神戸七福神霊場(大黒天)
神戸十三仏霊場第六番札所
摂津八十八ヶ所第八十二番札所
近畿十楽観音第八番札所
ぼけ封じ三十三ヶ所第八番札所
昨年11月にもお参りさせていただいたのですが、今回は神戸十三仏霊場巡りでお参りさせていただきました。
前回は紅葉の季節ということもあり、お参りされる方もちらほらといらっしゃいましたが、今回はハイカーの方が数人いらっしゃるだけでゆっくりとお参りさせていただきました。
また御朱印をいただく際には、しいたけ茶をいただき、ご住職ともお話させていただきました。
1250年以上の歴史を誇る山の中にある静かなお寺ですが、三宮からバスで約20分ほどで到着します。
昔は道路も十分ではなかったようで、参道を歩いて登るしかなかったようですが、それが故にこのお寺が現在も残ったのではないかとのこと。
ご住職も大変お優しい方で、またお参りしたいと思う素敵なお寺です。
ご詠歌
六つのちり 五つの欲も 立ちかへり
再び洗ふ 山の井の水
神戸十三仏霊場 御朱印
山門
山門の先の上り坂を登り切ると仁王門が見えてきます
仁王門
左に見えているのは権倉稲荷大明神の鳥居
前回はまず左手に進みましたが、今回はまっすぐ本堂を目指します
本堂
御本尊の如意輪観世音菩薩様(重文)は直接お目にはかかれませんでした。
修行大師
毘沙門堂
護摩堂
奥の院大師堂
前回「大師の霊水」がどこにあるのか判らず諦めて帰ったのですが、この大師堂の後ろにあるということで覗いてみました。
「大師の霊水」はここから湧き出るらしいのですが涸れていました。
あとでご住職にお聞きしたところ、この時期(乾期)は水が涸れるらしく、雨期の頃でないととのことでした。
山門前の六地蔵様
神戸七福神霊場巡りもこの機会にスタート❗
大黒天の御朱印
| 名称 | 大龍寺 |
|---|---|
| 読み方 | たいりゅうじ |
| 参拝時間 | 9:00〜17:00 |
| 参拝料 | なし |
| 御朱印 | あり |
| 限定御朱印 | なし |
| 御朱印帳 | なし |
| 電話番号 | 078-341-3482 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |
| ホームページ | http://www.tairyuji.com |
| 近畿三十六不動尊霊場 第9番 | 御詠歌: 大小の 祈る力の げにいわや 石の中にも 極楽ぞある |
|---|---|
| 摂津国三十三箇所 第6番 | 御本尊:聖観音 |
| 西国愛染十七霊場 第5番 | 御詠歌: 六(む)つの塵(ちり) 五つの慾(よく)も たちかへり 再度(ふたたび)洗う 山の井の水 |
| 摂津国八十八箇所 第82番 | 御本尊:聖如意輪観世音菩薩 御詠歌: 六つのちり 五つの欲も 立ちかへ里 ふたたび洗う 山の井の水 |
| 神戸十三仏霊場 第6番 | 御本尊:弥勒菩薩 御真言: おん、まいたれいや、そわか 御詠歌: 六つのちり 五つの欲も 立ちかへり 再び洗ふ 山の井の水 |
| ご本尊 | 聖如意輪観世音菩薩 |
|---|---|
| 山号 | 再度山 |
| 宗旨・宗派 | 東寺真言宗 |
| 創建時代 | 神護景雲二年(768) |
| 開山・開基 | 和気清麿 |
| 文化財 | 木造菩薩立像(国指定重要文化財) |
| 体験 | 重要文化財札所・七福神巡り |
| 概要 | 大龍寺(たいりゅうじ)は、兵庫県神戸市中央区神戸港地方再度山にある東寺真言宗の別格本山の寺院。山号は再度山(ふたたびさん)。本尊は如意輪観音。通称は中風除けの寺と呼ばれる。 |
|---|---|
| 歴史 | 歴史[編集] 寺伝によれば、称徳天皇の勅命により寺院を建立するのに適した地を探していた和気清麻呂が、摩尼山(再度山)山頂近くの南斜面であるこの地で道鏡の刺客に襲われた。しかし、突如現れた龍によって命を助けられたという。そこで、神護景雲2年(768年)に清麻呂は勅許を得て自らが所有していた行基菩薩が一刀三礼して彫り上げたという聖如意輪観世音菩薩像を建立した堂に祀り、摩尼山大龍寺と名付けたという。これが当寺の始まりであるという。 延暦23年(804年)には空海が唐に渡る直前に当寺に参詣し、その帰国後、再度当寺に参詣したという。その話から当寺の山号は次第に再度山と呼ばれるようになったとする。 ...Wikipediaで続きを読む |
| アクセス | 交通アクセス[編集] JR神戸線 三ノ宮駅 から市バスで森林植物園か再度山行バス30分、大龍寺山門前下車徒歩10分(冬季運休) JR神戸線 三ノ宮駅 から市バス10分、諏訪山公園前から徒歩1時間30分(ハイキングコース) |
| 行事 | 行事[編集] 1月1日〜3日 - 除夜の鐘ならびに修正会 1月6日 - 寒の入り中風除大祈祷加持 1月21日 - 初大師 2月3日 - 節分星まつり 3月21日 - 彼岸大師 4月第2日曜日 - 春季永代土砂加持法会 7月20日 - 中風除大祈祷加持 8月21日 - 柴灯護摩修行 9月21日 - 彼岸大師 10月第2日曜日 - 秋季永代土砂加持法会 |
| 引用元情報 | 「大龍寺 (神戸市)」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E5%A4%A7%E9%BE%8D%E5%AF%BA%20%28%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%B8%82%29&oldid=95546099 |
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。
ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ










































































9
0