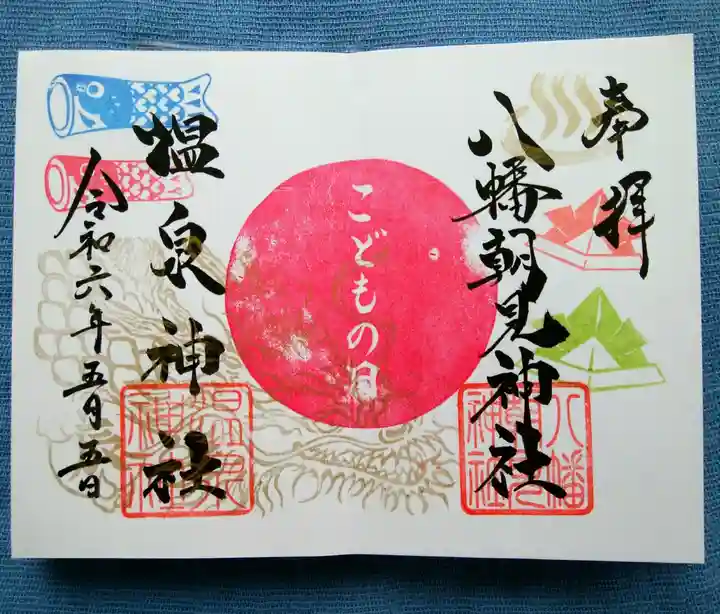はちまんあさみじんじゃ
八幡朝見神社大分県 別府駅
社務所:09:00〜17:00
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方
九州の旅⑫ 別府温泉総鎮守♨️『八幡朝見神社』『温泉神社』
素晴らしい眺望と美しい境内、結婚式へ向かう新郎新婦を祝福して参拝ヘ🍀
素敵な御朱印は種類も豊富 (*´∇`)
縁結びのパワースポット✨魅力もいっぱいです♪
雰囲気のいいカフェでは御神水がいただけます。
建久七丙辰年(1196年)に豊前・豊後守護職の大友能直公により創建。
鶴岡八幡宮の御勧請を受けに鎌倉まで向かったと知れば、趣があり美しい境内が鶴岡八幡宮と重なるように感じます!戦後の国家神道指令(GHQ)により、温泉神社が合祀され今のかたちになったそうです。
神社の下調べはせずに温泉がメインで訪れた別府。
「こんなに素敵な神社があるの!」 ~そんな嬉しい驚き (*´μ`*)
風情あるまちなみに様々な温泉🎵いい参拝までできて最高です。
こどもの日🎌限定御朱印
龍に温泉♨、兜と鯉のぼり🎏
御朱印帖いっぱいに書いてくださいました!
素晴らしい旅の記念です😊
新緑に鮮やかな朱の拝殿が素敵でした。
高低差のある境内は景色も素晴らしい✨
八幡朝見神社は、建久七丙辰年(1196)十月九日に、大友能直公により御創建されました。 豊前・豊後の守護職として、この地に赴任された大友能直公は入国するとすぐに、鎌倉幕府の鎮守、鶴岡八幡宮の御勧請を志しました。家臣能登助国久は朝見の庄民とともに鎌倉に赴き、建久七年十月朔日、神輿を奉じて久光文字の浜に到着いたしました。能直公は龍ヶ岡に社地を定め十月九日御鎮座申し上げました。現在の乙原の地であり、豊後八幡宮七社の一であります。
| 名称 | 八幡朝見神社 |
|---|---|
| 読み方 | はちまんあさみじんじゃ |
| 通称 | 八幡様、朝見様 |
| 参拝時間 | 社務所:09:00〜17:00 |
| 参拝にかかる時間 | 約20分 |
| 参拝料 | なし |
| トイレ | 有り |
| 御朱印 | あり 『湯けむり』や『勾玉』などの印が押された、カラフルな祝日限定御朱印がいただけます。 |
| 限定御朱印 | あり |
| 御朱印帳に直書き | あり |
| 御朱印の郵送対応 | なし |
| 御朱印帳 | あり |
| 電話番号 | 0977-23-1408 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |
| ホームページ | http://www.asami.or.jp/ |
| おみくじ | あり |
| お守り | あり |
| 絵馬 | あり |
| SNS |
| ご祭神 | 《主祭神》 大鷦鷯尊 《配祀神》 誉田別命 足仲彦命 気長足姫命 《合祀神》 大歳神 迦具土命 大穴牟遅命 少彦名命 |
|---|---|
| ご神体 | 不詳 |
| 創建時代 | 建久七丙辰年(1196年) |
| 創始者 | 大友能直 |
| 本殿 | 三間社流造 |
| 文化財 | クスノキとアラカシ林(大分県指定天然記念物)
|
| ご由緒 | 八幡朝見神社は、建久七丙辰年(1196)十月九日に、大友能直公により御創建されました。 豊前・豊後の守護職として、この地に赴任された大友能直公は入国するとすぐに、鎌倉幕府の鎮守、鶴岡八幡宮の御勧請を志しました。家臣能登助国久は朝見の庄民とともに鎌倉に赴き、建久七年十月朔日、神輿を奉じて久光文字の浜に到着いたしました。能直公は龍ヶ岡に社地を定め十月九日御鎮座申し上げました。現在の乙原の地であり、豊後八幡宮七社の一であります。 |
| ご利益 | |
| 体験 |
ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。
ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ