こうみょうじ|曹洞宗|般若山
光明寺公式静岡県 裾野駅
御朱印受付時間は下記のカレンダーをご覧ください。
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=hid5u71a8856s97jgq9sfnpehg%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FTokyo
*檀務の都合による急な変更もございます。必ずご来山前にご確認ください。
*仏像拝観も、御朱印対応時間にお願いいたします。
特にご用がある場合や遠方からお見えになる場合などはお電話・SNS等でご連絡いただければ時間外でも調整いたしますので、お気軽にご連絡ください。
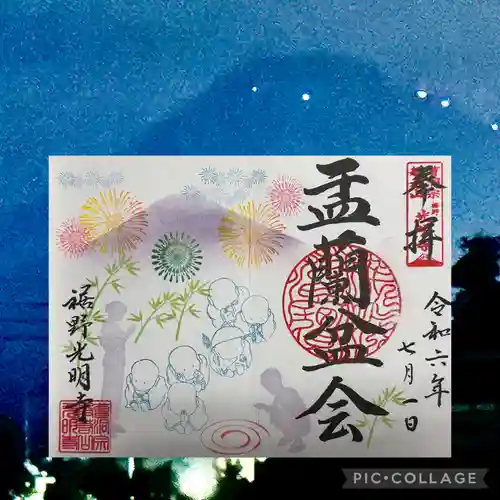







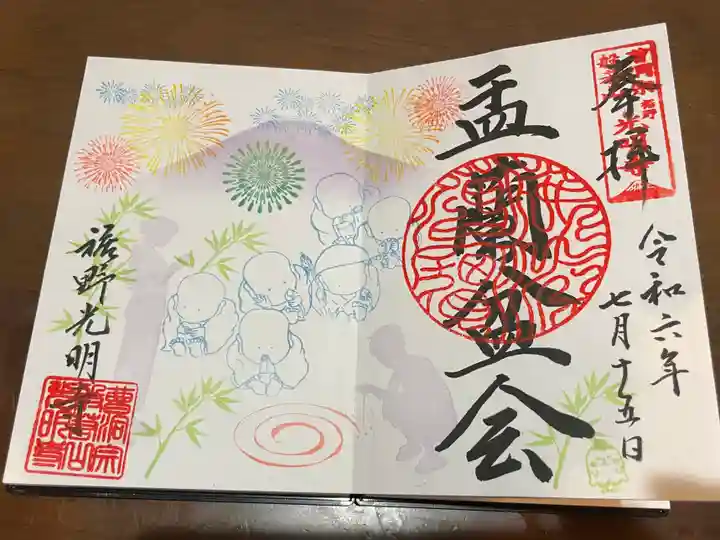
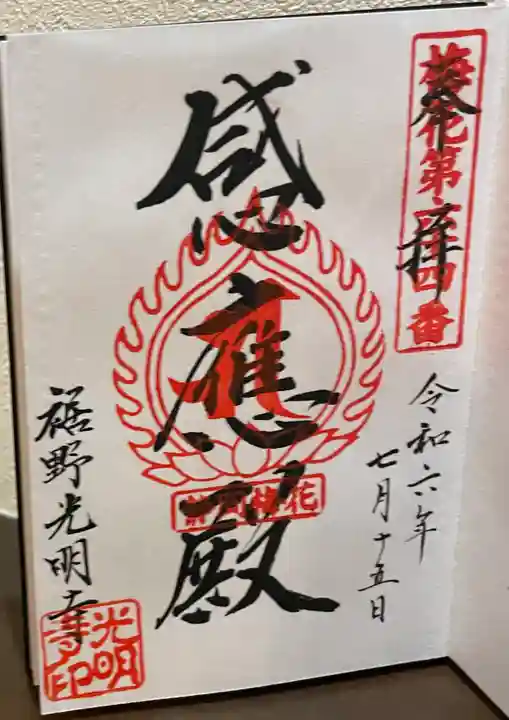
































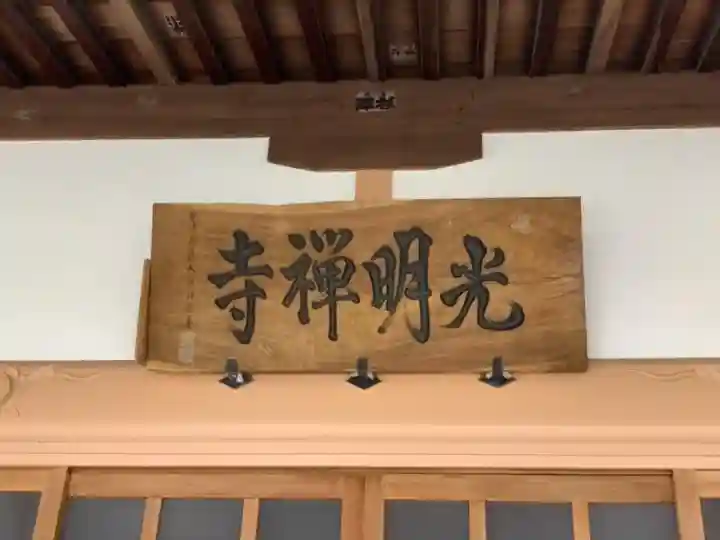













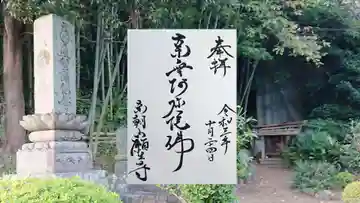






2
0