はぎひよしじんじゃ
あなたのサポートが必要です〈特典あり〉
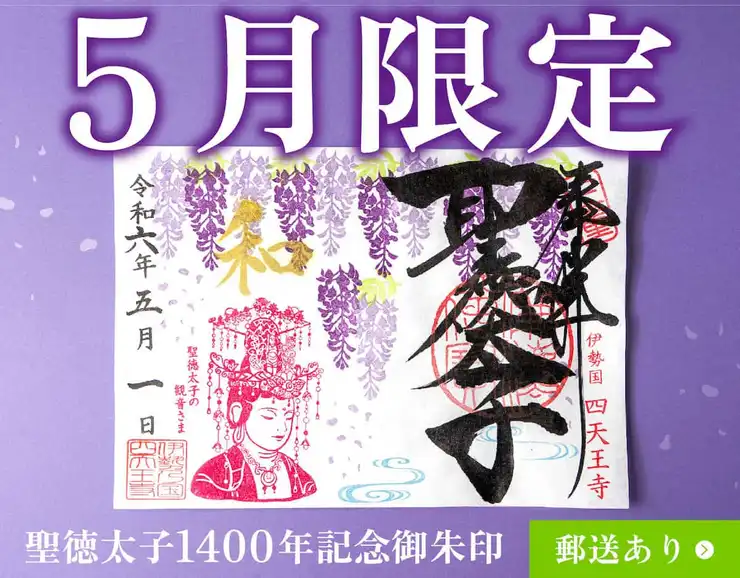
| 御朱印 | |||
|---|---|---|---|
| 限定 | - | ||
| 御朱印帳 | - | ||
| 駐車場 | あり |
おすすめの投稿

本日のドライブ神社巡りの目的地、萩日吉神社、ホトカミの投稿で知り参拝⛩
6世紀蘇我氏によって創建され萩明神と呼ばれていました。平安時代に比叡山から日吉大神を勧請合祀し萩日吉山王宮に改称したと言われています。萩日吉神社概要より
1月第3日曜日には、流鏑馬祭🏹がありこの時に縁起物の奉納猿🐵が販売されるそうです。
本日は雲一つない晴天で、来るまでの道のりも綺麗な桜や菜の花を見ながら来れたので来てよかったー*\(^o^)/*
山が近いし、境内には樹齢800年の児持杉を始め、杉の巨樹があり癒されました♪
社務所は閉まっていたので、電話で連絡したところ御自宅にて御朱印いただけるということでお伺いして、書き入れしていただきました。
御自宅は駐車場のすぐ前にありました^_^
外に出たらおばあちゃんにご苦労様ね、何処から来たの?
遠くからよくお参りでしたねと声かけていただきほっこりしました(*´ω`*)

杉の巨樹が並びます



鳥居の後ろには巨大な杉
樹齢800年の児持杉

祠があり、子宝にご利益



綺麗にされてます。


平 忠魂社




日吉神社ならではの
狛猿🐒さん


天気いいので緑も綺麗

拝殿


神楽殿

八坂神社


御神木




【山王様のお猿様:萩日吉神社】
「萩の山王様」として親しまれている萩日吉神社。
高さ8cmほど、3体の木彫りの猿。
裏には「山王社」と書かれています。
社務所は無人だったけれど、近所に神主さんのお宅があり、そこで授与して頂きました。
木肌の白い「ドロ」という木から作られているそうで、赤と黒と緑で簡単に彩色されています。
3体は親子なのかな?みなさん笑顔で良い表情をしています。
お猿様は山王権現の使いである猿を象ったもので、かつては子供の病気平癒のおまじないとされていました。
猿に添えられた縫い針を子供が患っている所と同じ箇所に刺して奉納すると子供の病が治るそうです。
※詳しくはブログ「郷土玩具の杜」をご覧下さい。
https://folktoys.blog.fc2.com/blog-entry-239.html
入手日:2004年6月13日
掲載されている内容は当時のものです、情報が古い場合がありますのでご了承下さい。

山王様のお猿様

山王様のお猿様(横から)

山王様のお猿様(後ろ側)

山王様のお猿様(上から)

お猿様の縁起

萩日吉神社

萩日吉神社

欽明天皇6年(544)蘇我稲目によって創建されたそうですが、500年代と言うのは、記憶のなかで一番古かったと思います。
確かに、、鳥居は見えるのですが、中は木々が茂り真っ暗で様子がわかりません。
ゾクゾクしました。

鳥居の奥が鬱蒼としていて、見えません。
神域、と言う感じをうけました。

鳥居の右に児持杉があります。

樹齢800年の杉は絨毯のように苔が生えています。



綺麗にお掃除されています。
初冬の15時は夕方の様に暗く寂しい。

イロハ四十八石階段
子供達にイロハ四十八で、文字や数を教えるため、石段を積んだ、と言うことかな?

イロハ四十八石階段


石造の祠
大田原市の西郷神社の様な派手な彫刻はありませんが、落ち着いた飾りがあります。

ニノ鳥居

立派な杉が立ち並んでいます。

手水舎

最後の石階段

両脇に狛猿

流鏑馬の時、納め猿、と言う木彫りの猿が売られているそうです。

なんだっけ?木の実?

神楽殿

拝殿
御朱印は神主さん宅でいただけるようです。
帰ってきてから知りました。
歴史
「平の山王様」「萩の山王様」と親しまれるこの萩日吉神社は、社伝によると欽明天皇六年(544)12月に蘇我稲目により創建されたと伝えられます。当初は、萩明神と称されましたが、平安時代初期に慈光寺一山鎮護のため、近江国(現滋賀県)比叡山麓にある坂本の日吉大社を勧請合祀して、萩日吉山王宮に改称したといわれています。
源頼朝は文治五年(1189)六月、欧州の藤原泰衡追討に際し、慈光寺に戦勝祈願しその宿願成就の後、慈光寺へ田畑千二百町歩を寄進しましたが、同時に当社へも御台北条政子の名により田畑一町七畝を寄進しています。以後社殿の造営が行われて別格の社となり、元禄十年(1697)以降は牧野家の崇敬が厚く、『風土記稿』には「山王社・村の鎮守なり」と記されています。明治元年(1868)の神仏分離令により、現在の神社名「萩日吉神社」となりました。
萩日吉神社の基本情報
| 住所 | 埼玉県比企郡ときがわ町西平1198 |
|---|---|
| 行き方 | JR八高線、明覚駅下車、町路線バス せせらぎバスセンター経由「宮平」バス停下車、徒歩5分
|
| 名称 | 萩日吉神社 |
|---|---|
| 読み方 | はぎひよしじんじゃ |
| 通称 | 平の山王様 |
| 参拝時間 | 参拝自由 |
| 参拝にかかる時間 | 20分 |
| 参拝料 | なし |
| 御朱印 | あり |
| 限定御朱印 | なし |
| 電話番号 | 0493-67-0119 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |
詳細情報
| ご祭神 | 《合》速玉之男命,天照大御神,木花開耶姫命,大山祇命,素盞嗚命,《主》大山咋命,国常立尊,天忍穂耳尊,国狭槌尊,伊弉冉尊,瓊瓊杵尊,惶根尊 |
|---|---|
| 創建時代 | 欽明天皇6年(537)11月 |
| 創始者 | 蘇我稲目 |
| 文化財 | 流鏑馬祭り,神楽(県指定無形民俗文化財)
|
| ご由緒 | 「平の山王様」「萩の山王様」と親しまれるこの萩日吉神社は、社伝によると欽明天皇六年(544)12月に蘇我稲目により創建されたと伝えられます。当初は、萩明神と称されましたが、平安時代初期に慈光寺一山鎮護のため、近江国(現滋賀県)比叡山麓にある坂本の日吉大社を勧請合祀して、萩日吉山王宮に改称したといわれています。
|
| 体験 | 御朱印 |
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ



























25
0