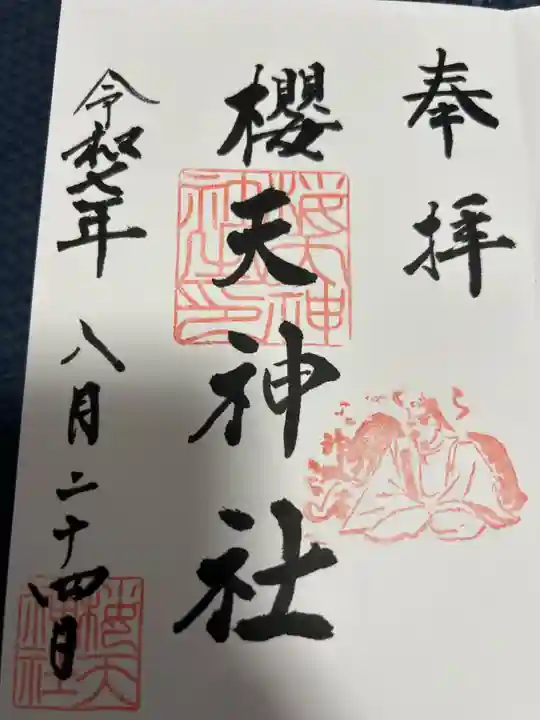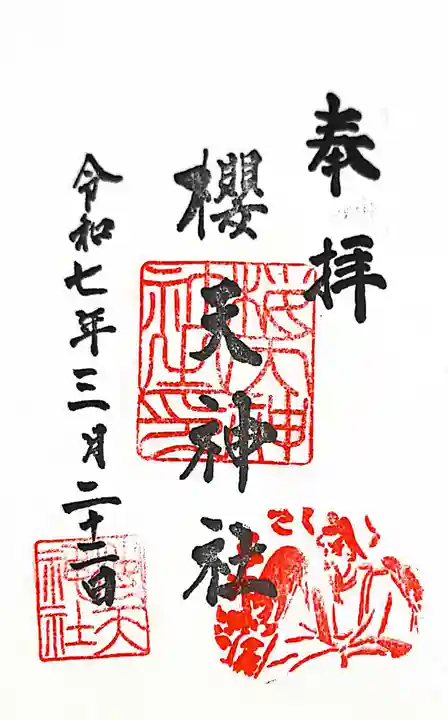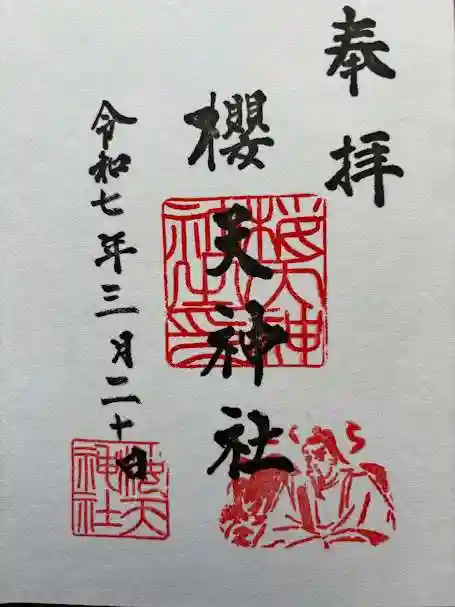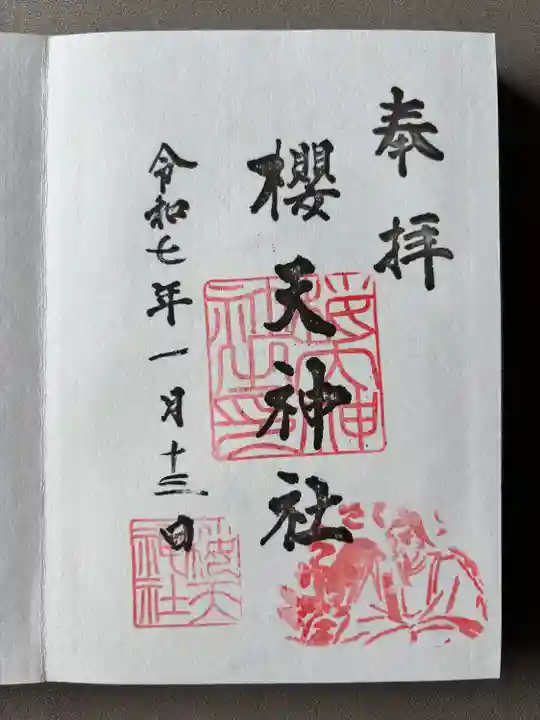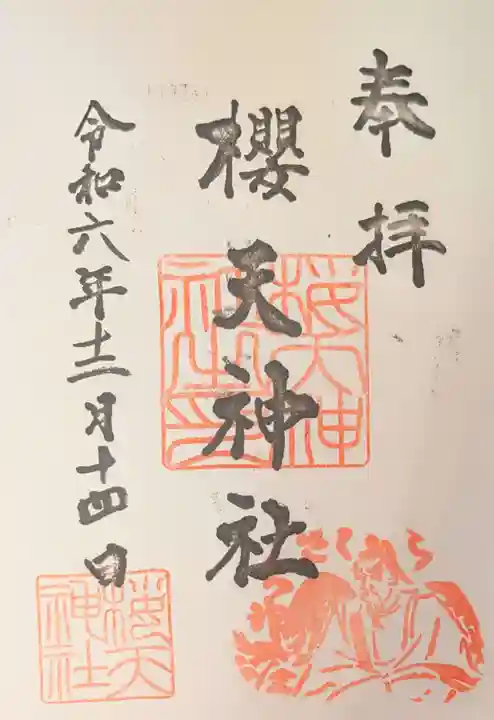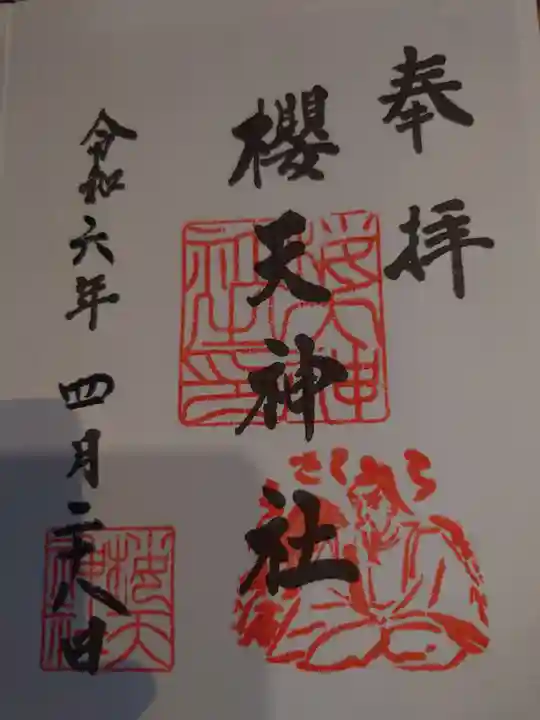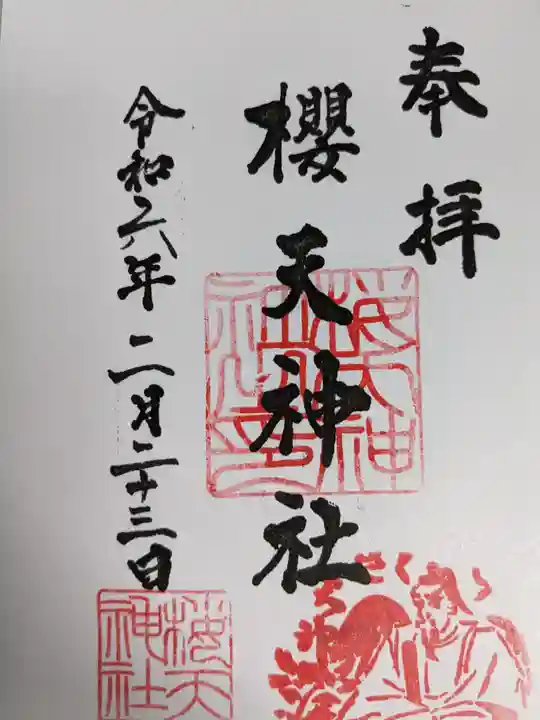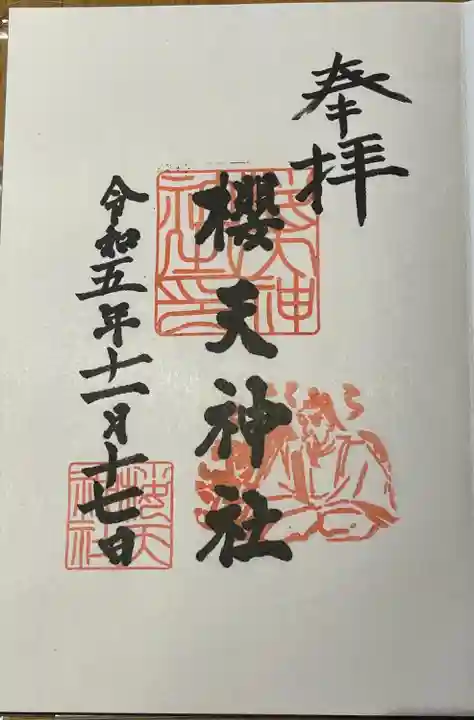さくらてんじんじゃ
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方櫻天神社のお参りの記録一覧
1 / 4ページ1〜25件90件中
絞り込み
複数語は空白区切り
参拝期間
----年--月
〜----年--月
御朱印関連
フォロー中
自分
サポーター
検索する
絞り込み限定
投稿日降順
キーワード
参拝----年--月〜----年--月
御朱印
フォロー
自分
サポーター
検索

ま~ちゃん
2025年06月11日(水)253投稿

shirobanbi🐈⬛
2025年01月15日(水)178投稿

Madelain#6
2025年01月06日(月)167投稿

ちょっと日本語話せる程度の…
2025年04月12日(土)80投稿

ゆりま
2024年06月28日(金)236投稿
愛知県のおすすめ2選🎌
広告
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ