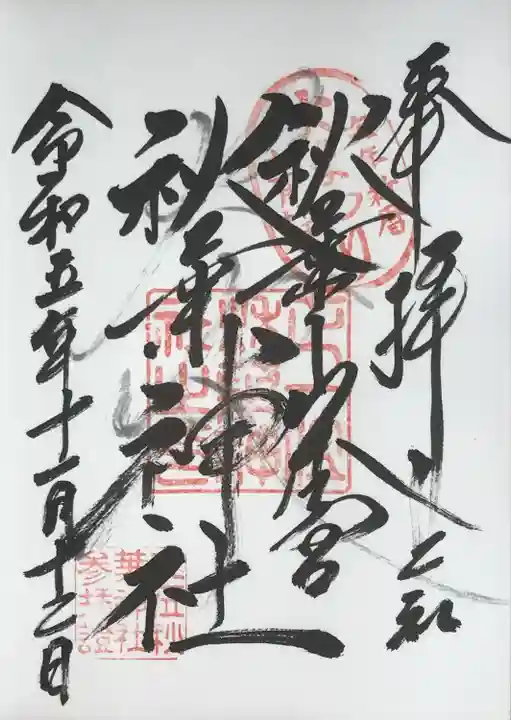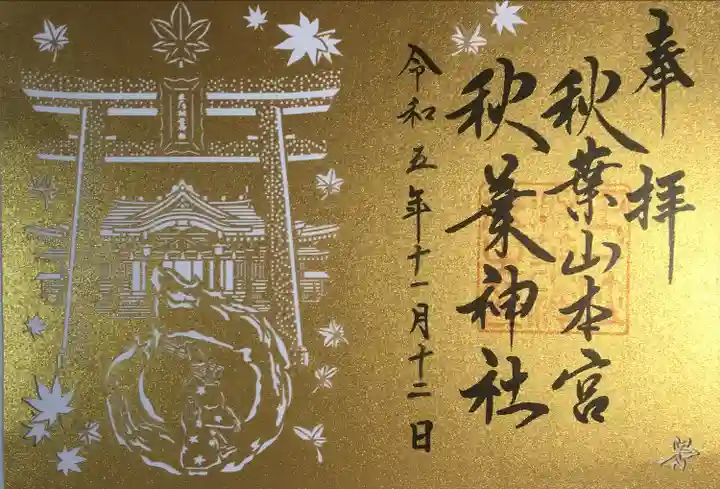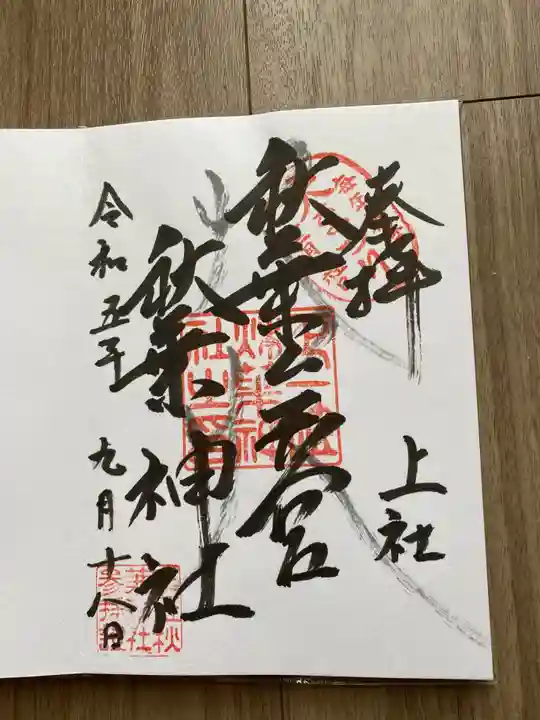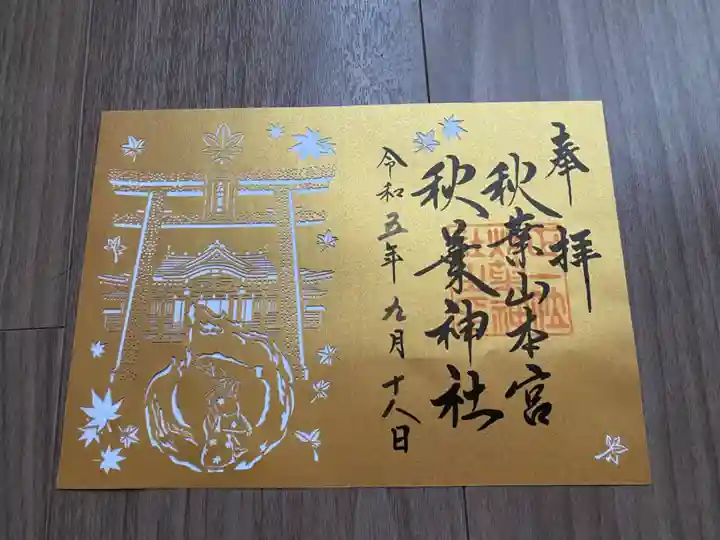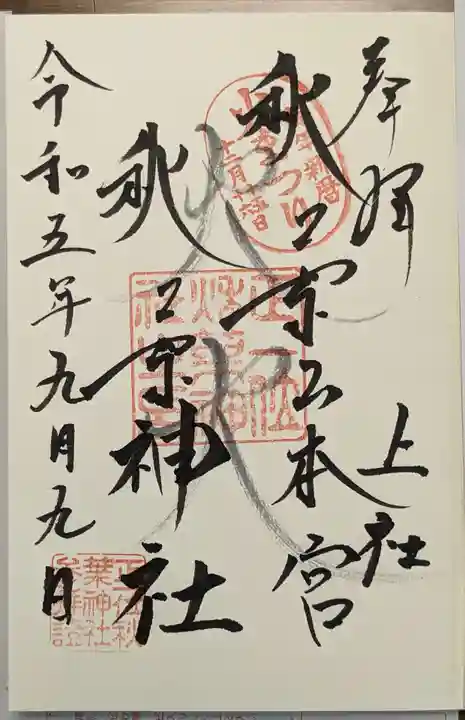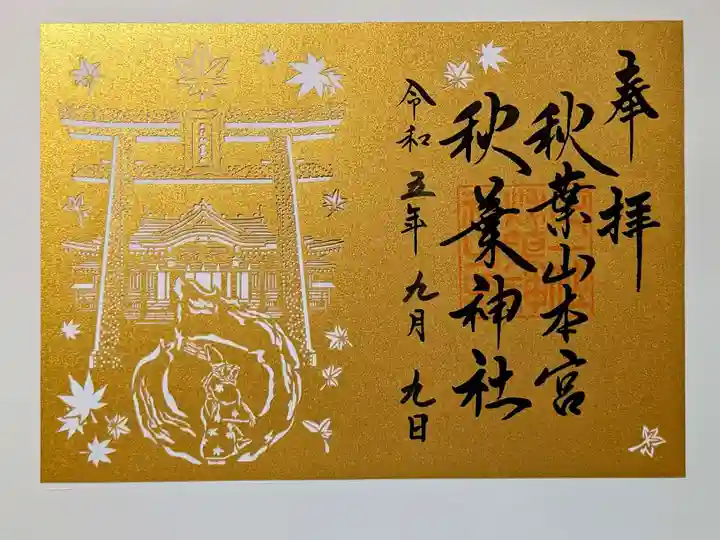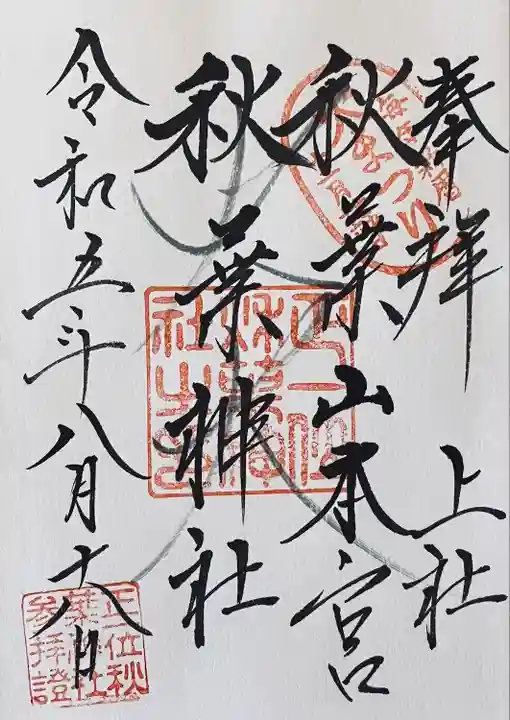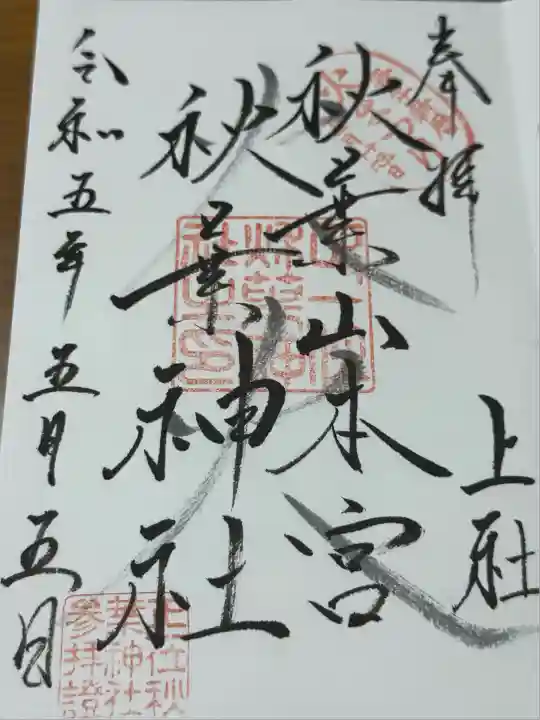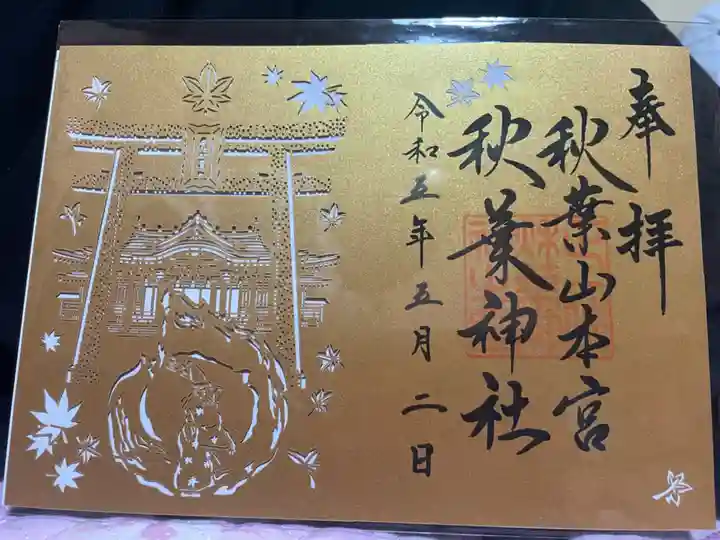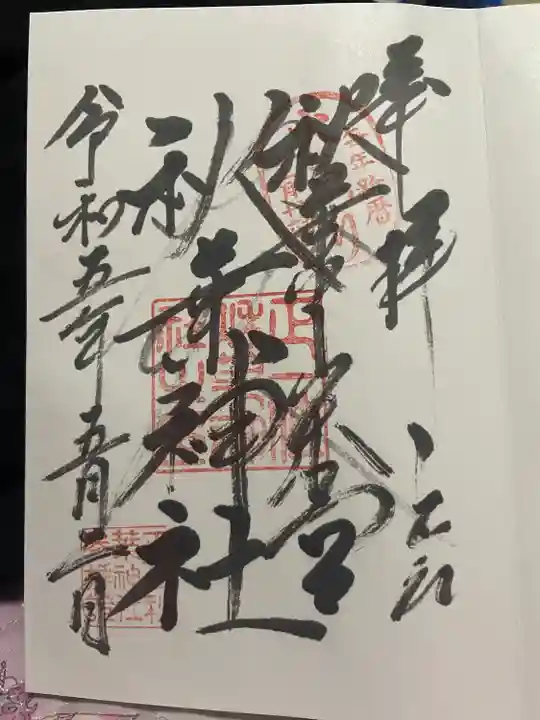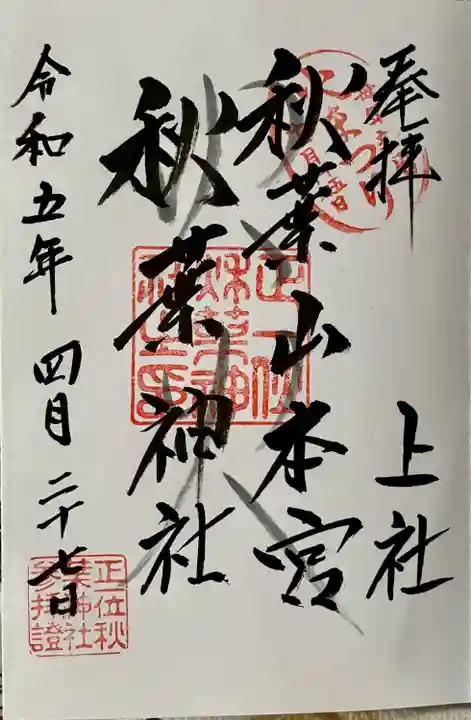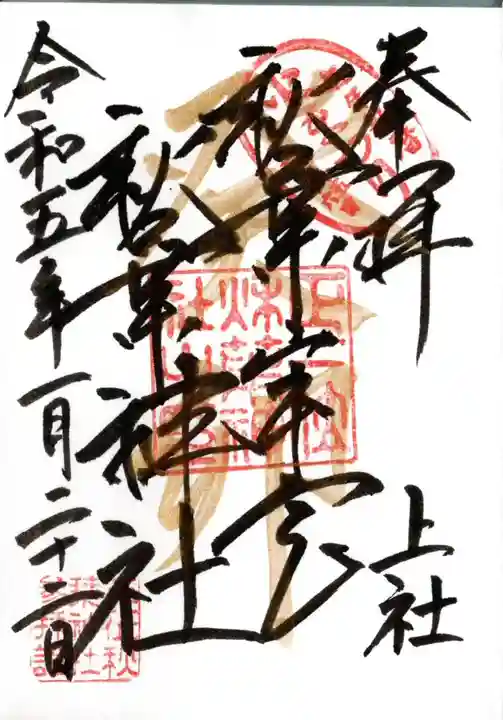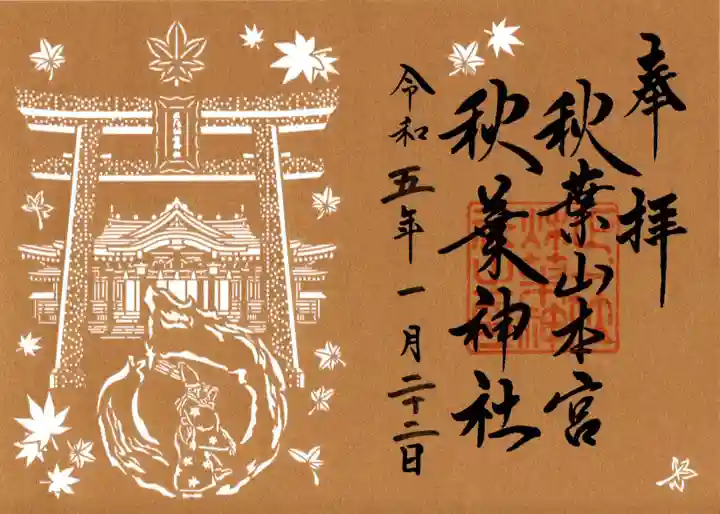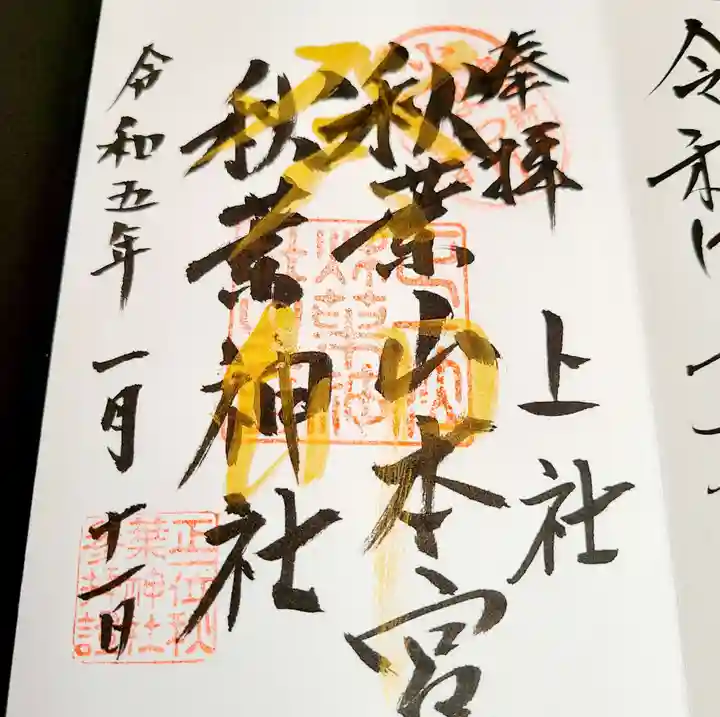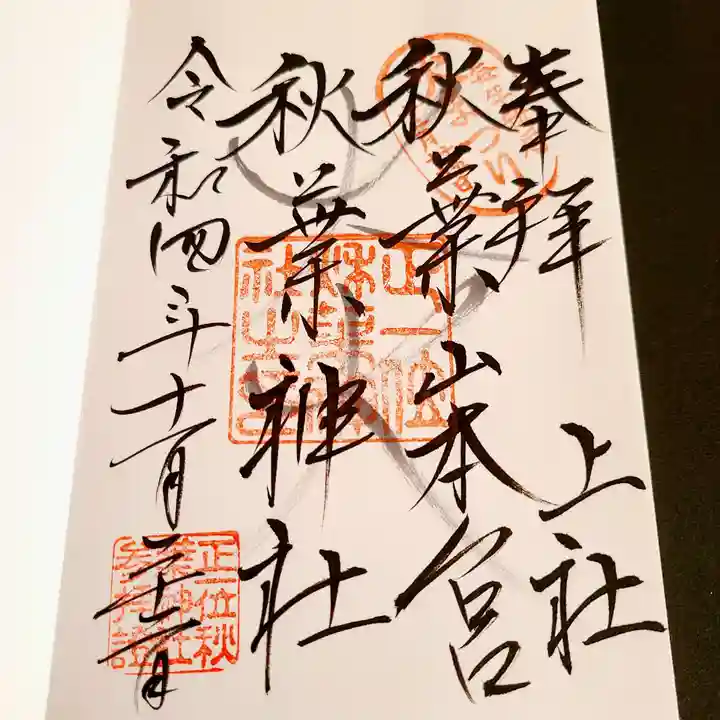あきはさんほんぐうあきはじんじゃかみしゃ
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方秋葉山本宮 秋葉神社 上社のお参りの記録一覧
2 / 5ページ26〜50件103件中
絞り込み
複数語は空白区切り
参拝期間
----年--月
〜----年--月
御朱印関連
フォロー中
自分
サポーター
検索する
絞り込み限定
投稿日降順
キーワード
参拝----年--月〜----年--月
御朱印
フォロー
自分
サポーター
検索

m
2024年02月18日(日)163投稿

奥の院好き
2024年02月05日(月)280投稿

angus
2025年11月02日(日)312投稿

STmasako
2023年12月11日(月)15投稿

すなっち
2023年11月12日(日)326投稿

なでしこ
2023年09月30日(土)103投稿

k0512
2023年08月26日(土)1691投稿

ゆりま
2023年04月27日(木)236投稿

神祇伯
2023年06月25日(日)1730投稿

つつうらうら
2023年02月05日(日)1191投稿

ナオ ユキオ
2023年01月18日(水)375投稿

ナオ ユキオ
2022年11月27日(日)375投稿

タンホイザ
2022年08月08日(月)3869投稿

じろー
2022年06月19日(日)19投稿
静岡県のおすすめ3選🎌
広告
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ