いしやまでら|東寺真言宗|石光山
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方石山寺の御由緒・歴史
| ご本尊 | 如意輪観音 | |
|---|---|---|
| 創建時代 | 天平十九年(747年) | |
| 開山・開基 | 良弁僧正 | |
| ご由緒 | 石山寺は、琵琶湖の南端近くに位置し、琵琶湖から唯一流れ出る瀬田川の右岸にある。本堂は国の天然記念物の珪灰石(「石山寺硅灰石」)という巨大な岩盤の上に建ち、これが寺名の由来ともなっている(石山寺珪灰石は日本の地質百選に選定)。
|
滋賀県のおすすめ2選🎌
歴史の写真一覧
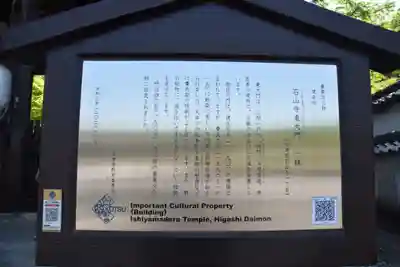
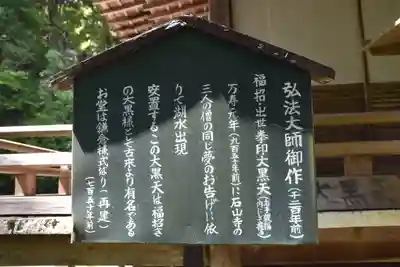
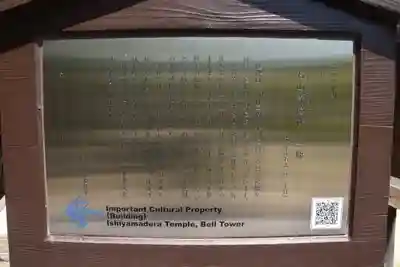
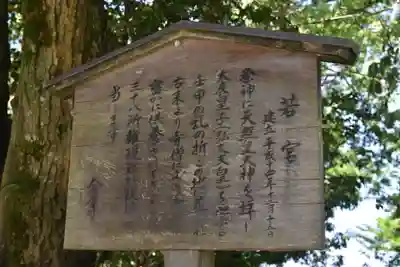

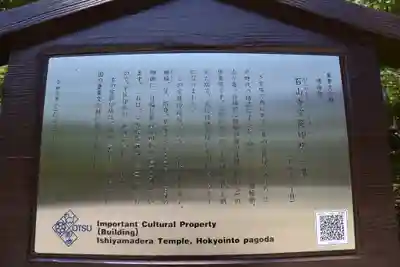
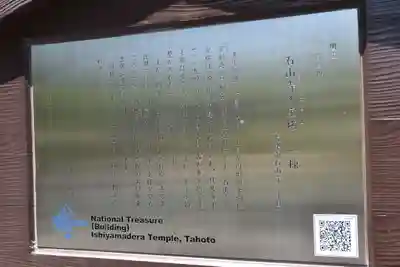

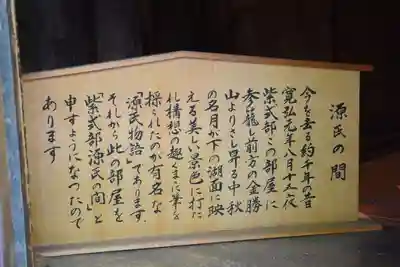
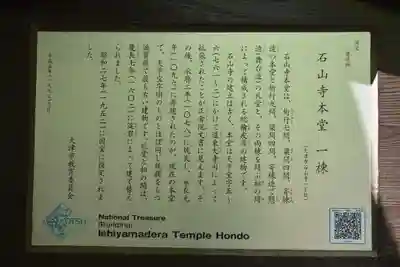
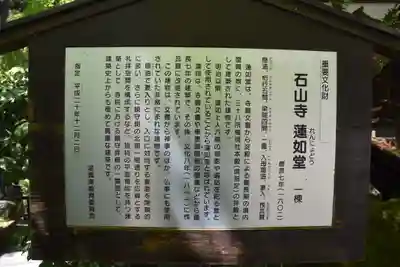
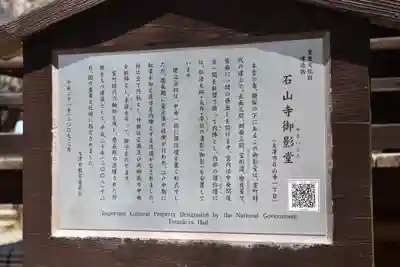
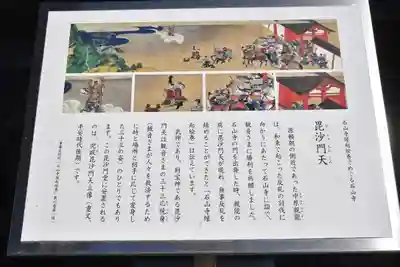
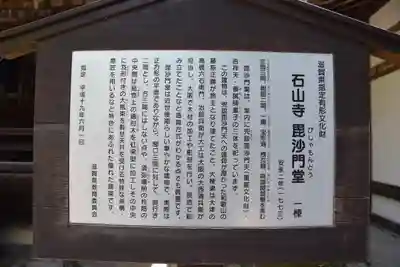
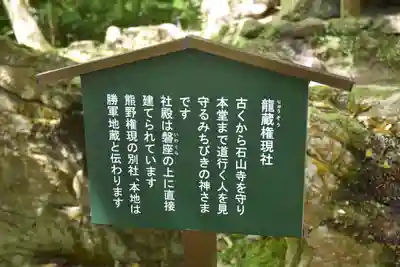
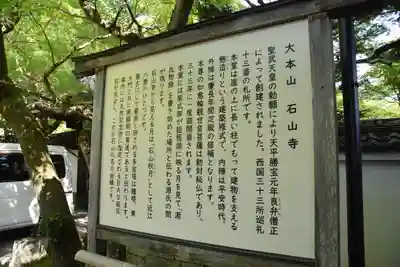
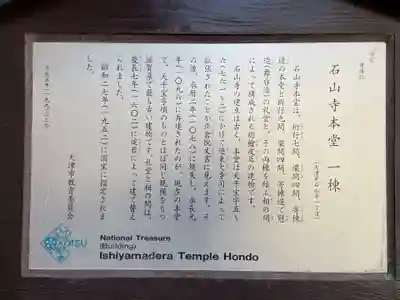
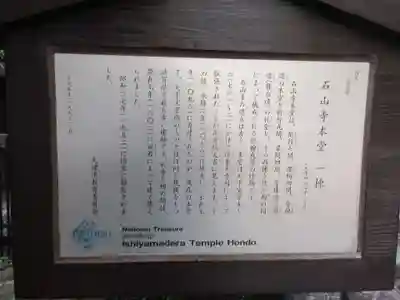


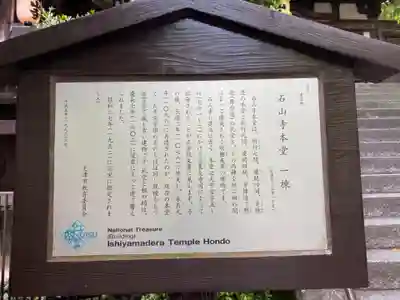
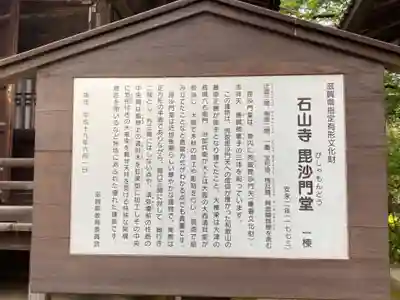

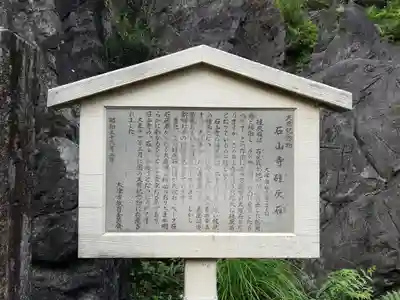
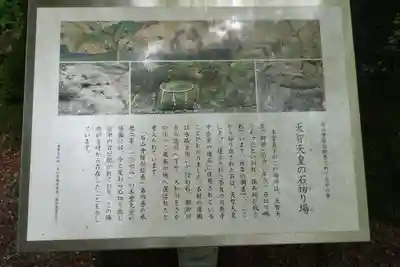
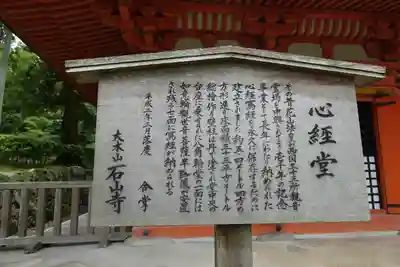
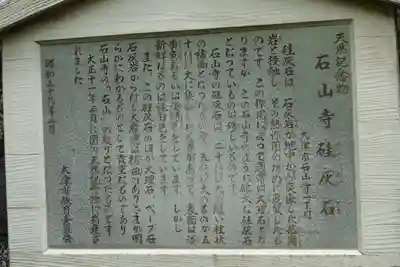
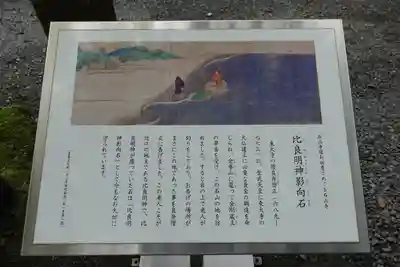
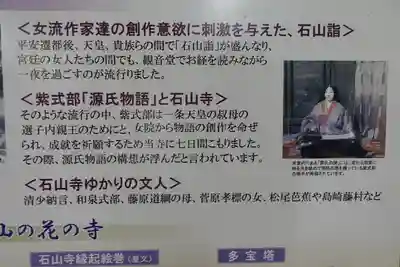
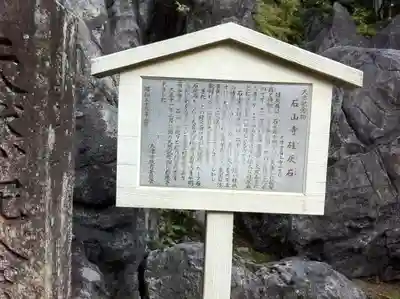
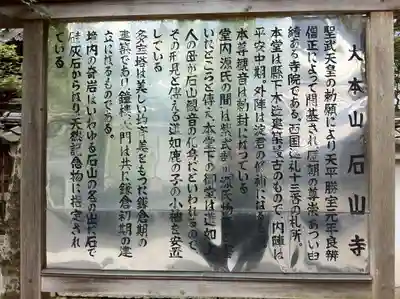
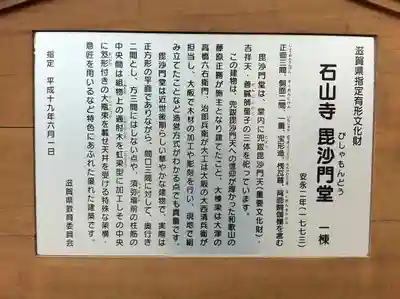
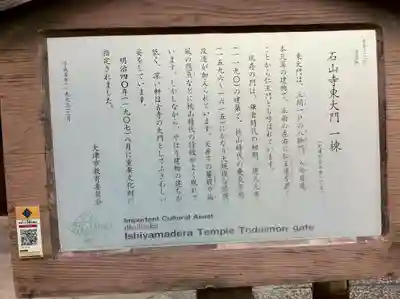
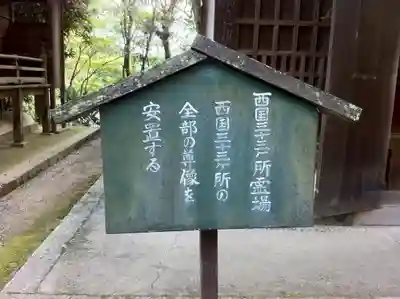
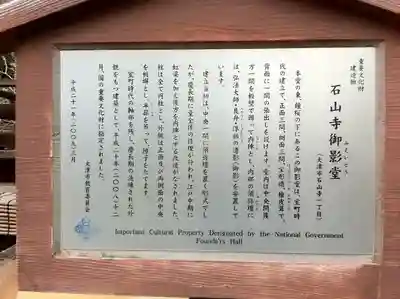
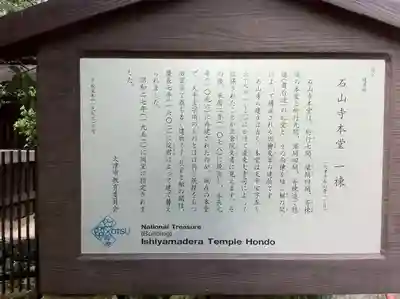

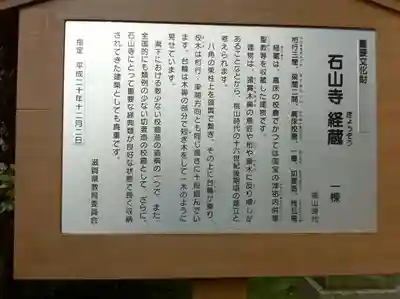
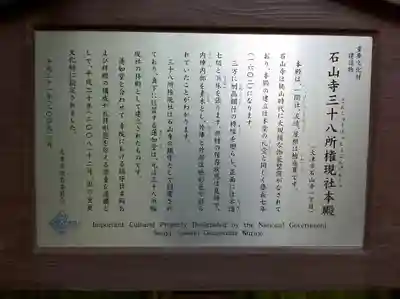
滋賀県のおすすめ2選🎌
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ

