みなみほっけじ(つぼさかでら)|真言宗|壺阪山
南法華寺(壷阪寺)奈良県 壺阪山駅
午前8時30分~午後5時まで
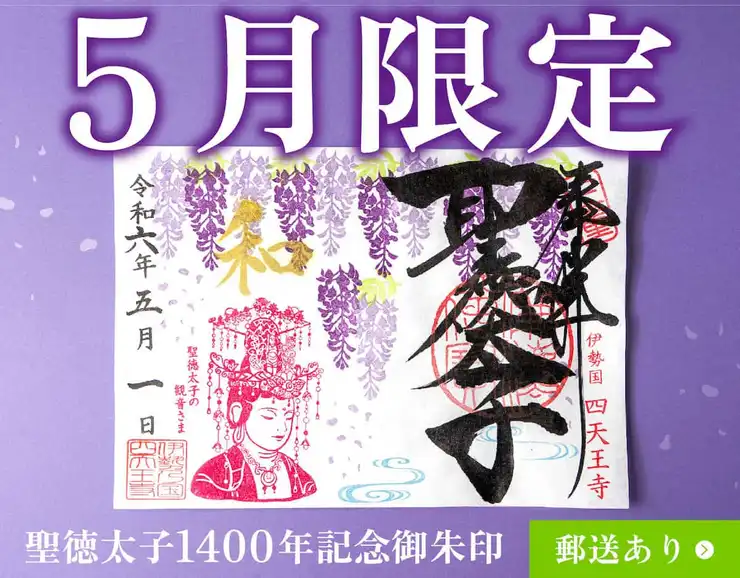
| 御朱印 | 通常いただける御朱印は、御本尊と御詠歌の2種類。また毎月18日に特別朱印を押印していだけます(奇数と偶数月で印が違います)。2022年3月31日まで左上に西国三十三所草創1300年記念でメガネに「慈眼」の文字が入った印をいただけます。 | ||
|---|---|---|---|
| 限定 | - | ||
| 御朱印帳 | |||
| 駐車場 | 第一駐車場 33台(大型4台・普通車30台)
|
【壺阪山(つぼさかやま)南法華寺(みなみほっけじ)】
本尊:十一面千手観世音菩薩
宗派:真言宗系単立
開基:弁基(べんき)
南法華寺は通称 壺阪寺で知られる。703(大宝3)年に元興寺の弁基上人により開かれたとされ、後に第44代 元正(げんしょう)天皇(在位:715-724)の祈願寺となった。京都の清水寺が北法華寺と呼ばれるのに対し当寺は南法華寺と呼ばれ、長谷寺とともに古くから観音霊場として栄えた。
本尊の十一面千手観世音菩薩は眼病封じの観音様として親しまれ、お里・沢市の夫婦愛をうたった人形浄瑠璃「壺坂霊験記」の舞台として有名。
西国三十三所観音霊場(第6番札所)で参拝。訪れた時は、散りはじめていましたが、それでも優しいお顔の桜大仏を拝見することができました。
【全景】
【山吹の咲く路】
【大講堂・受付所】
【大講堂・受付所】
【聖観音】
【仁王門】
仁王像は修理中で不在。
【寺号標】
【仁王門から上る石段】
【多宝塔】
【灌頂堂(かんじょうどう)】
【灌頂堂からみる大観音石像】
【夫婦観音】
【手水舎】
【手水舎の地蔵】
【十一面千手観音】
【壺阪大仏】
【壺阪大仏】
【壺阪大仏】
【壺阪大仏】
【大石堂】
【大石堂】
【壺阪大仏・大観音石像】
【多宝塔】
【慈眼堂】
【壺阪大仏】
【礼堂】
【本堂】
【礼堂内陣】
【本堂内陣】
【本堂内陣】
【三重塔】
【三重塔】
【めがね供養観音】
【お里観音六角堂】
【お里・沢市像】
【天竺門】
【大観音石像】
【大涅槃石像・大観音石像】
【西国三十三所観音霊場御納経帳】
【西国33奈良制覇編】
すっかり冬本番⛄の中、西国33箇所の奈良制覇してきました😁
2本立で投稿しますまずは壺阪寺さんからの岡寺さんです😌
めちゃめちゃ画像多いですが暇ならどうぞ😆
おまけの高取城跡もどうぞ🏯
もちろん入山料はいりますから💰
ガンダムよりちょびっとデカいですよ😁
流石デカ手です✋
お~いお茶🍵😅なぜ😅
めちゃめちゃえぇ顔して寝てます💤
立派でした😌
このショッピングモールの前が無料駐輪場です✌
この道を進んでくださいね🚶
おまけの高取城跡🏯
スゴい山道を上がってあとちょびっとです💦
本丸です😅
この道見てください😱
ん‼️アヒルちゃん👀なんで💦
ここからは岡寺さんです⛩️
もちろん入山料いりますよ💰
龍が出たみたいです🐲
かわいらしいですよ😆
岡寺さんも立派でした😌
これにて1部終わりです🙌
創建は寺蔵の『南法花寺古老伝』によると、大宝3年(703)年に元興寺の僧、弁基上人がこの山で修行していたところ、愛用の水晶の壺を坂の上の庵に納め、感得した観音像を刻んでまつったのが始まりといわれる。境内からは当時の藤原宮の時期の瓦が多数出土している。その後、元正天皇に奏じて御祈願寺となった。
平安期には、長谷寺とともに定額寺に列せられ(847年)、平安貴族達の参拝も盛んになり、ことに清少納言は「枕草子」のなかで「寺は壷坂、笠置、法輪・・・」と霊験の寺として、筆頭に挙げている。また、左大臣藤原道長が吉野参詣の途次に当寺に宿泊したという記録も残っている(1007年)。
この頃、子島寺の真興上人が壷阪寺の復興にあたり、真言宗子島法流(壷坂法流)の一大道場となり、三十三所の観音霊場信仰とともに、寺門は大いに栄えていった。
その後数度の火災にあうが、その度に山僧の合力により再建がなされてきた。
しかし、南北朝や戦国の動乱に巻き込まれ、当時庇護を受けていた越智氏の滅亡とともに壷阪寺も衰退していく。
一時は山内に三十六堂、六十余坊の大伽藍を配していたが、境内には三重塔と僅かな諸坊を残すだけとなった。
近世の壷阪寺は豊臣秀吉の弟秀長の家来本多利久が高取城主となり、本多氏とその後明治の廃藩置県まで続く藩主植村氏の庇護を受け復興していった。
明治の初め、盲目の夫沢市とその妻お里の夫婦の物語、人形浄瑠璃『壺坂霊験記』が初演され、歌舞伎、講談、浪曲となり壷阪寺の名は大きく世に広まっていった。(壺坂霊験記)
| 名称 | 南法華寺(壷阪寺) |
|---|---|
| 読み方 | みなみほっけじ(つぼさかでら) |
| 通称 | 壺阪寺 |
| 参拝時間 | 午前8時30分~午後5時まで |
| 参拝料 | 大人(18歳以上) 600円 小人(17歳以下) 100円 幼児(5歳以下) 無料 |
| トイレ | あり |
| 御朱印 | あり 通常いただける御朱印は、御本尊と御詠歌の2種類。また毎月18日に特別朱印を押印していだけます(奇数と偶数月で印が違います)。2022年3月31日まで左上に西国三十三所草創1300年記念でメガネに「慈眼」の文字が入った印をいただけます。 |
| 限定御朱印 | なし |
| 御朱印帳 | あり |
| 電話番号 | 0744-52-2016 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |
| ホームページ | http://www.tsubosaka1300.or.jp/index.html |
| おみくじ | あり |
| 絵馬 | あり |
| SNS |
| 神仏霊場巡拝の道 | |
|---|---|
| 西国三十三所霊場 |
| ご本尊 | 十一面千手千眼観世音菩薩 |
|---|---|
| 山号 | 壺阪山 |
| 宗旨・宗派 | 真言宗 |
| 創建時代 | 703年(大宝3年) |
| 開山・開基 | 弁基上人 |
| 文化財 | 礼堂・三重塔(重要文化財) |
| ご由緒 | 創建は寺蔵の『南法花寺古老伝』によると、大宝3年(703)年に元興寺の僧、弁基上人がこの山で修行していたところ、愛用の水晶の壺を坂の上の庵に納め、感得した観音像を刻んでまつったのが始まりといわれる。境内からは当時の藤原宮の時期の瓦が多数出土している。その後、元正天皇に奏じて御祈願寺となった。
|
| 体験 | 御朱印札所・七福神巡り |
| 概要 | 南法華寺(みなみほっけじ)は、奈良県高市郡高取町壺阪にある真言宗系単立の寺院。山号は壺阪山。本尊は十一面千手観世音菩薩。一般には壺阪寺(つぼさかでら)の通称で知られる。西国三十三所第6番札所。 本尊真言:おん ばざら たらま きりく そわか ご詠歌:岩をたて水をたたえて壺阪の 庭のいさごも浄土なるらん |
|---|---|
| 歴史 | 歴史[編集] 草創については不明な点が多いが、伝承によれば大宝3年(703年)に元興寺の弁基上人により開かれたとされる。後に元正天皇の祈願寺となった。 平安時代、京都の清水寺が北法華寺と呼ばれるのに対し当寺は南法華寺と呼ばれ、長谷寺とともに古くから観音霊場として栄えた。承和14年(847年)には長谷寺とともに定額寺に列せられている。貴族達の参拝も盛んであり、清少納言の『枕草子』には「寺は壺坂、笠置、法輪・・・」と霊験の寺の筆頭に挙げられている。また、寛弘4年(1007年)左大臣藤原道長が吉野参詣の途次に当寺に宿泊している。 往時は36堂60余坊もの堂舎があったが、嘉保3年(1096年)に...Wikipediaで続きを読む |
| 引用元情報 | 「南法華寺」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E5%8D%97%E6%B3%95%E8%8F%AF%E5%AF%BA&oldid=98807210 |
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。
ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ









































































44
0