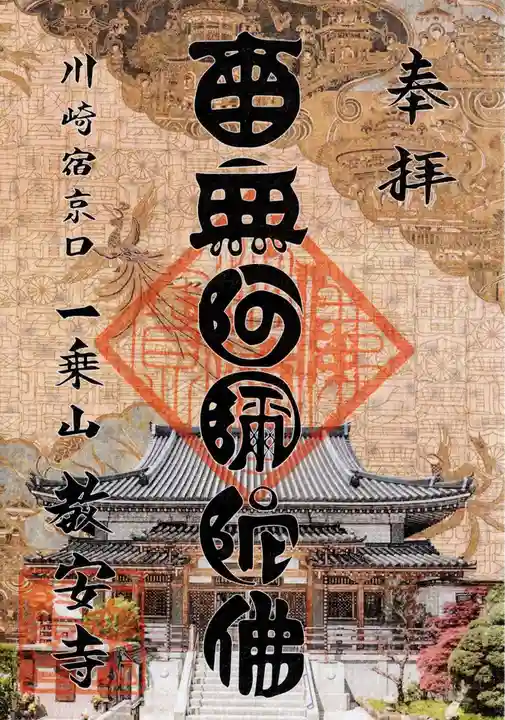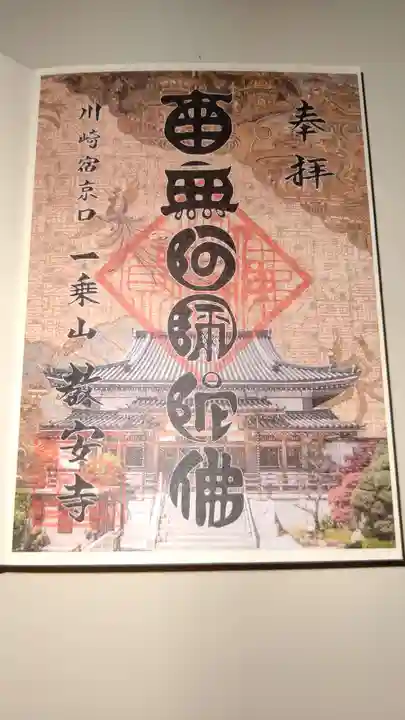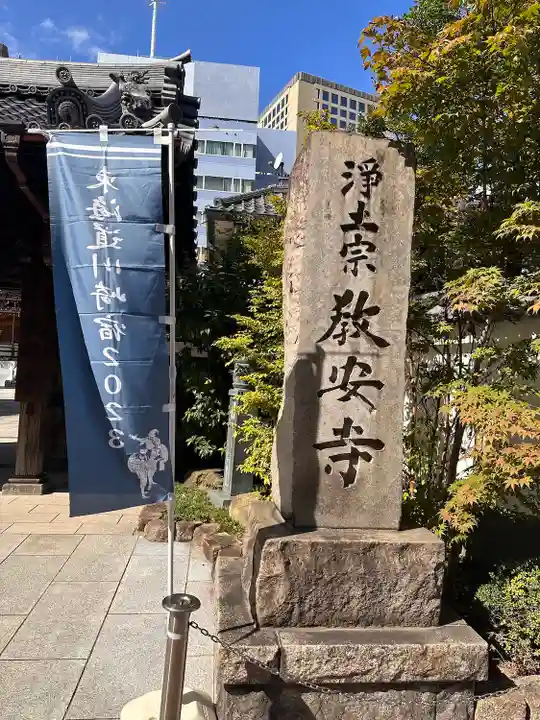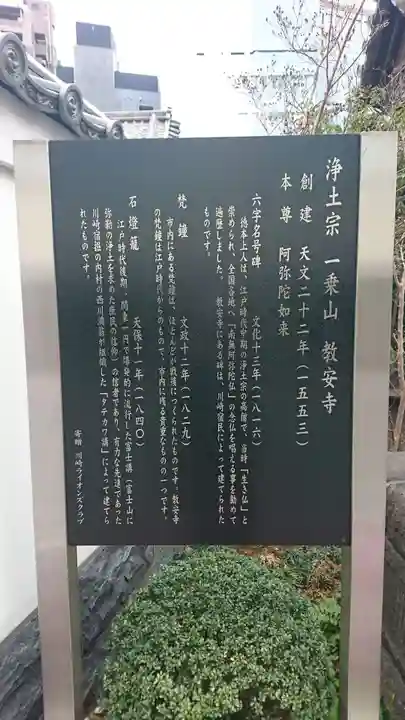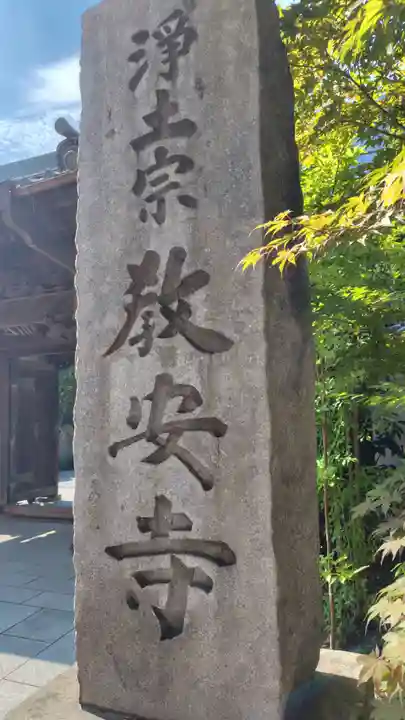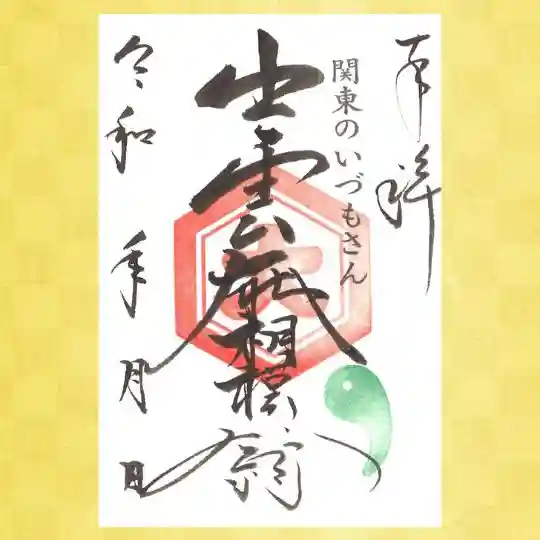きょうあんじ|浄土宗|一乗山
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方教安寺のお参りの記録一覧
1〜13件13件中
絞り込み
複数語は空白区切り
参拝期間
----年--月
〜----年--月
御朱印関連
フォロー中
自分
サポーター
検索する
絞り込み限定
投稿日降順
キーワード
参拝----年--月〜----年--月
御朱印
フォロー
自分
サポーター
検索

てえすけ
2025年09月03日(水)1574投稿

竜王
2024年01月21日(日)2037投稿
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ