いちじょうじ|天台宗|法華山
一乗寺兵庫県 播磨下里駅
8:00~17:00
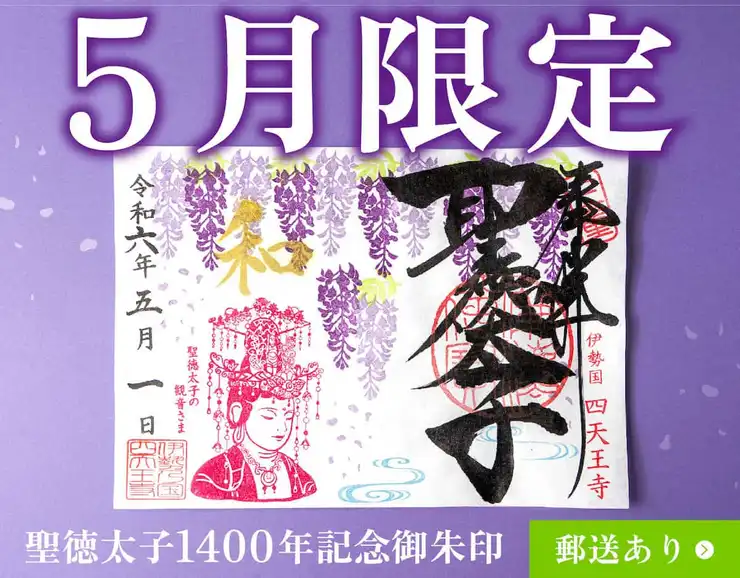
| 御朱印 | |||
|---|---|---|---|
| 限定 | - | ||
| 御朱印帳 | - | ||
| 駐車場 | 有料駐車場あり |
法華山 一乗寺
~加西西国・伝説の空鉢仙人~
山号 法華山
宗派 天台宗
御本尊 聖観世音菩薩
創建年 白雉元年(650年)
開山 法道仙人
札所等
西国三十三所第26番
播磨西国三十三箇所第33番
播磨天台六山
神仏霊場巡拝の道第77番(兵庫第12番)
御詠歌
春は花 夏は橘 秋は菊
いつも妙なる
法(のり)の華山(はなやま)
御詠歌 播磨西国
参れただ ここぞ御法(みのり)の 花の山
仏になると 一乗寺かな
本西国・加西西国では第二十六番、播磨西国第三十三番 最後の札所「一乗寺」には縁起となっている不思議な伝説が残っています。
インドから紫雲に乗ってやって来た法道仙人は空腹になると神通力で鉢を飛ばし、お供物を得ていたことから「空鉢(からはち)仙人」と呼ばれていました。
噂を聞いた孝徳天皇は仙人に病気平癒を依頼したところ、病気はすぐに治ったそうです。仙人を慕った天皇は法華山に金堂を建立し、鎮護国家の道場としました。
その後、法道仙人は、播磨各地に多くの寺を開基されました。
~長い階段を上りながら眺めるどっしりとした三重塔の調和美~
一つ目の階段を上がると「常行堂」。二つ目の石段を上がると県下最古の「三重塔」がどっしりと佇んでいます。
国宝の三重塔は平安時代後期を代表する和様建築の塔であり、日本では屈指の古塔です。
塔軒下の複雑な組木に目を奪われながら、三つ目の石段を上がると御本堂に到着します。薄暗い堂内へ入るとまず、目につくのが天井の模様。伺うと、参拝した証しとして打ち付けられた巡礼札だそうで、まるで花が咲いたよう。季節柄、青もみじの花(種)を思い浮かべました。
参拝を済ませ、回廊へ出ると山並みと木々、三重塔が織り成す壮大な眺めが広がっています。
回廊の床に正座して、しばし非日常の世界へ。塔の先端にそびえる水煙が空高くくっきりと浮かんでいました。
法華山は古来八葉の蓮華の山に喩えられ、
桜・新緑・紅葉が美しい都塵を絶した浄域です。
入園料 500円
(宝物館の拝観には、別途500円必要)
※宝物館の予約については、2週間前までに連絡要
営業時間 8:00~17:00
定休日 なし
加西市坂本町821-17
TEL 0790-48-2006
~・~・~・~
今回は加西西国でお参りさせて頂きました。
少しずつ播磨の霊場を巡礼しています。
加西西国は事務局がなく、御詠歌について御朱印書き手先生も熱心にお調べ下さいましたが、不明でした。
色々な霊場の事務局(お寺さま)の有り難さを痛感しました。
ひょうご五国(摂津・播磨・但馬・丹波・淡路)。
日本海、瀬戸内海、大阪湾、紀伊水道、播磨灘。改めて歴史の深さにワクワクしています。
#ひょうご五国
#摂津
#播磨
#但馬
#丹波
#淡路
#法道仙人
#伝説
#神通力
#空鉢仙人
#八葉蓮華
#孝徳天皇
#鎮護国家の道場
#地蔵菩薩
#法華経
#西国三十三所第26番
#加西西国第26番
#播磨西国三十三箇所第33番
#播磨天台六山
#神仏霊場巡拝の道第77番(兵庫第12番)
#天井の巡礼札
#賽の河原の石積み
#御朱印
#加西市
#かさい観光ナビ
#兵庫県
#love_hyogo
空高く
加西西国第二十六番御朱印
西国第二十六番御朱印(軸)
播磨西国第三十三番御朱印
神仏霊場巡拝の道 第77番(兵庫第12番)
常行堂
常行堂左の石仏様
いつも優しく見守っていて下さる様です
三重塔下のツツジも優しく
ゆらゆら灯 自分の中で消えずの法灯を思う瞬間です
「明らく後の 仏の御世までも 光つたへよ 法のともしび 」
屋根瓦まで重厚な御本堂
護法堂へ
御本堂に打ち付けられた巡礼札のように感じました
奥の院へ
賽の河原へ
放生池へ
法華山 隣聖院
山号 法華山
宗派 天台宗
御本尊 阿弥陀如来
法華山一乗寺の塔頭寺院です。
御本尊は聖観世音菩薩ですが、隣聖院内仏には阿弥陀如来を御持仏としています。
表門には三木城派で豊臣秀吉の関西制覇に依り落城した志方城の取手門を移転しましたので四百余年の歳月を感じる門です。
天平三年に創立。現在の庫裏は昭和六十年改築。可能な限り、旧建物に復しました。
又隣聖院境内にありました粟嶋堂は、法華山発展の為に法華山々内に県道を誘致する気運になった時、立替地として関係者全員の推挙を受け、当時の地主山下氏の御協力を得、現在地に昭和三十年地鎮新築移転今日に至っています。
特に難病平癒の拠所として親しまれています。又粟嶋堂境内地に水子供養を願われる人たちに奉納された水子地蔵尊は群をなして、代受苦の仏と云われる此の尊に多くの人の心の苦しみがやわらげられています。
尚お堂の前の 第253世山田恵諦座主猊下御染筆の碑は ひときわ大きくお地蔵様のお慈悲をお示し下さっています。
歓喜院(かんぎいん)
花橘に蕾が💚
はじめまして🌸耳ちゃん かわいすぐるにゃん 🐾
この幹 枝の逆くの字の根本に、御本尊の聖観世音菩薩さまがいらっしゃる様子に見えて毎回拝んでしまいます
天台宗 法華山 一乗寺
西国三十三所観音霊場 第26番札所
播磨西国三十三箇所観音霊場 第33番札所
今回2年ぶりの参拝。
前回の参拝時には受付のところで2匹の猫ちゃんがお出迎えしてくれました。
今回もいるかな?と思ったらそのうちの1匹が前回同様にお出迎えしてくれました。
前回は私の肩の上にまで乗ってくるほど人懐っこくて、とても癒されたのをよく覚えています。
法道仙人が白雉元年(650年)に開山したとされており、日本最古とされる承安元年(1171年)建立の三重塔(国宝)や、国宝「聖徳太子及び天台高僧画像」なども所蔵されています。
御本尊 聖観世音菩薩
ご詠歌
春は花 夏は橘 秋は菊 いつも妙なる 法の花山
次は桜か橘が咲き誇る時期にお参りしたいと思います。
朝から参拝者をお出迎えし、帰るときも見送りをしてくれます。
常行堂(阿弥陀堂)
三重塔
三重塔の前を過ぎて階段を登ると本堂です
本堂前から見た三重塔
更に本堂内から見た三重塔
本堂 扁額
鐘楼
放生池と弁天
太子堂
一乗寺の開基とされる法道仙人は、天竺(インド)から紫の雲に乗って飛来したとされる伝説的人物である。『元亨釈書』等の記述によれば、法道はインドに住んでいたが、紫の雲に乗って中国、百済を経て日本へ飛来、播州賀茂郡(兵庫県加西市)に八葉蓮華(8枚の花弁をもつハスの花)の形をした霊山を見出したので、そこへ降り立ち、法華経の霊山という意味で「法華山」と号したという。法道は神通力で鉢を飛ばし、米などの供物を得ていたため、「空鉢仙人」と呼ばれていた。法道の評判は都へも広まり、白雉元年(650年)、時の帝である孝徳天皇の勅命により法道に建てさせたのが一乗寺であるという。
法道仙人開基伝承をもつ寺院は兵庫県東部地域に集中しており、「インドから紫雲に乗って飛来」云々の真偽は別としても、こうした伝承の元になり、地域の信仰の中心となった人物が実在した可能性は否定できない。一乗寺には7世紀~8世紀にさかのぼる金銅仏6躯が存在し(うち3躯は重要文化財)、付近には奈良時代にさかのぼる廃寺跡、石仏などが存在することからも、この地域一帯が早くから仏教文化の栄えた地であることは確かである。[1]
創建当時の一乗寺は現在地のやや北に位置する笠松山にあったと推定されている。笠松山の山麓には古法華(ふるぼっけ)石仏と称される奈良時代の三尊石仏(重要文化財)があり、「古法華」とは「法華山一乗寺の旧地」の意味と思われる。現存する一乗寺三重塔は平安時代末期の承安元年(1171年)の建立であるところから、その年までには現在地において伽藍が整備されていたと思われるが、正確な移転時期は不明である。
一乗寺は中世、近世には何度かの火災に遭っているが、平安時代の三重塔をはじめとする古建築がよく保存されている。本堂は姫路藩主本多忠政の寄進により、寛永5年(1628年)に建てられたものである。
| 名称 | 一乗寺 |
|---|---|
| 読み方 | いちじょうじ |
| 参拝時間 | 8:00~17:00 |
| 参拝料 | 500円(宝物館入館料は別途) |
| 御朱印 | あり |
| 限定御朱印 | なし |
| 電話番号 | 0790-48-2006 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |
| お守り | あり |
| 絵馬 | あり |
| 播磨西国三十三箇所 第33番 | 御本尊:聖観音 御詠歌: 参れただ ここぞ御法の 花の山 仏になると 一乗寺かな |
|---|---|
| 神仏霊場巡拝の道 | |
| 西国三十三所霊場 |
| ご本尊 | 聖観世音菩薩 |
|---|---|
| 山号 | 法華山 |
| 宗旨・宗派 | 天台宗 |
| 創建時代 | 白雉元年(650) |
| 開山・開基 | 法道仙人 |
| 文化財 | 三重塔、聖徳太子及天台高僧像十幅(国宝) |
| ご由緒 | 一乗寺の開基とされる法道仙人は、天竺(インド)から紫の雲に乗って飛来したとされる伝説的人物である。『元亨釈書』等の記述によれば、法道はインドに住んでいたが、紫の雲に乗って中国、百済を経て日本へ飛来、播州賀茂郡(兵庫県加西市)に八葉蓮華(8枚の花弁をもつハスの花)の形をした霊山を見出したので、そこへ降り立ち、法華経の霊山という意味で「法華山」と号したという。法道は神通力で鉢を飛ばし、米などの供物を得ていたため、「空鉢仙人」と呼ばれていた。法道の評判は都へも広まり、白雉元年(650年)、時の帝である孝徳天皇の勅命により法道に建てさせたのが一乗寺であるという。
|
| 体験 | 御朱印博物館国宝重要文化財札所・七福神巡り |
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。
ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ


















































































12
0