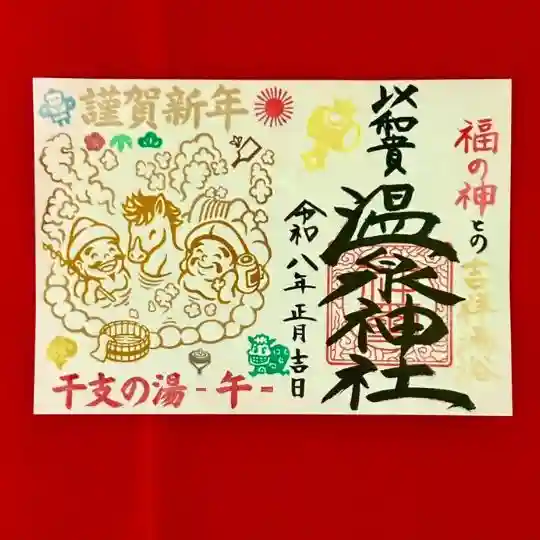こでらやまかんのんどう
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ
写真
小寺山観音堂の情報
| 住所 | 福島県いわき市四倉町西4丁目4−8 |
|---|---|
| 行き方 |
小寺山観音堂の基本情報
| 名称 | 小寺山観音堂 |
|---|---|
| 読み方 | こでらやまかんのんどう |
| 御朱印 | あり |
| 限定御朱印 | なし |
詳細情報
| ご本尊 | 正観音 |
|---|---|
| 宗旨・宗派 | - |
| ご由緒 | 【 現在の寺町の状況 】
|
| 体験 |
ホトカミのデータについて
ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。
ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。
周辺エリア
小寺山観音堂に関連する記事
おすすめのホトカミ記事
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ