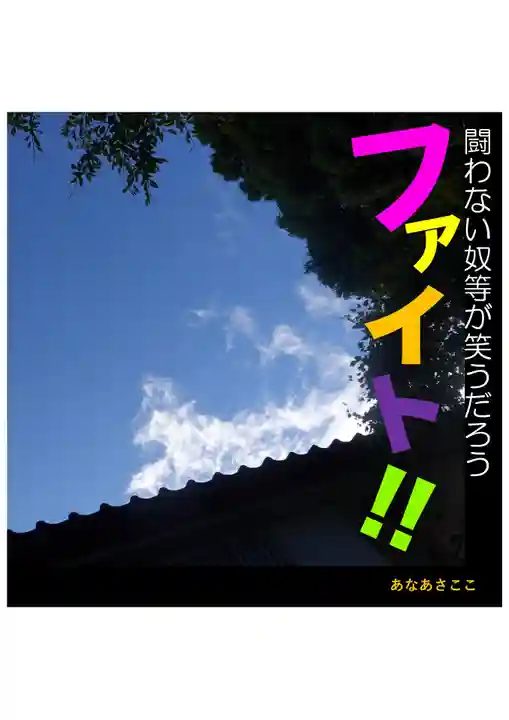耕田院の日常(83回目)|山形県羽前大山駅
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方投稿日:2022年10月21日(金) 21時21分02秒
「あたし中卒やからね 仕事をもらわれへんのやと書いた」で始まる中島みゆきさんの「ファイト」である。
暗い水の流れに打たれながら 魚たちのぼってゆく
光ってるのは傷ついてはがれかけた鱗が揺れるから
いっそ水の流れに身を任せ 流れ落ちてしまえば楽なのにね
やせこけて そんなにやせこけて魚たちのぼってゆく
ファイト! 闘う君の唄を
闘わない奴等が笑うだろう
ファイト! 冷たい水の中を
ふるえながらのぼってゆけ
◆もうすぐ鮭が遡上する。鮭は、海からふるさとの川に戻ってきて産卵の場所を探す。川を上っていくのだ。その姿は、ボロボロだ。力を振り絞って命を燃やす。
◆ところが、この鮭の遡上2020年には、最盛期は22%の生まれた川に戻る回帰率が1.6%にまで低下しているという。つまり、1/20くらいまで減少しているのだ。
◆昨年の鮭漁は、歴史的不漁だった。青森県内沿岸の漁獲量は、過去最低だった一昨年の3分の1にとどまる。鮭のほかにも、サンマやスルメイカなど多くの水産物は近年、全国的に不漁が続く。
◆鮭の身は、川を遡上すると一変で味が落ちてしまうので、価値がなくなる。しかし、メスの腹にあるハラコ(イクラ)は違う。そのイクラをとり、「栽培漁業」が行われている。
◆小学校5年生の社会で漁業の学習をする「栽培漁業」とは、卵から稚魚になるまでの一番弱い時期を人の手で守り、その後、自然の海に稚魚を放流し、成長したものをとる漁業だ。 養殖漁業は、一般的に、稚魚を生け簀(いけす)などで飼育し、食べられる大きさになったら出荷するので、自然の海に放流することはない。
◆鮭の放流は何度もしたことがある。秋に鮭が遡上する川に鮭を誘導する路を作る。檻が設置してあり、そこにかかった鮭の腹を切り裂きハラコを取り出す。それにオスの精子をかけ、受精させ、稚魚に育てる。そして冬を越させる。
◆まだ、卵からかえったばかりの鮭の稚魚は、はじめ腹にイクラを抱え、かわいらしい様子であるのだが、春が近づいてくると水槽の中で精悍で獰猛な顔だちになってくる。
◆三月になると稚魚を放流する。稚魚は海に向かっていく。中島みゆきさんの「ファイト! 」の通りだ。
ああ 小魚たちの群れきらきらと 海の中の国境を越えてゆく
◆しかし、今年も不漁だという。その原因は「地球温暖化」であるとされているが、気になる記事があった。
「断言まではできないのですが、自然産卵のサケの稚魚より、採卵された稚魚の方が生命力が弱いと仮定します。そこで自然産卵するサケの量が減ってしまった。つまり採卵用も含めて、サケの獲り過ぎで、自然産卵のサケの回帰数が減り、全体でサケの水揚げ量が激減していることが、減った主因ではないかと推測できないでしょうか?」
(魚が消えていく本当の理由https://suisanshigen.com/2020/01/03/article12/)
◆稚魚がオホーツク海にたどり着けるかどうかが最大のポイントなのだ。そのためには、環境変化にも生き残れる活きのいい稚魚でなければならないのだ。
◆雄と雌がペアを組み、産卵床を作成する。産卵床の直径は体長の約2~3倍もあるという。その産卵床を掘るのは、ボロボロの雌の役目だ。全て自然の摂理に任せた子孫を残すための最後の仕事だ。厳粛な命の引き継ぎの儀式にも見える。
◆やがて命を引き継いだ稚魚は厳しい冬を懸命に生き抜く。
◆十分研究調査され、検証した考えではないかもしれないが、良い条件で、守られて育った稚魚と自然の中で逞しく冬を越した稚魚では当然差はあるだろうとの予想は腑に落ちる
暗い水の流れに打たれながら 魚たちのぼってゆく
光ってるのは傷ついてはがれかけた鱗が揺れるから
いっそ水の流れに身を任せ 流れ落ちてしまえば楽なのにね
やせこけて そんなにやせこけて魚たちのぼってゆく
ファイト! 闘う君の唄を
闘わない奴等が笑うだろう
ファイト! 冷たい水の中を
ふるえながらのぼってゆけ
◆もうすぐ鮭が遡上する。鮭は、海からふるさとの川に戻ってきて産卵の場所を探す。川を上っていくのだ。その姿は、ボロボロだ。力を振り絞って命を燃やす。
◆ところが、この鮭の遡上2020年には、最盛期は22%の生まれた川に戻る回帰率が1.6%にまで低下しているという。つまり、1/20くらいまで減少しているのだ。
◆昨年の鮭漁は、歴史的不漁だった。青森県内沿岸の漁獲量は、過去最低だった一昨年の3分の1にとどまる。鮭のほかにも、サンマやスルメイカなど多くの水産物は近年、全国的に不漁が続く。
◆鮭の身は、川を遡上すると一変で味が落ちてしまうので、価値がなくなる。しかし、メスの腹にあるハラコ(イクラ)は違う。そのイクラをとり、「栽培漁業」が行われている。
◆小学校5年生の社会で漁業の学習をする「栽培漁業」とは、卵から稚魚になるまでの一番弱い時期を人の手で守り、その後、自然の海に稚魚を放流し、成長したものをとる漁業だ。 養殖漁業は、一般的に、稚魚を生け簀(いけす)などで飼育し、食べられる大きさになったら出荷するので、自然の海に放流することはない。
◆鮭の放流は何度もしたことがある。秋に鮭が遡上する川に鮭を誘導する路を作る。檻が設置してあり、そこにかかった鮭の腹を切り裂きハラコを取り出す。それにオスの精子をかけ、受精させ、稚魚に育てる。そして冬を越させる。
◆まだ、卵からかえったばかりの鮭の稚魚は、はじめ腹にイクラを抱え、かわいらしい様子であるのだが、春が近づいてくると水槽の中で精悍で獰猛な顔だちになってくる。
◆三月になると稚魚を放流する。稚魚は海に向かっていく。中島みゆきさんの「ファイト! 」の通りだ。
ああ 小魚たちの群れきらきらと 海の中の国境を越えてゆく
◆しかし、今年も不漁だという。その原因は「地球温暖化」であるとされているが、気になる記事があった。
「断言まではできないのですが、自然産卵のサケの稚魚より、採卵された稚魚の方が生命力が弱いと仮定します。そこで自然産卵するサケの量が減ってしまった。つまり採卵用も含めて、サケの獲り過ぎで、自然産卵のサケの回帰数が減り、全体でサケの水揚げ量が激減していることが、減った主因ではないかと推測できないでしょうか?」
(魚が消えていく本当の理由https://suisanshigen.com/2020/01/03/article12/)
◆稚魚がオホーツク海にたどり着けるかどうかが最大のポイントなのだ。そのためには、環境変化にも生き残れる活きのいい稚魚でなければならないのだ。
◆雄と雌がペアを組み、産卵床を作成する。産卵床の直径は体長の約2~3倍もあるという。その産卵床を掘るのは、ボロボロの雌の役目だ。全て自然の摂理に任せた子孫を残すための最後の仕事だ。厳粛な命の引き継ぎの儀式にも見える。
◆やがて命を引き継いだ稚魚は厳しい冬を懸命に生き抜く。
◆十分研究調査され、検証した考えではないかもしれないが、良い条件で、守られて育った稚魚と自然の中で逞しく冬を越した稚魚では当然差はあるだろうとの予想は腑に落ちる
すてき
ホトカミ見ました! で広がるご縁
ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。
住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、情報を発信しようという気持ちになりますし、
「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。