ありとおしじんじゃ
あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

| 御朱印 | |||
|---|---|---|---|
| 限定 | - | ||
| 御朱印帳 | - | ||
| 駐車場 | あり(参拝者無料) |
和歌山県のおすすめ🌸
おすすめの投稿

紀伊田辺駅近くの蟻通神社にも初参拝。
御祭神の天児屋根命は、知恵を働かされて国難を打開された故事(蟻通説話)から、「日本第一知恵の神」と称えられているそうです。そして、紀州田辺の「地主神」としても崇敬されているとのこと。






田辺市総鎮守として崇敬されている神社です。同名の神社が泉佐野市とかつらぎ町にありますが、本宮は泉佐野市だと思われます。その社名の由来から知恵の神様として知られており、私も今年の新たな知恵を授かりに行きました。

《一の鳥居》
駅前の大通りから少し内側に入ったところに入り口があります。

《神輿》
なんか古そうですね。

《手水舎》
柄杓が用意されていました。

《由緒書き》
👁チェックポイント‼️
蟻通はこちらに書かれているように、外国からの使者から日本の神々に出された課題の解決策を由来としており、この若い神様の発想を由来にして知恵の神様と言われています。
また、この若い神様がどなたなのかが決まっていないため、同名の神社でも大国主神、思兼命、天児屋命さまだったりとバラバラです。

《御神木のお社》
蟻通の由来とは別にこの神社の御神木には火災があったときに水を振り撒いて鎮火したと言う言い伝えがあります。

《拝殿》🙏
お酒を奉納したら職員さんのご厚意で昇段参拝させていただけました✨

《本殿》
春日造ですね。

《末社・恵比寿社、大黒天社》

《末社・弁天社》
隣の末社との間を縫うように鎮座しています。

《末社・稲荷社》
境内の角に鎮座しています。いつもお世話になって(🤛

蟻通むかしのことです。
ここ紀州田辺に外国の使者がやってきました。
その使者は
『今から出す問題を解いてみよ もし解けなければ日本国を属国にしてしまう』
といいました。そして、持ってきた法螺貝を出して、その貝に一本の糸を通すことを命じました。
日本の神がみは、この難問にたいへん頭を痛めました。
その時、ひとりの若い神様が前に進み出て『私が法螺貝にその糸をその糸を通してみせましょう」といって貝の口からどんどん蜜を流し込みました。
蜜は、貝の中の複雑な穴を通り抜けて貝尻の穴へと流れ出しました。そして、この若い神様は蟻を一匹捕らえて糸で結び貝の穴から追い込みました。
蟻は甘い蜜を追って、複雑な貝の穴を苦もなく通り抜けました。蟻の体には糸が結ばれていますから法螺貝には完全に糸が通ったのです。
これを見た外国の使者は『日の本の国はやはり神国である』と恐れその知恵に感服して逃げ帰りました。
日本の神がみは、たいそう喜んで『我国にこれほどの賢い神があるのを知らなかった』といって、その若い神様の知恵をほめました。そして、蟻によって貝に糸を通したことにより蟻通しの神と申し上げるようになりました
看板より








歴史
はるか昔のことです。外国がわが国を攻めようとして、試みに七曲がりに曲がりくねった玉(法螺貝)を送ってよこし、その玉に糸を通してみよと難題を出してきました。
日本の神々はこの難題に頭を痛めましたが、あるひとりの神さまが進み出て「私が通してみせましょう」といいました。その神さまは一匹の蟻(アリ)の腰に糸を結ぶと、貝の口の一方に蜜をぬり、もう一方の口から蟻を入れました。すると、蟻がどんどん進んで難なく貝に糸を通すことができました。これを知った外国は、日本はやはり神国であると恐れて、攻めるのをやめたといいます。
このことから、わが国の危機を救ったこのお宮の神さまを、「日本第一知恵の神」「蟻通しの大神さま」などとお呼びするようになりました。
| 名称 | 蟻通神社 |
|---|---|
| 読み方 | ありとおしじんじゃ |
| 通称 | 蟻通宮、御霊さん |
| 参拝にかかる時間 | 15分 |
| 参拝料 | なし |
| トイレ | あり |
| 御朱印 | あり |
| 限定御朱印 | なし |
| 電話番号 | 0739245072 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |
| SNS |
詳細情報
| ご祭神 | 天児屋根命(蟻通大神) |
|---|---|
| 創建時代 | 天平神護元年(766年) |
| 本殿 | 春日造 |
| 文化財 | 神輿(元和元年) |
| ご由緒 | はるか昔のことです。外国がわが国を攻めようとして、試みに七曲がりに曲がりくねった玉(法螺貝)を送ってよこし、その玉に糸を通してみよと難題を出してきました。
|
| 体験 | 祈祷おみくじお祓いお宮参り結婚式七五三御朱印お守り祭り伝説 |
和歌山県のおすすめ🌸
蟻通神社に関連する記事
おすすめのホトカミ記事
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ






















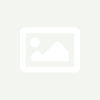




5
0