じげんじ|真言宗智山派|喜楽山
あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

| 御朱印 | |||
|---|---|---|---|
| 限定 | - | ||
| 御朱印帳 | - | ||
| 駐車場 | あり |
東京都のおすすめ2選🌸
| 名称 | 慈眼寺 |
|---|---|
| 読み方 | じげんじ |
| 御朱印 | あり |
| 限定御朱印 | なし |
| 電話番号 | 03-3700-0212 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |
| ホームページ | https://www.ans.co.jp/u/jigenji/ |
巡礼の詳細情報
| 玉川八十八ヶ所霊場 第37番 | 御本尊:大日如来 |
|---|
詳細情報
| ご本尊 | 大日如来 |
|---|---|
| 山号 | 喜楽山 |
| 院号 | 教令院 |
| 宗旨・宗派 | 真言宗智山派 |
| 創建時代 | 1306年 |
| 開山・開基 | 開山 法印定音/開基 長崎四郎左衛門 |
| ご由緒 | 新義真言宗で神奈川県小杉村西明寺の末寺で、京都の醍醐寺派に属する。
|
| 体験 | 御朱印札所・七福神巡り |
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ

































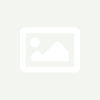





4
0