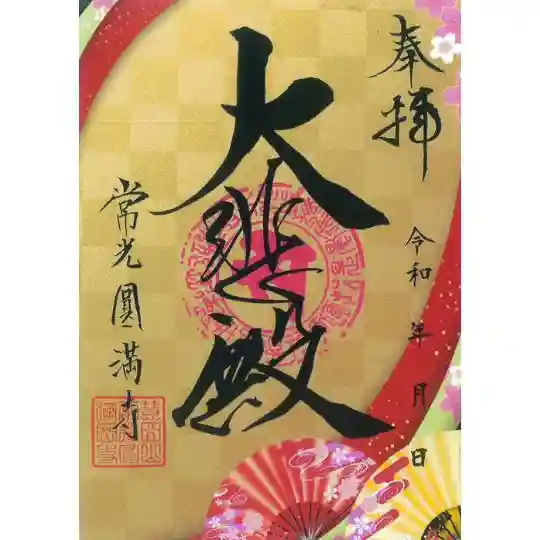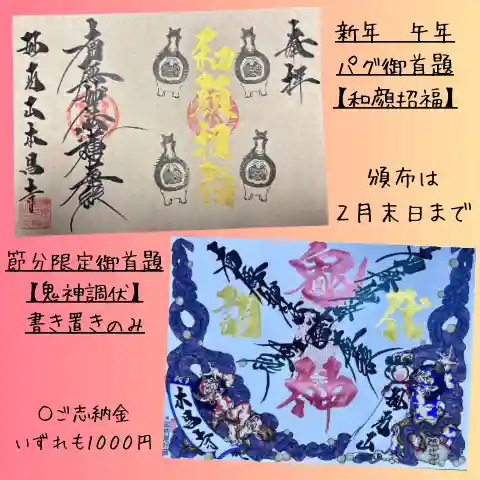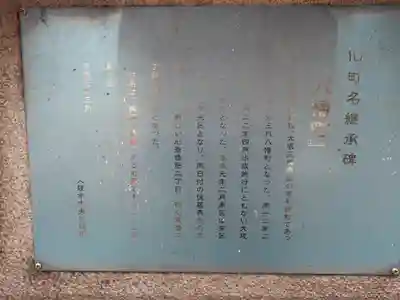みつはちまんぐう
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方御津八幡宮の御由緒・歴史
| ご祭神 | 應神天皇,仲哀天皇,比咩大神 | |
|---|---|---|
| 創建時代 | 伝・仁徳天皇朝 | |
| ご由緒 | 第58代清和天皇の時、貞観二年(860)、筑紫の宇佐の神を山城国男山に遷座の時、西海より初めて此の地に到る。その旧跡であるが故にここに祭った。
|
大阪府のおすすめ3選🎌
広告
歴史の写真一覧
大阪府のおすすめ3選🎌
広告
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ