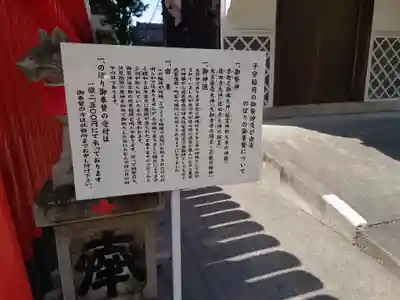ころもじんじゃ
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方挙母神社の御由緒・歴史
| ご祭神 | 《主》高皇産霊神,《配》迩迩芸之命,天万幡比売命,天水分神,国之水分神 | |
|---|---|---|
| 創建時代 | 289年(文治5年) | |
| 創始者 | 源義経家臣 鈴木重善(善阿弥) |
愛知県のおすすめ2選🎌
広告
歴史の写真一覧
愛知県のおすすめ2選🎌
広告
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ