かもじんじゃてんまんぐう
賀茂神社天満宮鳥取県 米子駅
受付/9:00~16:00
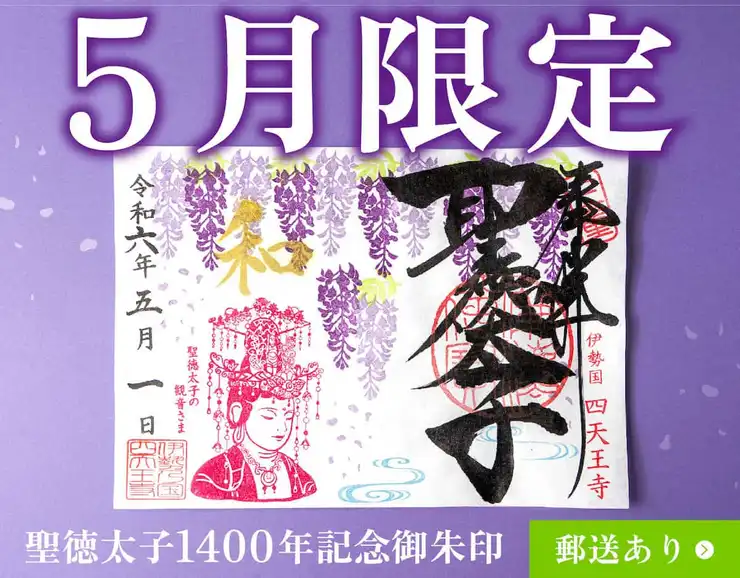
| 御朱印 | |||
|---|---|---|---|
| 限定 | - | ||
| 御朱印帳 | |||
| 駐車場 | 10台程度 |
個人的なことですが,父が病気になり,妻がネットで調べたところ,病気平癒の神社ということで,お参りに行くことにしました🚗相変わらず広くて綺麗な神社です😆社務所で妻と義母が御朱印を授与してもらっていましたが,書き置きのみで初穂料は500円とのことでした。どうか父の病気が悪くありませんように🙏
さてお参りしましょう⛩
随神門の扁額です。
随神門近くのおみくじ授与所です。
拝殿です。
拝殿の扁額です。
本殿です。
おや,目久美神社の御朱印も授与いただけるのかぁ😲
病気平癒の御守りです。初穂料は800円でした🙏
鳥取県米子市、米子城跡の麓にある賀茂神社天満宮を参拝いたしました。 米子市最古の社、米子(旧米子町)の総鎮守社とされています。 創立の年代は不詳ながら、最も古い棟札に「慶長三年霜月二十五日米子総産土賀茂皇大明神再建」と記されており、それ以前に京都上賀茂神社より勧請し創建されたであろう、とされています。 神社周辺の発掘調査によると平安時代には既に人家があり、室町時代には相当の集落が存在したと推測される為、神社創建もこの時代に遡るのではないかと考えられます。 賀茂三笠山(米子城跡)を神体山とする、別雷神(ワケイカズチノミコト)と菅原道真神を主祭神とし、他五社を合祀しています。 社伝には米子の地名の由来もあり、①戦国時代、野田翁次郎というものが老年になっても子供が無く、畏敬の念を込め祈願したところ八十八歳で子供に恵まれたことでが霊験と評判になり、「八十八」に因んで「米子」と言う地名が誕生した。 ②境内にある井戸「宮水」は、まだこの地が「米子」と云う地名が無く「賀茂の浦」と呼ばれていた頃、この地に住む漁民が飲料水を供するために掘ったもので、飲料水→「米を研ぐ水」から、古は「米をとぐ」と云う事を「よなぐ」と云ったので「よなぐ井」→「よなご井」と云った。 天正年間に、戦国武将・吉川元春が飯山に砦(米子城出丸)を築いた際に、此の地の「よなご井」に「米子」と云う文字を当てたので米子という地名が誕生したとする説。 ①の説は話としては面白く、おめでたい説ではありますが、「米子」と云う漢字がありきの説なので、私としては②の説の方がまだ真実味があるのでは、と思いました。 今回、賀茂神社天満宮さんを参拝させて頂いたのは、「米子に立ち寄った際におすすめの神社仏閣は?」と知人に聞いたところ、こちらを勧められたからでした。 なるほど、境内はさほど大きくないですが、綺麗にされていて清々しい雰囲気の神社でした。 宮司さんも気さくにお声がけくださり、御朱印も丁寧に対応戴きました。 ありがとうございます。
賀茂神社天満宮・神社入り口の看板
賀茂神社天満宮・石鳥居
賀茂神社天満宮・米子名水「宮水」
米子名水の一つだそうです。
賀茂神社天満宮・手水舎
賀茂神社天満宮・拝殿
賀茂神社天満宮・本殿
賀茂神社天満宮・神門
稲荷神社天満宮を合祀する際、その本殿屋根を移設したそうです。
御朱印
戌の御神籤
創立の年代は不詳であるが、最も古い棟札に「慶長三年霜月二十五日米子総産土賀茂皇大明神再建」と記されており、それ以前に京都上賀茂神社より勧請し創建された事は明らかである。神社周辺の発掘調査によると平安時代には既に人家があり、室町時代には相当の集落が存在したと推測されるので、神社創建もこの時代にさかのぼるのではないかと考えられる。
当神社は米子(旧米子町)最古の社と言われ、歴代米子城主より社殿の建立、修復、社領金子の寄進、祈願所等、米子城鎮護の社として手厚い保護を受け、米子鎮守の神として厚く尊崇される。鎮座地より南西に城山、北西に米子港、弧を描くように町が広がっており、戦国時代の頃まで神社周辺は「賀茂の浦」と呼ばれていた。その頃、野田翁次郎という者が老年になっても子供が無く、畏敬の念を込め祈願したところ88歳で子供に恵まれた。以来、稀代の霊験と評判になり、「八十八に因んで米子」と言う地名が誕生したと云う伝説がある。また、境内にある井戸は極古井であり、米子の起源に関係する口碑も残っている。昔、「よなご」と云う地名が無く賀茂の浦であった頃、此の地に住む漁民が飲料水を供するために掘ったもので、その頃は賀茂神社境内の西辺りまで湾で海岸の漁民が一部落をつくり暮していた。古は「米をとぐ」と云う事を「よなぐ」と云ったので「よなぐ井」そして「よなご井」と云った。其の後、飯山に吉川元春が砦を築き、其の麓の部落である此の地を「米子」と云う文字を当てたので、「よなご井」から米子の地名が誕生したのである。この井戸は米子三名水の一つ「宮水」と呼ばれ、上水道が普及するまでは町民に親しまれ、飲料水として売り歩かれていたものである。
また、城山を賀茂三笠山と言い、町中を貫流する川を賀茂川(現在加茂川)と呼んだのは全て当神社に因んだものと言われている。往古より賀茂皇大明神と称えていたが、明治元年神社改正により賀茂神社と改め、昭和36年稲荷神社天満宮を合祀し、神社名を「賀茂神社 天満宮」と改称した。
| 名称 | 賀茂神社天満宮 |
|---|---|
| 読み方 | かもじんじゃてんまんぐう |
| 通称 | 賀茂さん |
| 参拝時間 | 受付/9:00~16:00 |
| 参拝料 | なし |
| トイレ | 社務所の隣 |
| 御朱印 | あり |
| 限定御朱印 | なし |
| 御朱印帳 | あり |
| 電話番号 | 0859-22-5780 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |
| メールアドレス | front@kamoten.org |
| ホームページ | http://www.kamoten.org/ |
| お守り | あり |
| SNS |
| ご祭神 | 《合》品陀和気命,事代主神,素盞嗚命,天照大御神,大穴牟遅命,少彦名命,《主》別雷命,菅原道真 |
|---|---|
| 創建時代 | 不詳 |
| ご由緒 | 創立の年代は不詳であるが、最も古い棟札に「慶長三年霜月二十五日米子総産土賀茂皇大明神再建」と記されており、それ以前に京都上賀茂神社より勧請し創建された事は明らかである。神社周辺の発掘調査によると平安時代には既に人家があり、室町時代には相当の集落が存在したと推測されるので、神社創建もこの時代にさかのぼるのではないかと考えられる。
|
| 体験 | 祈祷おみくじお祓いお宮参り絵馬結婚式七五三御朱印お守り祭り伝説 |
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。
ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ



















6
0