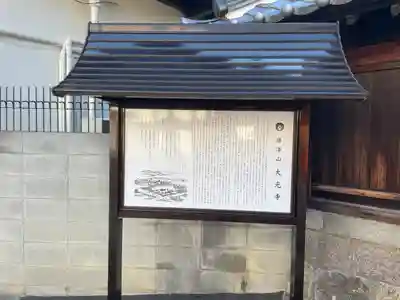とうたくさん ほうごんいん だいこうじ|浄土宗|藤澤山
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方藤澤山 宝厳院 大光寺の御由緒・歴史
| ご本尊 | ・春日大明神作の阿弥陀三尊(ご本尊)安土桃山時代作 ・耳と安産にご利益がある薬師三尊(奈良の薬師寺様より)平安時代作 ・伏見人形として作られた十二神将(頭に十二支)江戸時代作 ・アフロ阿弥陀でお馴染みの木造の五劫思惟阿弥陀像(頭部は寺伝によると善導大師作) | |
|---|---|---|
| 創建時代 | 1260年 | |
| 開山・開基 | 寛海上人 | |
| ご由緒 | 開山は1260年、法然6代目の弟子、寛海上人によります。室町時代の一時期には伏見殿(伏見御所)が焼失したために、栄仁親王(伏見宮家初代)やその子貞成親王(後崇光院)により伏見殿の仮のおすまい(=仮御所)となりました。現在は大手筋商店街の中に位置します。 |
京都府のおすすめ🎌
広告
歴史の写真一覧
京都府のおすすめ🎌
広告
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ