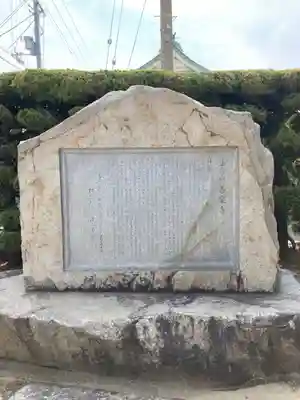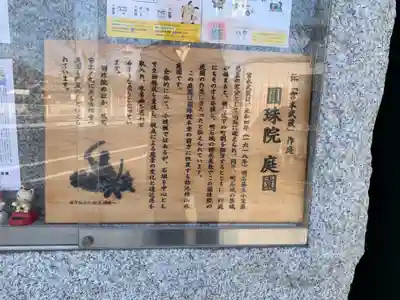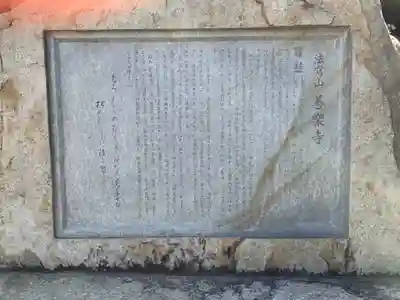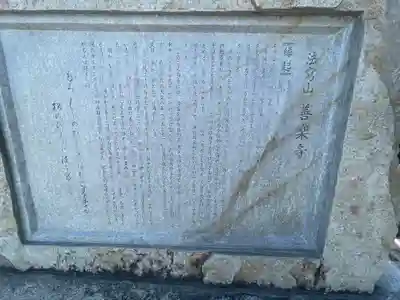ぜんらくじ|天台宗|法寫山
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方善楽寺の御由緒・歴史
| ご本尊 | 地蔵菩薩 | |
|---|---|---|
| 創建時代 | 大化年間(645〜650) | |
| 開山・開基 | 法道仙人 | |
| ご由緒 | 善楽寺は孝徳天皇の大化年中(643〜650)に天竺の高僧法道仙人の開創した。天台宗の大寺院で、明石では最も古い寺である。平清盛ゆかりの地でもあり、源氏物語の舞台にもなるほど知られたところであった。
|
兵庫県のおすすめ2選🎌
歴史の写真一覧
兵庫県のおすすめ2選🎌
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ