てんのうじ|臨済宗妙心寺派|香積山
天王寺福島県 花水坂駅
午前9時から16時30分
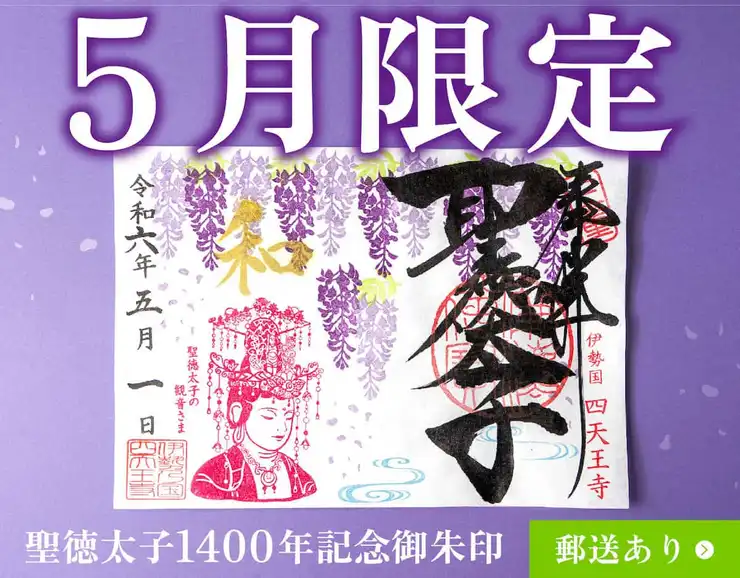
| 御朱印 | |||
|---|---|---|---|
| 限定 | - | ||
| 御朱印帳 | - | ありません | |
| 駐車場 | 立派な駐車場が有ります、何台も、駐車出来ます。 |
| 名称 | 天王寺 |
|---|---|
| 読み方 | てんのうじ |
| 参拝時間 | 午前9時から16時30分 |
| 参拝にかかる時間 | 20〜30分 |
| 参拝料 | 御朱印は1枚につき300円 |
| トイレ | 門を潜り右手 |
| 御朱印 | あり |
| 限定御朱印 | なし |
| 御朱印帳 | なし |
| 電話番号 | 024-542-2439 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |
| 奥州三十三観音霊場 第11番 | 御本尊:聖観音 御詠歌: てらさめと 濁れる世にも じけんして 草木も共に 誓ひもらさず |
|---|---|
| 信達三十三観音霊場 第11番 | 御本尊:聖観世音 御詠歌: 説きおける 法の始めを 天王寺 知るや悟りの 仏ある世に |
| ご本尊 | 聖観世音菩薩 毘沙門天 |
|---|---|
| 山号 | 香積山 |
| 宗旨・宗派 | 臨済宗妙心寺派 |
| 本堂 | 木造平屋建て、寄棟、鉄板葺き、平入、桁行7間、正面1間向拝付き、外壁は真壁造り白漆喰仕上げ。観音堂は木造平屋建て、寄棟、鉄板葺き、平入、桁行3間、正面1間向拝付き、外壁は真壁造り板張り。 |
| 文化財 | 山門は切妻、桟瓦葺き、三間一戸、四脚門、「香積山」の山号額が掲げられています。天王寺の寺宝には「什物」や「経筒」、「三筋壺」などがあり,特に陶製経筒は承安元年(1171)の銘があるもので大変貴重な事から昭和11年(1936)に国指定重要文化財(考古資料)に指定されています。 |
| ご由緒 | 香積山天王寺は福島県福島市飯坂町天王寺に境内を構えている臨済宗妙心寺派の寺院です。案内板によると「 当山天王寺は大阪(難波)・谷中・富国の天王寺とともに日本四天王寺の一寺といわれ第31代用明天皇の開基と伝えられる。用明2年(587年)厩戸皇子(聖徳太子)が物部守屋を討たれ佛法眞密即ち佛の道を修める道場の1つとして建立された。当初は、天皇山天王寺と呼ばれ毘沙門天(北方多聞天)と千手観音・地蔵菩薩を安置したのに初まりという。平安時代文治5年(1190年)源頼朝の平泉攻めで大鳥城落城の時共に兵火により焼失、その後、法燈国師が当地を巡錫で訪れた際に再興、さらに、室町時代初期の応安7年(1375)、智鑑禅師により境内には七堂伽藍の堂宇が再建されています。中世以降、飯坂城の城主を歴任した飯坂氏が篤く庇護し、特に天正3年(1576)には飯坂宗康と春翁正堂和尚が中興し堂宇などを再建し宗康の菩提寺となっています。 |
| 体験 | 仏像御朱印札所・七福神巡り |
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。
ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ
3
0