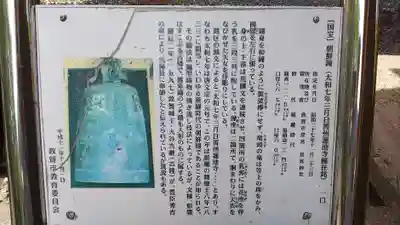じょうぐうじんじゃ
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方常宮神社の御由緒・歴史
| ご祭神 | 天八百萬比咩神(あめのやおよろずひめのかみ) 神功皇后(じんぐうこうごう) 仲哀天皇(ちゅうあいてんのう) | |
|---|---|---|
| ご神体 | 不詳 | |
| 創建時代 | 仲哀天皇二年 | |
| 創始者 | 仲哀天皇 | |
| ご由緒 | 天八百萬比咩命(常宮大神)は上古より此の地に鎮まり給い、今から2,000年前、仲哀天皇の即位2年春2月に天皇皇后御同列にて百官を率いて敦賀に行幸あそばされ、筍飯の行宮を此の地に営まれた。
|
歴史の写真一覧
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ