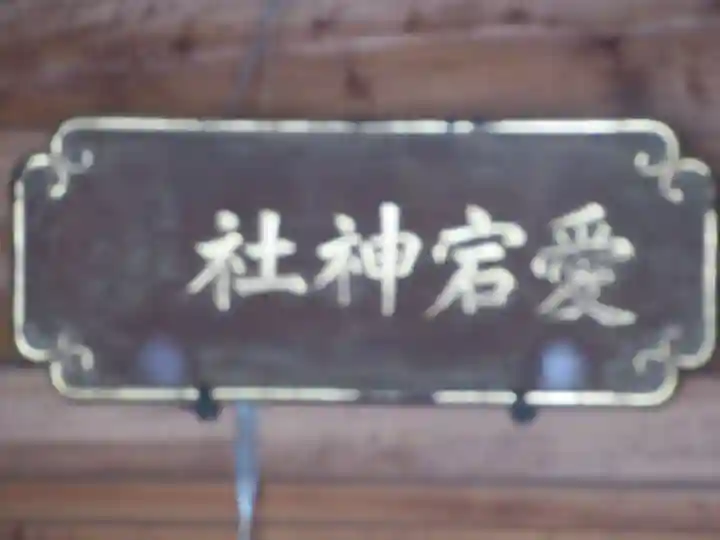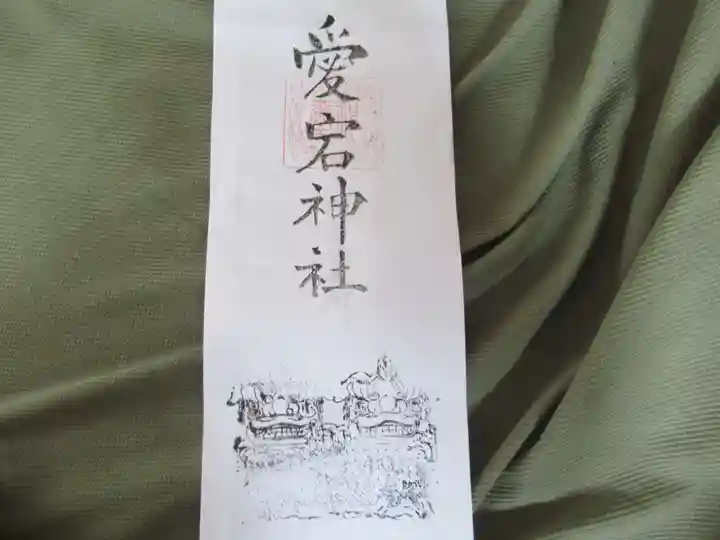あたごじんじゃ
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方愛宕神社のお参りの記録一覧
絞り込み

愛宕神社(青梅)は、青梅市柚木にある神社。旧社格は村社。祭神として火産霊神(ほむすびのかみ)を祀る。
平安時代前期の元慶年間(877年~885年)、即清寺の開基に伴い、その鎮守として標高584mの愛宕山の山頂に創建された。中世においては当地の豪族・三田氏の居城である辛垣城(からかいじょう)の鎮護守とされ、江戸時代には幕府から社領20石の御朱印状を下賜された。なお、明治維新の神仏分離までは即清寺が当社の別当寺を務めた。
明治時代には村社に列格した。昭和初期の1936年に麓に社殿を造営しこれを里宮とし、山頂の社殿を奥宮(奥ノ院)とした。
当社は、JR青梅線・二俣尾駅の南西1.5kmの、愛宕山の裾野に位置している。当社の境内までの長く急な階段が有名で、『青梅の出世階段の神社』と呼ばれ人気を博しているとともに、両脇に約1000本のツツジが植わっており時期になるとかなり美しいとのこと。
今回は、旅行情報サイト<じゃらん>で口コミ数の多い人気神社として紹介されていたので参拝することに。参拝時は週末の午前中で、自分以外には数組の家族連れが急階段にチャレンジしていた。
もっと読む

令和3年のお正月は、青梅市柚木町の愛宕神社に参拝しました。山頂の奥の院まで足を延ばしてお参りしました。愛宕山頂上にある奥の院は、山道を1時間以上かけて登ったところにあります。里山ハイキング程度の準備は必要です。靴はトレッキングシューズか運動靴。水も500㎖ペットボトル1~2本は持っていきましょう。

吉野街道沿いにある一の鳥居です。昭和52年建立の御影石製です。

街道を挟んだ反対側にお祀りされているお地蔵様にも手を合わせました。お顔が風化してしまっているほど、昔からお祀りされているようです。すぐ横にコンビニがあるので、飲み物やおにぎり、おやつなどの軽食は現地でも購入できます。

最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ