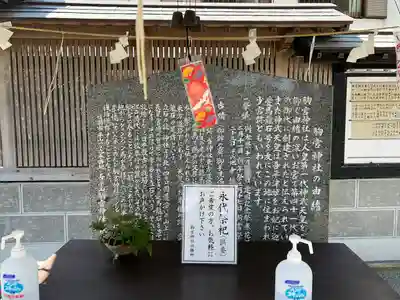こまみやじんじゃ
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方駒宮神社の御由緒・歴史
| ご祭神 | 《主》神武天皇 | |
|---|---|---|
| ご由緒 | 初代天皇である神武天皇の幼少時の少宮趾として伝えられ、「駒宮大明神縁起」によると、弘治2年(1556年)6月には駒宮領二町、足洗田一町を御供田として有していたとされる。
|
歴史の写真一覧
最新の限定御朱印情報が届く!
御朱印メルマガを受け取ろう
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ